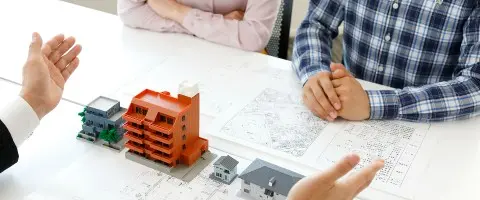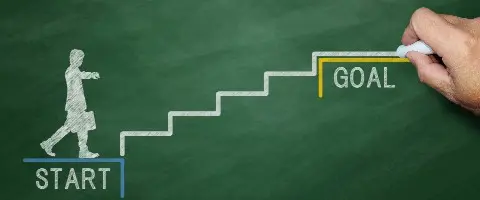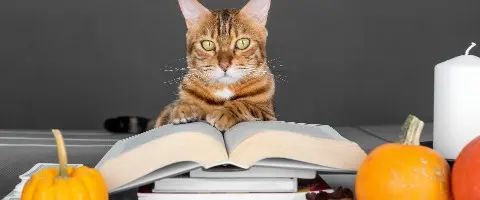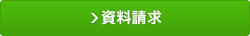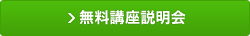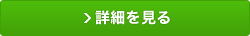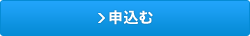宅建とは? 宅建士の仕事とは?資格概要・仕事内容を徹底解説!
宅建とは「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る日本最大規模の国家資格
宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。宅建とは、不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格です。宅建士だけに許された独占業務として、「重要事項の説明」や「35条書面(重要事項書面)への記名」「37条書面への記名」などがあります。

宅建士講座 デジタルパンフレットを閲覧する
宅建とは?宅建士の仕事内容を紹介
宅建とは?
宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。宅建とは、不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格です。
宅建士になるための試験を宅建試験といいます。宅建試験に合格し登録実務講習を経て登録することで、宅建士として不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に対し「登記」「不動産の広さ」「飲用水・電気・ガスの供給施設」「キャンセルの際の取り決め」など、契約の根幹に関わる「重要事項の説明」をすることができるようになります。
不動産に関する重要事項の説明などは宅建士だけに許された独占業務です。また、不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)といった不動産取引をおこなう場合、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられており、宅建士の需要は高いといえます。

『無料』令和7年度(2025年度)宅地建物取引士試験
本試験解答解説を閲覧する
令和7年度(2025年度)に実施された宅建士の本試験問題に加えて、TACが徹底的に本試験を分析した上でまとめあげた全問題の解答解説や総評を無料で簡単にご請求いただけます!
各問題の難易度や科目別の分析も掲載されていますので、これから合格を目指す方には必見の内容です。自由に閲覧・印刷できるだけでなくPDFダウンロードも可能です。以下のフォームにご入力の上、ご請求ください。
初めて受験される方も再度挑戦される方もお見逃しなく!

個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
重要事項の説明│宅建士の独占業務
不動産を購入しようとする人・借りようとする人がその物件について無知のまま取引してしまうと、後々思わぬ損害を被ったりすることがあります。そこで、取引物件の「重要な事項」について、有資格者である宅建士が取引相手に内容を説明する必要があります。重要事項は登記、敷地面積、飲用水・電気・ガス等のインフラの供給施設、契約の解除方法、水害ハザードマップなど多岐にわたります。
35条書面(重要事項書面)への記名│宅建士の独占業務
また、責任の所在を明らかにするために、重要事項の説明だけでなく重要事項書面に宅建士自らが記名する必要があります。
37条書面への記名│宅建士の独占業務
代金や支払い方法、引き渡しの時期などを記した書面への記名です。不動産取引が成立すると、宅建士が当書面にに記名し、売主・買主双方に交付しなければなりません。
宅建を持つメリットは?宅建があるとどうなる?
取得した宅建はどう活かせるでしょうか?また、あるとどうなるのでしょうか?
まず、宅建資格を取得し、登録講習・登録等の手続を踏むことで、「宅建士(宅地建物取引士)」になることができます。宅建士(宅地建物取引士)になれば、前述のとおり不動産取引・契約の場面で有資格者として活躍することができます。また、宅建士(宅地建物取引士)になる他にも色々なメリットがあります。いくつかの例を挙げてみましょう。
1
就職・転職に有利
宅建があるとどんなメリットがあるでしょう?まず、不動産業界関連への就職や転職には特に大きなメリットとなります。また、それ以外にも建築業界、金融業界などへの就職・転職活動でも有利になることがあります。昨今、全国に支店を展開する大手企業やIT業界でもニーズが高まってきています。
2
独立開業やキャリアアップも狙える
資格を持つことで、社会的に一定水準以上の知識を有することを証明することができます。また、昇格の条件に宅建の取得を必須とする企業もあります。さらに、独立開業やキャリアアップにもつながることは、大きなメリットといえるでしょう。不動産鑑定士や司法書士などの資格と宅建を組み合わせることで、業務の幅を大きく広げられるチャンスもあります。
3
資格手当がつく場合もある
宅建をなぜ取得すべきか?資格手当がつくことで年収アップが図れる点も挙げられます。企業にもよりますが、毎月の給与のベースが5千円~5万円アップすることもあります。合格は一生有効ですから、資格を取得して損は全くありません。
宅建の資格が役立つ業界は?
宅建を役立てるのに最適な業界はどこでしょうか?例を挙げてみます。
不動産会社│宅建が役立つ業界
不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)をおこなう会社では従業員5名につき1名以上の宅建士を設置することが義務付けられています。そのため、不動産会社で活躍をしたい方は宅建資格が必須とっても過言ではありません。
建設会社│宅建が役立つ業界
建築会社では自社で建築した物件を販売する際に宅建の資格が必要となります。説明する内容が「明確な根拠」とともに予めわかっているだけに、自社物件のウリを顧客にアピールしやすくなります。
金融機関│宅建が役立つ業界
金融機関では不動産の担保価値を評価して融資する業務が多いため、宅建の知識は非常に有益です。また不動産販売会社を傘下に持つ銀行も多く、籍を金融機関・不動産販売会社のどちらに置いていても知識を活用できます。
不動産管理会社│宅建が役立つ業界
不動産管理会社では、不動産分譲の仲介をおこない、さらに管理も自社でおこなう会社が増えており、宅建の資格は非常に有効です。
さらに管理会社で必須の資格となる「管理業務主任者」の試験内容は、宅建試験の内容と酷似しているため、取得しやすいメリットもあります
宅建の試験概要
宅建の試験日・スケジュール
令和8年(2026年)10月18日(日)13:00~15:00 ※予定
試験当日は受験の注意事項説明が始まる12:30(登録講習修了者は12:40)までに自席に着席。
試験時間中の途中退出は認められておらず、途中退出した場合は棄権または不正受験とみなし採点されません。
宅建は年1回実施されます。例年10月の第3日曜日に実施されますが、過去には新型コロナウィルス感染症の対策として試験会場の縮小が図られ、10月と12月の2回に割り振られて実施されるケースがありました。この場合、どちらの月で受験するかを選択することはできません。また、振り分けの方法は公開されていません。
6月 実施告知
7月 申込受付開始
10月 宅建士本試験
宅建の合格発表
参考:令和7年(2025年)11月26日(水)
合格者の受験番号が一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページで掲載された後、合格証書が郵送にて届きます。
宅建の試験会場
47都道府県
受験申し込みをした県(受験票が郵送で届く居住地)が試験会場になります。学校や仕事の都合で現住所と居住地が異なる場合でも居住地に合わせて受験することができます。
宅建の受験費用
8,200円
インターネット申込の場合は、指定のクレジットカードにより、またはコンビニエンスストアから納入します。郵送申込の場合は、都道府県毎に、
いったん振り込んだ受験手数料は、申し込みが受付されなかった場合や試験中止の場合を除いて返還されません。
消費税及び地方消費税は非課税です。
宅建の申込方法
宅建試験を受験する場合、申込みの方法は以下の2通りあります。
(1)インターネットを使って申し込む方法(参考)
令和7年7月1日(火)9:30~7月31日(木)23:59まで
原則として24時間利用可能。
(2) 官公庁・書店等で願書を入手して郵送で申し込む方法(参考)
試験案内配付期間:令和7年7月1日(火)~7月15日(火)
申込み受付期間:令和7年7月1日(火)~7月15日(火)
郵送は簡易書留郵便として郵便局の窓口で受付されたもので、消印が上記期間中のもののみ受理されます。
令和8年度宅地建物取引士資格試験申込期間の確定版は2026年6月上旬に官報にて広告、及び「一般財団法人不動産適正取引推進機構」のホームページにも掲載されます。
参考:一般財団法人不動産適正取引推進機構
宅建士試験について詳しく知ろう
宅建の試験内容
宅建の受験形態は、4肢択一のマークシート方式です。出題数は50問。採点は1問1点、50点満点で計算されます。
宅建試験は合格点が明確に決められている絶対評価試験ではなく、受験人数や合格率の調整のために合格点が変動する相対評価試験です。
試験時間は2時間です。
-
出題形式
4肢択一(マークシート式)
-
出題数
50問(1問1点で採点)
-
試験時間
2時間
-
採点方式
相対評価
宅建の試験科目
宅建試験に出題される科目は以下の4種類、「民法等」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」です。それぞれ問題数が異なり、対策方法も様々です。
民法等(14問出題)│宅建の試験科目
不動産を購入する際などに交わす「契約書」に記載されているトラブルが起こった場合の処理方法や、トラブルを未然に防ぐための約束事を定めた法律です。特に「不動産の取引」に関係した部分から出題されます。
宅建試験対策における「民法等」とは・・・
最大の関門です。他の科目よりも出題範囲がずっと広く、深入りしても満点を取るのは至難のワザです。したがって、この科目をいかに絞り込めるがかが合否のポイントとなります。
民法等│宅建の過去問
(不動産の)売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
-
正解
× 損害賠償請求ができます。
宅建業法(20問出題)│宅建の試験科目
お客さんに不利が生じないように、宅建業者や宅地建物取引士の仕事上のルールを定めています。業者はもちろんのこと、皆さんがマンションなどの賃貸借や売買をする際にも「宅建業法」の知識が大きな味方になります。
宅建試験対策における「宅建業法」とは・・・
大きな得点源となる科目です。難易度はそこまで高くないですが、どのような問題が出題されても正解できるよう知識を正確にインプットする必要があります。得意科目にできるよう、過去問を使って訓練しましょう。
宅建業法│宅建の過去問
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。
-
正解
◯
法令上の制限(8問出題)│宅建の試験科目
「住み良い街づくり」「安全な家づくり」をしていくためのルールを定めた法律です。あまり馴染みがないかもしれませんが、学習していくと自分の住んでいる街を見る目が変わるはずです。
宅建試験対策における「法令上の制限」とは・・・
学ぶべき法令が多いためか、10人中8人が「不得意科目」と答える科目です。ただし、出題されるパターンはある程度決まっているため、得意科目にすれば安定して得点できる科目でもあります。
法令上の制限│宅建の過去問
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
-
正解
× 義務ではなく、「定めることができる」だけです。
その他関連知識(8問出題)│宅建の試験科目
不動産購入の際にかかる税金制度のことや、土地・建物の安全性や耐久性といった不動産にまつわるさまざまな知識を学習します。
宅建試験対策における「その他関連知識」とは・・・
年度によって難易度に差があり、かなり勉強しても歯が立たないことがある反面、全く勉強していなくても解けることもあります。
その他関連知識│宅建の過去問
土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。
-
正解
× 不動産取得税の課税対象は「土地及び家屋」のため、立木は対象外です。
民法等(14問出題)│宅建の試験科目
不動産を購入する際などに交わす「契約書」に記載されているトラブルが起こった場合の処理方法や、トラブルを未然に防ぐための約束事を定めた法律です。特に「不動産の取引」に関係した部分から出題されます。
宅建試験対策における「民法等」とは・・・
最大の関門です。他の科目よりも出題範囲がずっと広く、深入りしても満点を取るのは至難のワザです。したがって、この科目をいかに絞り込めるがかが合否のポイントとなります。
(不動産の)売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
-
正解
× 損害賠償請求ができます。
宅建業法(20問出題)│宅建の試験科目
お客さんに不利が生じないように、宅建業者や宅地建物取引士の仕事上のルールを定めています。業者はもちろんのこと、皆さんがマンションなどの賃貸借や売買をする際にも「宅建業法」の知識が大きな味方になります。
宅建試験対策における「宅建業法」とは・・・
最大の関門です。他の科目よりも出題範囲がずっと広く、深入りしても満点を取るのは至難のワザです。したがって、この科目をいかに絞り込めるがかが合否のポイントとなります。
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。
-
正解
◯
法令上の制限(8問出題)│宅建の試験科目
「住み良い街づくり」「安全な家づくり」をしていくためのルールを定めた法律です。あまり馴染みがないかもしれませんが、学習していくと自分の住んでいる街を見る目が変わるはずです。
宅建試験対策における「法令上の制限」とは・・・
学ぶべき法令が多いためか、10人中8人が「不得意科目」と答える科目です。ただし、出題されるパターンはある程度決まっているため、得意科目にすれば安定して得点できる科目でもあります。
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
-
正解
× 義務ではなく、「定めることができる」だけです。
その他関連知識(8問出題)│宅建の試験科目
不動産購入の際にかかる税金制度のことや、土地・建物の安全性や耐久性といった不動産にまつわるさまざまな知識を学習します。
宅建試験対策における「その他関連知識」とは・・・
年度によって難易度に差があり、かなり勉強しても歯が立たないことがある反面、全く勉強していなくても解けることもあります。
土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。
-
正解
× 不動産取得税の課税対象は「土地及び家屋」のため、立木は対象外です。
宅建の合格率・合格基準点
過去10年間の宅建の合格率は15%~18%で、合格基準点は31~38点(50問中)です。
つまり、約75%を正解できれば合格できます。
直近の試験傾向も下記のようになっており、大きな変化はありません。
令和7年(2025年)試験の合格率は18.7% ※受験者 245,462人 のうち合格者 45,821人
| 実施年度 | 申込者数(名) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 | 合格基準点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 306,099 | 245,462 | 45,821 | 18.7% | 33点 |
| 令和6年度 | 301,336 | 241,054 | 44,992 | 18.6% | 37点 |
| 令和5年度 | 289,096 | 233,276 | 40,025 | 17.2% | 36点 |
| 令和4年度 | 283,856 | 226,048 | 38,525 | 17.0% | 36点 |
| 令和3年度[12月] | 39,814 | 24,965 | 3,892 | 15.6% | 34点 |
| 令和3年度[10月] | 256,704 | 209,749 | 37,579 | 17.9% | 34点 |
| 令和2年度[12月] | 55,121 | 35,261 | 4,610 | 13.1% | 36点 |
| 令和2年度[10月] | 204,163 | 168,989 | 29,728 | 17.6% | 38点 |
| 令和元年度 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17.0% | 35点 |
| 平成30年度 | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.6% | 37点 |
| 平成29年度 | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.6% | 35点 |
| 平成28年度 | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.4% | 35点 |
| 平成27年度 | 243,199 | 194,926 | 30,028 | 15.4% | 31点 |
実績で選ぶなら「講師力」のTAC
2024年度 宅地建物取引士試験
TAC本科生カリキュラム修了者※1
合格率 75.5%!
※1 TAC本科生カリキュラム修了者とは、2024年合格目標のTAC本科生コース(通学・通信)を受講され、カリキュラムに含まれる答案練習の提出率が70%以上かつ、直前答練(全4回)と全国公開模試の平均正答率が70%以上の結果を出された方を指します。なお、当合格率は上記のTAC本科生カリキュラム修了者421名中318名の割合で算出しています。
※2 「全体合格率の約4.1倍」は、TAC本科生カリキュラム修了者の合格率(75.5%)を2024年宅建士試験合格率(18.6%)で除して算出し、小数点第2位を四捨五入しています。
宅建に合格したら?資格証明書発行まで
宅建士の試験に受かると、受験地の都道府県知事の登録を受けることができます。そして、登録を受けた都道府県知事から宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けることで、晴れて宅建士として業務をおこなうことができるようになります。
また、登録の際、宅建士証交付の際は、その都度国が実施する講習を受講する必要があります。ただし、登録の場合は宅建業の実務経験が2年以上ある方、宅建士証交付の場合は試験合格後1年以内の方は各講習が免除されます。
登録は一度してしまえば一生有効ですが、宅建士証の有効期間は5年なので、引き続き宅建士として業務をおこなうためには更新が必要になります。
全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。
まとめ
1
宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、不動産取引の専門家であることを示す資格
2
宅建は不動産会社・建築会社・金融機関・不動産管理会社への就職、転職に有利な資格
3
宅建試験は4肢択一のマークシート式で50問が出題され、試験時間は2時間
5秒で診断!最適な学習コースを知る
宅建の学習ははじめてですか?
- はい
- いいえ
宅建士(宅地建物取引士)についてもっと知ろう!
宅建は毎年20万人が受験する日本一の人気国家資格です。
宅建とはいったいどんな資格で、宅建士になるとどんな仕事ができるのか?また、宅建の資格を取るとどんなメリットがあるのか?わかりやすく解説します。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験試験の受験申込・試験実施日程・試験概要をご案内します。しっかりとスケジュールを確認して、申し込み忘れなどのないように準備・手続きをしておきましょう。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)の資格取得をしたい方は、まずは概要や試験問題の傾向を理解しましょう。TACが宅建士試験の内容を詳しく解説します。民法改正によって2020年度から試験内容に変化があったことなど、知っておきたいポイントまでチェックしましょう。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)の合格率ってどれくらい?出題範囲は?何時間くらいの勉強で合格できるの?皆さんが感じる素朴な疑問にお答えします。続きを読む »
宅建には毎年多くの受験生がいますが、勉強法・学習法がわからないという方も多いと思います。ここではTAC式の勉強法・学習法をご紹介します。試験の特徴や配点比率などに触れながらわかりやすく解説していきます。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験の合格までどれくらいの勉強時間が必要なの?総勉強時間は?科目別の内訳は?勉強はいつから始めるとよいの?TACが詳しく解説します。続きを読む »
仕事をしながら宅建士に合格するにはどのように学習すればよいの?限られた時間で効率よく学習し合格をつかみ取るために、必要なあれこれを合格者の実体験をもとに解説します。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)の資格を持っている人は就職に有利です。また、資格取得がプラスに働く業界が幅広いため、大学生のうちに取っておく資格としてもおすすめです。TACが宅建士の就職に関する内容を解説します。さらに、有利になる理由や取得をおすすめする人の特徴まで解説します。続きを読む »
あまりお金をかけずに宅建士(宅地建物取引士)の資格取得をしたい方は、独学で合格できないかと考えるでしょう。この記事では、宅建士試験に向けた独学方法予備校を利用した場合と比較しながら解説します。勉強方法ごとのメリットやデメリット、独学でのポイントなど、知っておきたい内容を確認しましょう。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験合格発表に合わせて、合格基準点や合格率、試験傾向を分析しました。最新の宅建試験、結果はどのようなものだったのでしょうか?続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験において過去問を使う意味とは何?入手方法は?活用方法は?TACが詳しく解説します。続きを読む »
TACが考える宅建士(宅地建物取引士)試験の攻略ポイントを解説します。完璧主義を捨てる!問題を解くことを恐れない!Inputは学習の順序を大切に!大切な要点をまとめました。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)を受験する際に覚えたい豆知識と用語の一部を一覧表にしました。日常使うものとは異なる、ちょっとクセのある法律用語。どんなものがあるか覗いてみましょう!続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験合格を目指すなら、「講師のフォローが手厚い」「教材が充実している」「合格実績のある」TACです。毎年大勢の合格者を送り出しているTACで合格を目指しましょう!続きを読む »