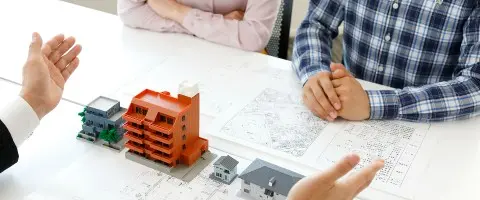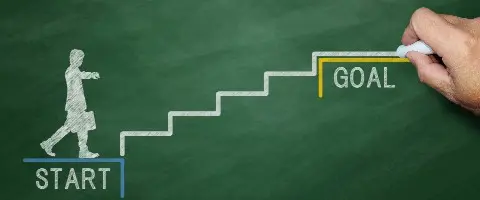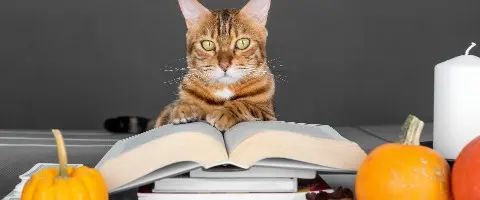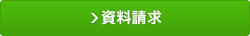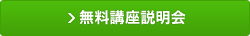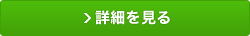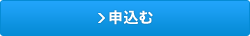宅建士(宅地建物取引士)試験 合格発表!
合格基準点・合格率・試験傾向分析
令和7年度(2025年度)宅建士試験は、前年との比較で、令和6年度との比較で、申込者は4,763名の増加、受験者数は4,226名の増加、合格者数は829名の増加となりました。合格率は18.7%で過去数年で最も高い数字となりました。
このページでは令和7年度(2025年度)宅建士試験を分析します。受験者の人数や年齢、職業構成比を見てみましょう!

宅建士講座 デジタルパンフレットを閲覧する
令和7年度 宅建士(宅地建物取引士)試験の
合格者数・合格基準点・合格率等
(一財)不動産適正取引推進機構より、令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の実施結果が発表されました。合格者には合格証書等を簡易書留郵便にて発送されるほか、(一財)不動産適正取引推進機構のホームページでも合否の確認や合否判定基準、試験問題の正解番号を確認することができます。なお、不合格者への結果通知はおこなわれません。
申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率│令和7年度(2025年度)宅建士試験
令和7年度宅建士試験は、10月19日(日)に全国で実施され、結果は以下の通りです。
令和6年度との比較で、申込者は4,763名の増加、受験者数は4,226名の増加、合格者数は829名の増加となりました。合格率は18.7%となりました。
| 令和7年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|
| 申込者数 |
306,099名 <内訳> |
301,336名 <内訳> |
| 受験者数 |
245,462名 <内訳> |
241,436名 <内訳> |
| 受験率 | 80.2% | 80.1% |
| 合格者数 |
45,821名 女性:17,490名 一般申込者 33,505名 登録講習修了者 12,316名 |
44,992名 女性:17,593名 一般申込者 34,170名 登録講習修了者 10,822名 |
| 合格率 |
18.7% うち登録講習修了者 24.2% |
18.6% うち登録講習修了者 21.9% |
『無料』令和7年度(2025年度)宅地建物取引士試験
本試験解答解説を閲覧する
令和7年度(2025年度)に実施された宅建士の本試験問題に加えて、TACが徹底的に本試験を分析した上でまとめあげた全問題の解答解説や総評を無料で簡単にご請求いただけます!
各問題の難易度や科目別の分析も掲載されていますので、これから合格を目指す方には必見の内容です。自由に閲覧・印刷できるだけでなくPDFダウンロードも可能です。以下のフォームにご入力の上、ご請求ください。
初めて受験される方も再度挑戦される方もお見逃しなく!

個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
合否判定基準│令和7年度(2025年度)宅建士試験
令和7年度(2025年度)宅建士試験の合格判定基準点は33点です。
登録講習終了者の合格判定基準点は28点です。
合格者の平均年齢・職業別構成比率│令和7年度(2025年度)宅建士試験
合格者の平均年齢│令和7年度(2025年度)宅建士試験
| 令和7年度:参考 | 前年(令和6年度):参考 | |
|---|---|---|
| 平均年齢 |
36.2歳 男性:36.4歳 女性:35.9歳 |
35.9歳 男性:36.2歳 女性:35.4歳 |
職業別構成比率│令和7年度(2025年度)宅建士試験
| 不動産業 | 33.2% |
|---|---|
| 金融関係 | 8.1% |
| 建設関係 | 8.7% |
| 他業種 | 27.9% |
| 学生 | 10.9% |
| その他 ※主婦を含む | 11.3% |
宅建試験合格者で宅建業の実務に2年以上従事している者は、宅地建物取引士資格登録を経て、宅地建物取引士となることができます。
宅建業の実務経験が2年に満たない方が資格登録をする場合、「登録実務講習」を受講・修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地建物取引士資格の登録要件を満たすことができます。
お問い合わせ・試験実施機関
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3丁目8番21号 第33森ビル3階
試験部(宅建試験等)
電話:03-3435-8181
TACにまかせてください!今始めるならこのコース
合格者必見!!「TAC宅建士登録実務講習」~宅建士試験合格後もTACにお任せください!~
宅建士(宅地建物取引士)についてもっと知ろう!
宅建は毎年20万人が受験する日本一の人気国家資格です。
宅建とはいったいどんな資格で、宅建士になるとどんな仕事ができるのか?また、宅建の資格を取るとどんなメリットがあるのか?わかりやすく解説します。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験試験の受験申込・試験実施日程・試験概要をご案内します。しっかりとスケジュールを確認して、申し込み忘れなどのないように準備・手続きをしておきましょう。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)の資格取得をしたい方は、まずは概要や試験問題の傾向を理解しましょう。TACが宅建士試験の内容を詳しく解説します。民法改正によって2020年度から試験内容に変化があったことなど、知っておきたいポイントまでチェックしましょう。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)の合格率ってどれくらい?出題範囲は?何時間くらいの勉強で合格できるの?皆さんが感じる素朴な疑問にお答えします。続きを読む »
宅建には毎年多くの受験生がいますが、勉強法・学習法がわからないという方も多いと思います。ここではTAC式の勉強法・学習法をご紹介します。試験の特徴や配点比率などに触れながらわかりやすく解説していきます。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験の合格までどれくらいの勉強時間が必要なの?総勉強時間は?科目別の内訳は?勉強はいつから始めるとよいの?TACが詳しく解説します。続きを読む »
仕事をしながら宅建士に合格するにはどのように学習すればよいの?限られた時間で効率よく学習し合格をつかみ取るために、必要なあれこれを合格者の実体験をもとに解説します。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)の資格を持っている人は就職に有利です。また、資格取得がプラスに働く業界が幅広いため、大学生のうちに取っておく資格としてもおすすめです。TACが宅建士の就職に関する内容を解説します。さらに、有利になる理由や取得をおすすめする人の特徴まで解説します。続きを読む »
あまりお金をかけずに宅建士(宅地建物取引士)の資格取得をしたい方は、独学で合格できないかと考えるでしょう。この記事では、宅建士試験に向けた独学方法予備校を利用した場合と比較しながら解説します。勉強方法ごとのメリットやデメリット、独学でのポイントなど、知っておきたい内容を確認しましょう。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験合格発表に合わせて、合格基準点や合格率、試験傾向を分析しました。最新の宅建試験、結果はどのようなものだったのでしょうか?続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験において過去問を使う意味とは何?入手方法は?活用方法は?TACが詳しく解説します。続きを読む »
TACが考える宅建士(宅地建物取引士)試験の攻略ポイントを解説します。完璧主義を捨てる!問題を解くことを恐れない!Inputは学習の順序を大切に!大切な要点をまとめました。続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)を受験する際に覚えたい豆知識と用語の一部を一覧表にしました。日常使うものとは異なる、ちょっとクセのある法律用語。どんなものがあるか覗いてみましょう!続きを読む »
宅建士(宅地建物取引士)試験合格を目指すなら、「講師のフォローが手厚い」「教材が充実している」「合格実績のある」TACです。毎年大勢の合格者を送り出しているTACで合格を目指しましょう!続きを読む »