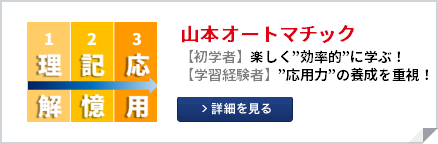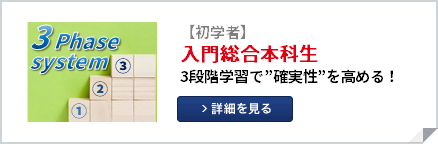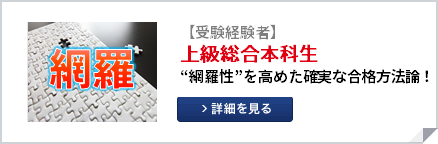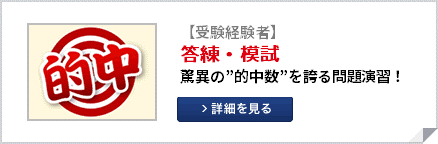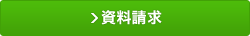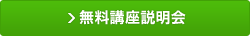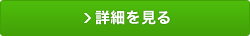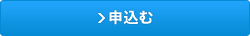合格体験記
低い本試験合格率でもTAC本科生の多くが合格!
実績から示された合格者の“本音”をご覧ください!

司法書士講座 デジタルパンフレットを閲覧する
合格報告会

「合格報告会」をTAC新宿校で実施しました。会の中では実務家の先生による「新人研修、就職、独立、実務」等の体験談や、TAC講師による「特別研修、認定考査対策」など、合格後に役立つ講演を実施しました。
合格報告会に参加された方から喜びのメッセージをいただきました!
一発合格者特集
一発合格者インタビュー
山本オートマチックを受講し、令和7年度試験にて午後の部択一式を単独1位で見事一発合格を果たした橋本鎌多さんと、山本・西垣両講師が、合格者を多数輩出する山本オートマチックの魅力をお伝えします。
一発合格者 合格体験記
例年「一握り」と言われる一発合格者。
難関試験として知られる司法書士試験に、なぜ一発合格できたのか。
2回目以降の受験生と比べて、勉強に充てた時間は決して長くはありません。
そのような状況下で、どのように一発合格を掴み取ったのでしょうか?
一発合格者とは、2025年度司法書士試験対策用TAC初学者向けまたは中上級者向けコースを受講し、その後初回の試験(2025年度司法書士試験)に合格された方です(一般的に言う「お試し受験」は受験回数に含めておりません)。
受験回数、学習時間等の内容は、体験記ご提出時にご本人様に申告いただいた内容をもとに記載しております。また、受講講座名は原則として最新年度の名称で表記しています。
各種コースや講座のカリキュラムは、受講生を対象に実施しているアンケートをもとに、毎年見直しを行っております。そのため、体験記に記載されているものから名称・内容等が変更される場合や販売を終了する場合もございます。最新情報は案内書等をご確認ください。
村山 翔輝 さん インプットもアウトプットもできるオートマテキスト
2025年合格目標:山本オートマチック<20ヵ月総合本科生>

【受講講座】
●「山本オートマチック<20ヵ月総合本科生>」Web通信講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】学生 【合格時(合格年の直前期)の職業】学生
【得意科目】民法・不動産登記法 【不得意科目】商法(会社法)・商業登記法・
【1日の平均学習時間】5時間 【学習開始時からの総学習時間】2500時間~3000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
大学一年生の当時、将来について考える機会があり、そのとき資格者として生涯専門業務で人を助けることがしたいと漠然と考えていました。大学在学中に資格を取得することが理想であったため、司法書士という資格を知ったときに直感的に選びました。
<学習時の環境>
大学生ということもあり、多くの授業を取りながらサークル活動、バイトを両立させていました。直前期に近づくと、バイトを辞めましたが、大学の授業とサークル活動はやめることなく両立させました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
テキストの量を見たとき、司法書士が難関資格ということが分かり、自分の能力では独学で受かることはできないなと思いました。また、短期合格を目指していたため、独学で勉強するという選択肢はありませんでした。
<TACを選んだ理由>
TACは大手予備校であり、かつ豊富な合格実績があったため選びました。また、予備校について調べていくうちに山本先生のオートマは楽しく勉強することができそうだと思ったことが大きかったです。ウサギと亀の話が強く印象に残り、ビビッときました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
学習スタイルとしてはアクティブリコールを活用していました。これは、講義で見た内容を復習したのち、寝る前や起きた後、隙間時間などに真っ白なノートに講義の内容を書き出す勉強法です。思い出そうとすることで脳に負荷をかけることができました。そのほかには、テキストの読み込みやでるトコの活用、過去問の周回を行いました。択一に関しては基本的に予習することはなく、忘却曲線を意識しながら復習中心の学習スタイルでした。直前期に関しては、間違いノートの作成、付箋での覚えてないところの抽出作業にも取り組みました。直前期に間違いノートを作ることで重点的に鍛えることができ、とても力がついたと思います。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
私は20ヵ月の期間で勉強していたので、比較的無理なく学習することができました。学習開始時期は9月頃でしたが、その年中に民法の債権まで、2月までに民法を終わらせ、そこから6月までに不動産登記法を学習しました。その後、9月までは民法と不動産登記法を繰り返し復習し、ほぼ完ぺきにしていました。この学習ペースで大丈夫なのかなと不安でしたが、出題問題が多い民法と不動産登記法をしっかり学習できたことが後々よかったなと感じています。
そこから9月から年内に不動産登記法の記述の基礎講座と会社法・商業登記法を仕上げました。年明けから4月までは商業登記の記述とマイナー科目の学習を進め、直前期は総復習の時間に当てることができました。
学習時に意識したポイントは、わからないことがあってもとまらないことです。講義を進めることと復習を両立させることを意識しました。また、講義の受講日から時間を空けずに何度も復習することも意識しました。
記述式に関しては、オートマの教科書と過去問で十分に満点近くとることができます。特にオートマの論点別の過去問は、ボリュームがある過去問を効率よく論点別に学習することができ、とても効果的でした。記述式はしっかり講義前に自分で予習、間違い合わせをすることが大切だと思います。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
不動産登記法や会社法など、日常生活では関わりが少ない教科に進むたびに苦労しました。苦手な科目は全体像を素早くつかみつつ、何度も復習することが大切だと思います。また、本当にわからないことがあれば飛ばしてもいいと思います。あとから復習していくうちにわかってきます。
これらの教科は、記述をしていくうちに理解が深まっていくので、記述式に進む前に基礎をしっかりやりこんでいくことが大事でした。
■TACの良かった点【講師】
山本先生の講義はメリハリがあり、どこが必要であるか、どこが必要でないかを明確に伝えてくれるので、それを信じて学習すればよかったです。また、法律書学者である私にも楽しくわかりやすい講義であったため、初学者に非常におすすめだと感じました。
■TACの良かった点【教材】
テキストは図表があり、過去問も載っていて、インプットとアウトプットの両方ができてよかったです。過去問に関しては肢別だったため、隙間時間にパパっと取り組むことができました。テキストとでるトコ、過去問をやりつくしただけで本試験で高得点を取ることができました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
20ヵ月本科生は長期ということもあり、日常生活と両立しながら無理なく勉強することができました。
民法と不動産登記法を重点的に学習できるカリキュラムであったため基礎がしっかり身につき、直前期にマイナーや記述に時間を取ることができました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
直前期から毎週ある答練、模試のおかげで自身のモチベーションアップにつながりました。いい結果であれば「もっと上を目指そう」、悪い結果であれば「もっと頑張ろう」と毎週頑張ることができました。記述に関して自分では気づかないところを添削していただくことによって、細かいところまで間違いに気くことができました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
自分自身あまりフォロー制度は使わなかったのですが、オンラインホームルームはアーカイブで毎月視聴していました。オンラインホームル―ムは学習のペースメーカになってくれました。また、毎月喝を入れなおす良い機会だったと思います
■勉強以外の部分
早寝は早起き、湯船にしっかりつかる、健康なごはん、週二回以上の運動を心掛けていました。
長期にわたる受験生活の中で一番怖かったのが病気になったり気が病んだりすることだったので、自分は勉強以外の面により力をいれていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
講師のいうこと、ペースを信じて毎日コツコツ続ければ絶対力がつきます。
この試験は特別な才能は必要なく、愚直に続ければ誰でも合格できます。自分に自信をもって、自信をつけるために毎日と戦って頑張っていってください。
角田 憲治 さん 講師のことを信じ、合格へ一直線
2025年合格目標:山本オートマチック<1.5年総合本科生>

【受講講座】
●「山本オートマチック<1.5年総合本科生>Web通信講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】補助者 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法 【不得意科目】商法(会社法)・商業登記法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】2500時間~3000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
私が司法書士という職業を知ったのは、動画配信サイトの投稿者が司法書士であったことです。その後、前職を退職する事になった時に司法書士という職業を思い出し、元々法律の学習に抵抗がなかったため目指すことにしました。今思うと、軽い気持ちで学習を始めたと思います。(笑)
<学習時の環境>
学習を始めた際に、司法書士補助者として勤務も始めましたが、学習との両立が自分の場合は難しかったため、試験までに辞めて、受験に専念いたしました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
はじめはオートマのテキストを自分で購入し独学で勉強をするつもりでしたが、自分でオートマのテキストを読むだけでは完全に理解できなかったのと、ペースメーカーとなる予備校の存在が欲しいと思ったからです。
<TACを選んだ理由>
TACのオートマ講座を選んだ理由は、自分で購入したテキストがオートマだったからです。オートマのテキストは他の一般販売されているものよりもわかりやすいと評判だったので選びました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
自宅で学習するのは自分ではできなかったため、毎日TAC神戸校の自習室で勉強しておりました。11月の行政書士試験の後は、朝9時から16時まで神戸校で自習し、夜は自宅で講義の視聴をしておりました。55分勉強した後5分休憩を繰り返すのが学習初期の段階でやっていたスケジュールでした。直前期は本試験を意識して、3時間連続で勉強をすることを心がけました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
択一対策としては、初回の授業で山本先生が5回繰り返すこととおっしゃっていたので、主要科目はその通り実施いたしました。基本的にはテキストとでるトコの繰り返しをしていました。
記述対策はこちらもオートマの記述対策のテキストの問題を、5回以上繰り返し解きました。最初は答えを写す段階でしたが、繰り返し解くことで次第にできるようになりました。
直前期は、オートマ過去問を2周と記述の過去問を解いていました。重視したことは、テキストをただ読むだけでなく、暗記事項(不動産登記法の添付書類など)を理由づけして空で言えるようにしていました。インプットよりもでるトコなどを使ってアウトプットをすることをこころがけておりました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
実際に試験の点数として上がってくるのは、オートマ過去問をやり始めた直前期からでした。模試で1回も合格見込み点を取れたことはなく、今年1回で合格することを諦めかけたこともありましたが、最後までやり切ったことで乗り切ることができました。記述式もきちんと書けるようになったのも、直前期でした。不安になることも多かったですが、毎日やることを前日に決めてそれを無心でこなすことで乗り切っていました。
■TACの良かった点【講師】
山本講師の授業はもちろん分かりやすいですが、毎月の西垣講師のオンラインホームルームも後日必ず見ておりました。1人で勉強していると勉強のペースを見失いがちですが、ホームルームに参加することで勉強の短期的な目標が定まり、ペースを保つことができました。
■TACの良かった点【教材】
オートマのテキストが評判通り分かりやすかったです。口語調の語り口で、初回の理解にとても役立ちました。テキストを理解した後は、でるトコで繰り返しのアウトプットができた点も良かったです。
■TACの良かった点【カリキュラム】
講義が1回あたり3時間で半分に区切って1.5時間ごとでも学習できたことが良かったです。復習の際も授業の進捗に合わせて復習できることも良かったです。私は講義の配信ペースも程よいと感じました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
オンラインホームルームは毎回アーカイブで見ておりました。自身の学習のペースメーカーになりました。
■勉強以外の部分
毎週1日を勉強はしない日と設定し、遊びに行ったりすることもありましたが、11月以降は結局勉強をしていた日がほとんどでした。無理して勉強することは時に必要かもしれませんが、睡眠時間を削ったり体調が良くない日に勉強するなど無茶なことはしないようにしておりました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
私の合格体験記を読んでいただきありがとうございました。しかしながら、私の方法が再現性のあるものかどうかはわかりません。TACのオートマ講座で学習すると決めたのであれば、山本先生と西垣先生のおっしゃる通りに素直に勉強されることが1番の近道であることは確実です。皆様の司法書士試験の合格を願っております。
富樫 香央理 さん 洗練された講義・テキストで、合格への最短ルートを進めた
2025年合格目標:山本オートマチック<1年総合本科生>

【主な受講講座】
●「山本オートマチック<1年総合本科生>」Web通信講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】受験専念 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法・供託法 【不得意科目】商法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・刑法
【1日の平均学習時間】6時間 【学習開始時からの総学習時間】2000時間~2500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
去年4月に退職をして、法律に関する専門知識を身につけたいと思い、資格取得を検討しました。勉強に専念できる環境だからこそ、難易度の高いものに挑戦し、取得後すぐに人の役に立てる資格がいいと考えて司法書士を選びました。学歴を問わず誰でも挑戦できる、という点にも魅力を感じました。
5月に勉強を開始してからは、平日に勉強、休日に息抜きをして11月ごろまで過ごしました。12月から試験日までは、家族の協力を得て勉強のみに集中した生活を送りました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
短期合格のためには情報が必要だと思い、受験指導校を選びました。自分に合った勉強法として、参考書を読むことよりも耳で聞いて印象に残ったものが記憶に定着するタイプだったので、講義形式のものに決めました。いくつかの予備校の体験授業などを見て、山本先生の話し方がよかったことと、私が求めていた効率的な勉強法だと思ったからです。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
学校に通っているかのように時間割を作っていました。「50分勉強10分休憩」を1コマとし、午前4コマ午後3コマを目標にしていました。朝型で余裕を持たせたスケジュールを立てて達成感を重視しました。
3月ごろまでは、科目別にこだわりなくカリキュラム通りにこなしていきました。答練を始めた頃に会社法が苦手だと気づいてからは、慌てて会社法の比率を増やしました。学習進捗をメモするシートを見返したところ、復習回数が足りなかったことに気づき、それから改めて短期の繰り返し学習を強化しました。
記述に関しては、実践的なので楽しんで覚えていたように思います。択一の合間に挟んで、クイズを解くように間違えては書き直しを繰り返していました。山本先生の講義が、記述式を楽しいものにしてくれていたと思います。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
体調管理にかなり苦戦しました。食事、睡眠には気をつけていましたが、毎月のように何か病気になっていました。直前期手前でひと月寝たきりになったこともあり、心が折れそうでした。気が張ることではありますが、オンオフを上手にコントロールしてリラックスする時間を設けるようになってからは、ようやく軌道に乗ったように思います。
■TACの良かった点【講師】
山本先生は法律の解釈を教えてくださったり、考え方を分かりやすい言葉に噛み砕いて話してくださるので、理解が早かったです。絵を描く方法なども先生にならって真似していたら自然とできるようになり、板書がわかりやすかったです。
■TACの良かった点【教材】
オートマの洗練されたテキスト、でるトコの簡潔さが良かったです。「この教材にあることだけをやって合格してる人がいるんだ」と信じてついていけました。
答練の解説冊子には、まとめたかった横断整理のような表がたくさん入っていて、調べる時間の短縮に繋がりました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
総合本科をとっていたので、記述対策や答練、模試を「何をいつやるか」考える時間を割かなくて済んだのがよかったです。
オンラインホームルームのおかげで進捗を確認したり、不安なことを質問もできる環境がとても助かりました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
答練や模試は、自分の立ち位置を把握できる点が良かったです。得意だと思っていたことが意外と点が取れなかったり、逆に苦手意識のあるものもそれなりにできるのかと、発見が多かったです。
解答解説動画では姫野先生の講義を受けれたことで、新しい視点が入ったので良かったです。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
質問メールができるので、立ち止まってしまった時にとても助かりました。
西垣講師とオンライン面談できたことは、メンタル面で大変ありがたかったです。不安でいっぱいなところ、「大丈夫ですよ。これが出来てますよ。前よりこれが成長してますね。」といつも安心感をいただきました。
■勉強以外の部分
受験仲間はいませんでした。代わりに合格体験記や合格者インタビューを何度も見ました。
勉強を自宅のみにしていたので、運動時間は意識的に設けていました。オンラインピラティスなど勉強の合間でできることをしました。ずっと座っているにも体力がいるというのは学びでした。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
終わってみて「手を広げないことが最短ルート」という意味が実感できました。「これでいいのか」という不安は、最後の最後までついてまわりました。
情報の蓄積がある予備校を信じて、身を任せてみるのもいいと思います。繰り返しインプットするという、自分にしかできないことに専念することが効率の良い勉強だと思います。
「大丈夫」信じて進んでいってください。
橋本 鎌多 さん 常識を覆す山本オートマの面白さ
2025年合格目標:山本オートマチック<1年総合本科生>

【受講講座】
●「山本オートマチック<1年総合本科生>」Web通信講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】学生 【合格時(合格年の直前期)の職業】学生
【得意科目】不動産登記法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法 【不得意科目】供託法
【1日の平均学習時間】10時間以上 【学習開始時からの総学習時間】4000時間~4500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
司法書士受験のきっかけは、法律が嫌いになったことです。自分の周りの人たちには、その嫌いな法律に関わらないでほしいと思いました。そのようにできるのが、登記等を業とする司法書士だと考え、受験を決意しました。
<学習時の環境>
学習時の環境は、大学生として、大学の勉強とアルバイトをしながら、試験勉強をしていました。ただ、大学講義は先に履修してしまい、アルバイトも、出勤日時は週3日平均5時間程度でしたので、ほとんど勉強専念だったと思います。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
試験範囲の広さと細かさから、独学で2、3年かけて勉強するよりも、受験指導校を利用して1年間で集中的に勉強した方が、記憶や効率の面でみて良いと考えたからです。
<TACを選んだ理由>
TACさんを選んだきっかけは、特にありません。他の受験指導校と比べるまでもなく、最初からTACさんしかないと考えていたからです。そう考えていた理由は、「山本オートマチック」があったからです。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
1日のルーティーンを決めて、家で勉強していました。1年間を通して、とにかく勉強しない無駄な時間を削ぎ落し、寝ている時間以外のすべてを勉強にあてる、ということを徹底していました。
入門期は、3時間ある1回の講義を6時間ほどかけて視聴し、その後に「講義の急所」を活用して山本先生のご説明のように、自分で声に出してアウトプットをしてみる、というのを4.5時間ほどかけて行いました。その後に記述式対策として、4.5時間ほど勉強しました。また、『でるトコ』を起床後、講義終わり、就寝前に必ずやるということも日課にしていました。
直前期は、13時間ほど、ひたすら過去問を繰り返しました。その後に記述式対策として3時間ほど勉強をしました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
特別に科目別で勉強方法を変えたということはありません。ただ、午後の部については「時間がないなかで解くなら、より早く正確に知識を出せるようにならなければならない」と考え、全体としては、「初級と中上級で変わるのが、勉強期間と基礎の範囲の深さにしかないなら、最初からその基礎の範囲を深く勉強してしまおう」と考え、これらを意識、重視して勉強しました。
記述式対策としては、毎日不動産登記、商業登記を必ず1問ずつは解くというようにしていました。そのなかでも、時間の制限と知識の正確さは常に意識し、あえて解答時間を短めに設定する、復習で模範解答と全く同じものを思い出しながら書いてみる、ということは重視していました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
受験時代の失敗としては、記述式の解き方を変えようとしてしまったことです。
私は合格力完成答練の結果が非常に悪く、そのとき解き方が合っていないのではないかと考えて山本先生からご教示いただいた方法から、色々とカスタマイズをしました。結果、成績は全く上がらず、むしろ下がっていったと思います。その後は、山本先生の方法に戻し、とにかく回数をこなしたことで、克服をすることができたと考えています。
■TACの良かった点【講師】
山本浩司先生には勉強内容を、西垣哲也先生には勉強内容と勉強方法を、主にご教授いただきました。先生方のお話や試験についての知識、物事の見方や考え方まで、本当に自分にピッタリと当てはまっていたと思っています。
■TACの良かった点【教材】
教材としてはオートマシステムを利用させていただきました。
総論分野から書き始まったり、文語体で統一してあったりする堅苦しい教材とは全く異なる、法律学習教材の常識を根底から覆すような、本当に面白い教材だと考えています。
■TACの良かった点【カリキュラム】
私は独学期間中、勉強順やアウトプットできる環境の少なさ、自分の実力が分からないという部分で悩みました。TACさんのカリキュラムやWebトレーニング、基礎演習は、これら全てを払拭してくれましたので、非常にありがたかったです。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
TACさんの答練や模試は、問題、添削、解説、成績表示全ての面において、質が非常に高いと思います。未出の論点だけでなく既出の論点を深く出題し、かつ出題予想も高確率で的中しているので、TACさんのものだけで十分なのではと思います。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
私は、西垣先生のフォロー制度を全て活用させていただきました。特に個別相談は、必ず月に1回利用すると決めていました。直前期は模試の結果を先生に報告していたことで、悪い点数を報告しないようにと、自分を追い込めたと思います。
■勉強以外の部分
私が勉強以外でしていたことは、基本的に食事と睡眠だけです。ここはとにかく自由で、何を食べてもいい、何時に寝てもいい、という感じでした。バイト中は、正直言って勉強していたのですが、若干の息抜きにはなったと思います。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
合格者という存在は、自分が分からないだけで、試験当日には客観的に決まっています。そうである以上、その当日までに、とにかくやるべきことを脇目もふらずにやる、という姿勢が大切だと考えています。
ぜひ、頑張っていただきたいです。
M.I さん 基礎の重要性 山本講師の教えで合格
2025年合格目標:山本オートマチック<1年本科生>、4月答練パック

【主な受講講座】
●「山本オートマチック<1年本科生>」ビデオブース講座
●「4月答練パック」ビデオブース講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】受験専念 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法 【不得意科目】商法(会社法)・商業登記法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】6時間 【学習開始時からの総学習時間】1500時間~2000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
大学で学んだ法律に関係する仕事に就きたかったからです。法律関係の仕事の中でも、争いごとが起こらないよう未然に予防することができるという司法書士の業務に魅力を感じ、受験を決意しました。
<学習時の環境>
司法書士試験の勉強に集中するために仕事は退職し、勉強に専念できる環境でした。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
効率よく勉強して短期間で合格したいと考え、独学でなく受験指導校を利用することに決めました。司法書士試験はマークシートだけではなく記述式もあるため、独学では対策が非効率になるかもしれないと思ったことも受験指導校を利用した理由です。
<TACを選んだ理由>
受講した山本先生の体験講座がわかりやすかったことと、校舎に通いやすく解放されている自習室が多くて使いやすい環境であったことが決め手でした。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
学習スタイルは、講義を受講した後は、問題集を解き、テキストを読み、再度問題集を何度も解くという勉強方法でした。勉強スタイルは人によりますが、私は理解できるまでテキストを読み込むよりも、何度も問題集を解くことで知識が定着するタイプでした。
学習スケジュールは、1年本科生の配信スケジュールにあわせて講座を受講し、同時にすでに受講が終わった科目の問題集を何度も解いていました。カリキュラムにあわせて勉強をすることで、あまり焦らず計画的に進めることができたと思います。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
科目別勉強法としては、択一式は民法・不動産登記法・会社法・商業登記法を中心に、とにかく過去問を何度も解くことを重視していました。出題数が多い不動産登記法と、苦手だった会社法は特に何度も過去問を解きました。なお、マイナー科目は他の科目と比べてあまり深くやりこみ過ぎず、重要論点を落とさないことを重視して勉強しました。
記述式対策については、まずは択一式の対策で知識を定着させてからと思っていたので、本格的に開始したのは答練からでした。答練で記述式の答案が作成できないことに焦ったりもしましたが、解説講座を聞き、解き方を理解することで徐々に解答が作成できるようになりました。記述式に慣れるためにも答練・模試は受講して良かったと思います。
学習時に重視したポイントは、上記のとおりアウトプットに時間をかけることです。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
本試験の半年ほど前に盲腸になり手術をしました。退院後もあまり動けない日が続き、予定通り勉強ができませんでした。体調が回復した後に、溜まった講座を急いで受講してなんとか遅れを取り戻しましたが、その時期は少し焦りました。
■TACの良かった点【講師】
山本先生の講義はとても面白くて記憶に残りやすく、また話し方も落ち着いていて、楽しくすべての講座を受講することができました。山本先生の講座で基礎の重要性を知ることができ、そのことが合格に繋がったと思います。
■TACの良かった点【教材】
オートマの教材がとても読みやすく、わかりやすかったです。復習するときもテキストの読み直しが苦にならなかったです。テキストに合わせて過去問もオートマで揃えて勉強しました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
学習内容や時期がカリキュラムで決まっているので、それにあわせて進めることで焦らず勉強することができました。私は勉強を開始したのが4月頃だったので1年コースを受講しましたが、1年以外のコースや中上級者のコースも選択肢にあるのは良いと思いました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
答練・模試の受験は、記述式の答案がうまく書けないことに気付ける良い機会だったと思います。自分の実力把握のためにも受験して良かったです。解説講座で記述式の解き方を丁寧に説明いただき、回数を重ねるごとに答案が作成できるようになりました。
■勉強以外の部分
ビデオブースでの受講だったので受験仲間はいませんでしたが、周りと比較することなく自分のペースで進めることができたので特に不便なことはありませんでした。
勉強に疲れたときは、家で夫と映画を観たりして気分転換していました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
山本先生もおっしゃっていたように、基礎が完璧であれば合格できる試験だと思います。試験科目も多いため焦りやプレッシャーを感じることもあるかと思いますが、何度も基本を繰り返し勉強すればきっと大丈夫だと思います。自分を信じて頑張ってください!
世利 尚也 さん 法律初学者でも6カ月で一発合格
2025年合格目標:山本オートマチック<速修本科生>

【受講講座】
●「山本オートマチック<速修本科生>」Web通信講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】不動産登記法・商業登記法・司法書士法・供託法・憲法・刑法 【不得意科目】民事訴訟法・民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】10時間以上 【学習開始時からの総学習時間】1500時間~2000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
前職(学習開始時の職場)の人材育成指針がジェネラリストの養成であり、就労する中で自覚した「特定領域で専門的なキャリア形成を図りたい」という自身の希望と会社の方針との間でミスマッチが生じたため、この年齢からでも未経験での業界転職を比較的容易とする国家資格の取得に目が向きました。その中でも司法書士という資格を志したのは【①受験要件がないこと。②短期合格を現実的に目指すことができること。③資格取得後の働き方がイメージしやすいこと。④将来的な独立開業が選択肢として近いこと。】といった観点からです。
<学習時の環境>
学習を本格的に開始する段階では退職して、受験に専念していました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
非法学系学部卒業かつ他資格学習経験もない完全初学者であったため、独学の選択肢は当初からありませんでした。また、自身の学習環境で可能な限り最短での合格を目指すには、効率的な学習が不可欠と考えていましたので、蓄積された合格ノウハウの恩恵を得るためにも予備校の活用は必須の選択でした。
<TACを選んだ理由>
・短期合格を目指せる講座であり、毎年の合格実績が安定していること。
・講師の話し方、講義スタイル、またテキストの文体との相性が良いこと。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル>
学習開始が試験前年12月であり、本試験までの時間が限られていたことから、常に自身で策定した学習計画とその進度を意識して日々の学習に臨んでいました。
<学習スケジュール>
【学習初期】
講義の受講を完了したのが4月半ばであり、この間は講義視聴を進めることを第一に、具体的には、2日セットで5コマ(A日程:講義2コマ+前日講義3コマ分の復習/B日程:講義3コマ+前日講義2コマ分の復習)のスケジュールを組んでおりました。試験までの残り日数からも、何度もテキストを再読できないことはわかっていたので、1読目(講義)と2読目(復習)で可能な限り理解しておくことを意識しました。
【学習中期】
テキストの3読目(主要科目は4読目)と問題集、答練・模試等の演習を並行して行いました。
【直前期】
最後の1か月間は、各科目問題集の中で、主に複数回誤答箇所の徹底的な繰り返しを行いました。
<科目別勉強法>
講義とテキストでは「理解」することに主眼をおき、問題演習の繰り返しで「知識の定着」を図る王道スタイルで臨みました。科目毎の学習方法については、民法と会社法/商法は他科目に比べてより深いレベルの理解を要するため、テキスト読みにかける時間を多く配分していました。
<重視したポイント>
学習初期から直前期まで、徹底して計画的に学習を行いました。当然、計画通りにいかないことも多々生じますが、その度に見直しを行い、本試験までの残日数を逆算して、何をすべきか、どこを補強すべきか、どれくらいの時間配分で学習すべきかを考え、日ごと、週ごと、月ごと、そして本試験までの学習計画を常に念頭においていました。
<記述式対策>
大きな流れとしては、ひな形演習を毎朝学習開始時に行うことで基礎体力を養い、オートマ記述で網羅的に論点に触れ、答練・模試、過去問で本試験レベルの文章/資料の量に慣れていく、といった形で対策を行いました。本試験問題は午後の限られた時間内で処理しなければならないこともあり、一見すると高い壁があるようにも思えますが、個人的には慣れ(解法,解き方の確立)の問題が大きいと感じています。より重要なのは、ひな形を用いた反復演習と、問われ方を含めた論点確認を通じて基礎トレーニングを積むことだと思います。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
学習期間を通じて絶望感があったのは、【①民法の講義を終え、不動産登記法の講義に入った瞬間。②本試験レベルの記述問題に初めて触れた瞬間。】でした。いずれも今までの学習事項からの飛躍があり、当初戸惑いを覚えたものです。長期間にわたる学習を通じて誰もが、どこかで躓きかけるポイントがあると思います。若干精神論にもなりますが、そういう瞬間に、歯を食いしばり、振り落とされないように何とか講義についていくことができるか、が私にとって合否をわけるポイントであったかもしれません。一度で完璧に覚えてしまうことは不可能と割り切り、とにかく学習を前に進めることに全力を注ぎました。
■TACの良かった点【講師】
合格への方法論、講義の展開、話し方、声色、話すスピード、板書の使い方等、予備校やコースの選択に際して考慮する事項は多岐にわたると思いますが、法律初学者で短期合格を目指す私にとって、山本先生の指導は完璧にフィットするものでした。テキストのみでは理解が難しい論点や覚えにくいポイントも、その行間を補完し、重要事項にフォーカスするような形で山本先生が講義をしてくださるので、一度の講義で内容を「理解」するレベルには到達することができます。
■TACの良かった点【教材】
失礼ながらテキスト表紙にある「すいすい読める、すいすい分かる、だから暗記不要」の謳い文句に当初は半信半疑でしたが、偽りはありませんでした。試験勉強を通じて、「さぁ暗記するぞ」と記憶することを目的にした学習時間は極々わずかです。オートマテキストは「理解」することに重点がおかれている参考書であり、講義を受け、復習として再読し、過去問等で論点に改めて触れる、その繰り返しを行うことで、自然に記憶が定着していきました。図表で整理された情報からの知識定着が不得手な私にとって、オートマテキストは最良の参考書であったと思います。
■TACの良かった点【カリキュラム】
オートマの核心でもある「基礎の完成」を目指す指導方針は、私を含めこれまで多くの短期合格者を輩出してきたその実績からも、司法書士試験の短期攻略を目指す上での定石であると思います。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
提出から添削答案の返却、成績通知までのスピードが非常に早く、自分の現在地を可能な限り早く捕捉して今後の学習計画を練りたかった私にとって大変有意義なツールでした。順位や判定に一喜一憂することなく(実際はしてしまいますが。)、苦手分野の把握や、解答時間の練習など、目的意識をもって活用すれば、自分の成績を伸ばす起爆剤になると思います。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
問題集等で、解説を読んでもどうしても理解が及ばない点について質問をしていました。
■勉強以外の部分
私にとってこの学習期間は精神力の闘いでした。振り返ればやや見切り発車で前職を退職し、受験専念となったため、経済的な不安も大きくありました。答練や模試の結果をみて本当に合格できるだろうかと、司法書士を目指すとした自身の選択への不安も当然ありました。一方で、取り組むべきことは非常に明確でした。受講した講義のカリキュラムをこなし、言われたことをやり、言われていないことはやらない。そういった意味で、精神力の闘いであったと思います。不安に打ち勝つため、絶対に合格できると自分に言い聞かせ信じ込ませ、時には狂人的に勉強にのめり込む精神力が合格を手に運んできてくれたのだと確信しています。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
自分の学習スタイルを確立し、それを徹底することが試験突破のカギであると思います。巷には多くの合格方法論があふれていますが、仕事や育児,介護など各受験生の置かれている状況は千差万別で、捻出できる勉強時間や、学習環境もそれぞれです。学習の進め方について悩むことがあれば、司法書士試験指導のプロであり、これまで蓄積された合格ノウハウをもつ講師に相談して、合格メソッドの最大公約数を取り入れつつ、各人の自分流を見つけてみてください。
H.M さん 山本講師の講義は分かりやすく面白い
2025年合格目標:山本オートマチック<速修本科生>

【受講講座】
●「山本オートマチック<速修本科生>」Web通信講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】受験専念 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法・司法書士法・供託法・憲法・刑法 【不得意科目】商法(会社法)・商業登記法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】7時間 【学習開始時からの総学習時間】1000時間~1500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
受験のきっかけは転職活動です。勤め先を退職したものの、中途採用の面接で、自分にはアピールできる内容が何もないことを痛感し、他の人とは違う特別なスキルを身につけなければと思うようになりました。
<学習時の環境>
学習時の環境は、転職のため地方から都市部へと引っ越しをしていましたが、まずは一年、アルバイトもせず勉強に専念することとし、貯金を切り崩しながら自習室に通う受験生活を送ることにしました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
教材の選定や計画など、独学だと「何をすればいいか」で迷う時間が多く、逆に不安やストレスに繋がると思いました。それらを予備校に任せた方が、時間を有効に勉強に充てられるため、より効率的だと考え、利用を決めました。
<TACを選んだ理由>
予備校を選ぶ上で、検索サイトや動画サイトで個人が公開している合格体験記を参考にしました。オートマシステムを使っていた方がとても多かったことから信頼感が芽生え、TACを選ぶことにしました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
学習スタイルは、択一式に関してはテキストの読み込み、でるトコやオートマ過去問に色ペンで必要な情報や豆知識を書き込みつつの演習が主です。記述式は書いて覚える側面が強く、テキストの内容を復習して、その際にまとめたノートを見て覚えるほか、過去問を解くスタイルでした。
スケジュールは、勉強のスタートが9月半ばからと遅れていました。綿密にスケジュールを組むのが苦手だったので、まずは講義動画の視聴をこなしました。1時間半の講義動画を一日に4~5コマほど消化し、特に主要科目はテキストをじっくりと読み直して復習するための時間を作りました。12月頃からは記述式やマイナー科目の講義をこなし、3月以降には試験直前の演習(模試、過去問の周回)を中心に行いました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
主要4科目の択一式対策としては、講義直後や時間をおいてからテキストを読み返すほか、ひたすらオートマ過去問とでるトコに取り組みました。マイナー科目は、講義後の復習はでるトコとオートマ過去問を軽く解き、試験直前期に同問題集で追い込むことにしました。
記述式については、覚えるより書いて覚える要素が強く、講義終了後に2周ほどテキストの内容を反復し、ノートに要点をまとめては読み返しました。実際の出題形式に慣れるよう、直前期に記述式の過去問集を購入し、10年分ほど遡って演習をしました。こちらは問題集同様にテキストに直接色ペンで書き込みをして、解けなかった論点は読み返す方法を取りました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
専業受験生のため時間はあったものの、自分自身の体力と気力の限界がネックでした。仮に1日7時間以上の勉強を4日取り組んだだけで、それ以降脳の機能がかなり低下し、2~3日ほど休んでようやく回復するといった有様でした。また、追い込もうとすればするほど眠れなくなってしまうことも問題でした。解決方法として、睡眠導入剤を処方してもらい、覚悟と決意を持って休日を設けたことで体調の維持とやる気の醸成に繋がりました。
■TACの良かった点【講師】
山本先生の講義が面白く、わかりやすかったのがTACを選んでよかった点です。時には笑ってしまうこともあり、学習当初積み上がっていた長い講義動画の視聴が苦痛になりませんでした。
■TACの良かった点【教材】
過去問をベースにしているテキストは無駄なく必要な情報をカバーできます。択一式はオートマ過去問とでるトコしか解いていませんでしたが、最低限の教材で合格のための実力を身につけられるのは魅力だと思います。
■TACの良かった点【カリキュラム】
資格試験は量との戦いになりますが、いつまでにすべきことがコンパクトかつ明確に固まっていたため、独学で取り組んだ場合と比して効率の面でもストレス対処の面でも非常にありがたかったです。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
模試は出題内容が非常に難しく、試験直前の模試ですらC評価が並び、試験日まで全く楽観的になれませんでした。模試の結果を基に試験直前に苦手分野の追い込みを図れたことが結果的に合格につながったのだと思います。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
講義動画が積み上がったり、疲れてやる気が出ないタイミングでは西垣先生主催のオンラインホームルームに参加しました。力強く受講生を励ましてくれたり、過去の出題傾向を示していただけるので、気分転換になりました。
■勉強以外の部分
通信生のため受験仲間もなく、友人とは受験期間中は連絡を断ち、家族は遠方に住んでいた、一人予備校の自習室に篭る生活でした。他受験生の影響がなかったことは、自分のペースを保つのに効果的でした。試験直前週でも校舎近くのカラオケに行く心のゆとりがありました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
全ての時間を勉強・休息に集中させられる環境作りが非常に大切だと思います。まずはSNSアプリを削除し、親しい人には資格取得を目指していることや、しばらく忙しく過ごすことを宣言してみるとよいかと思います。
藤野 恭平 さん TACの答練と姫野講師解説講義の記述解法でパワーアップ
2025年合格目標:4月答練パック

【受講講座】
●「4月答練パック 解説講義あり」Web通信講座
【受験回数】1回
【学習開始時の職業】公務員 【合格時(合格年の直前期)の職業】公務員
【得意科目】民法(総則・物権法・相続法)・不動産登記法 【不得意科目】民法(親族法)・民事訴訟法
【1日の平均学習時間】5時間 【学習開始時からの総学習時間】1500時間~2000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
私は地方自治体の住宅政策に関わる仕事をした経験から、老朽化した建物の維持管理、空き家の利活用などといった不動産に関する社会問題に関心を持ち、将来的にこのような社会問題に関わる仕事をしたいと考えていました。その中でも、安全かつ円滑な不動産取引の基礎となる不動産登記制度にとって必要不可欠な存在である、司法書士の資格に興味を持ち、受験を決意しました。
<学習時の環境>
試験の1年3カ月ほど前から学習を開始し、仕事はその直後から育児休業に入りました。学習と並行して子2人を自宅育児していたため、まとまった勉強時間を確保しづらい時期もありましたが、すきま時間を学習に充てるなど工夫して、勉強時間を捻出していました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
司法書士の資格に興味を持ってすぐ、書店に行きテキストを1冊買って読んでみましたが、講義のないテキストや問題集のみの学習では、学習のモチベーションを保ち続けることが難しいのではないかと感じました。また、記述式問題の学習にあたっては、答案の添削を受ける必要性を感じ、受験指導校の利用を決めました。
<TACを選んだ理由>
択一式の学習までは他の予備校の講座を利用していましたが、記述式対策に不安を感じたため、答練・模試を追加で受講することにしました。中でも、TACの講座は答練の種類が豊富であり、組み合わせでの受講方法も充実している点や、姫野講師の解説による記述式対策の評判が非常によかった点に惹かれ、TACの答練・模試を受講しました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
司法書士試験に向けた学習を開始したのは本試験前年の春で、同年秋までは、先に始めていた土地家屋調査士試験の学習も同時並行で進めていました。調査士試験までは、調査士と司法書士で試験範囲が重複している民法や不動産登記法総論を中心に学習し、理解を深めました。
<科目別勉強法>
択一式の対策については、私はテキストを読んで覚えるよりことも問題を何度も解いて覚えることが得意なので、とにかく過去問を繰り返し解くことに力を入れました。過去問演習の際は、テキストや六法を机に出しておき、間違えた問題のみならず正解した問題についても、テキストの該当ページや六法の条文を参照し、その周辺に書いてある知識と関連付けて覚えることを心がけました。
<記述式対策>
記述式対策を開始したのは、択一式の知識がひととおり身についた本試験5か月前の2月頃です。できるだけ早く答案用紙の完成まで到達できる解法を習得し、とにかく答案作成に慣れることに力を入れました。本試験の記述式問題では、短い時間で大量の論点を処理したうえで答案を作成しなければならないため、答案構成用紙の作成など、検討した論点を答案に反映させていく作業は、できるだけ効率的に行う必要があります。このため、答案を作成する手の動きに迷いが出ないように、何度も問題を解いて練習しました。
<学習時に重視したポイント>
2人の子供を家庭で育児をしながらの勉強であり、まとまった勉強時間を確保することが難しかったため、すきま時間の有効活用に力を入れていました。ふと手が空いたその瞬間に学習を開始できるよう、机の上に教材を開いたまま置いておいたり、スマホの暗記アプリを活用したりすることで、数分単位の空き時間も有効活用しました。だっこ紐で子供をだっこしながら勉強することもありました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
司法書士試験では、民法や不動産登記法で抵当権・根抵当権について非常に細かい知識が問われますが、私は本試験直前まで、根抵当権の元本確定事由を正確に覚えられず、苦戦していました。特に、元本確定の覆滅の有無、元本確定登記の要否や、複数不動産・複数当事者が絡むケースの元本確定のタイミングが苦手でした。そこで、「誰が」「どうしたら」「いつ確定」するか等を1枚の表に整理して、その表を見ながら問題演習を行ったところ、暗記がはかどりました。
■TACの良かった点【講師】
姫野講師の解説による記述式対策は、事前に見聞きしていた評判どおり素晴らしかったです。特に不動産登記法の申請登記リストなどの解法たちは私にとって革命で、この解法をマスターすれば本試験も怖くないという自信がつきました。20年以上の受験指導経験により裏付けられる安定感のある講義で、説明内容だけでなく話し方まで含めて「この講義についていけば大丈夫」と感じさせる何かがありました。
■TACの良かった点【教材】
TACの答練・模試の解説冊子は、択一・記述とも非常に詳細に記載されていて、効率的な学習に大変役立ちました。前提となる規定や先例から記載されており、問題に関して生じた疑問が解説を見ても解消されない、ということは一度もありませんでした。
■TACの良かった点【カリキュラム】
4月答練パックを利用し、4月から6回の答練と4回の模試を受けました。本試験の直前期に、2週間に1回というハイペースで、出題予想を踏まえた新作問題に触れることができたので、本番に向けてのペースメーカーとなり、よいリズムを作ることができました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
各答練・模試とも、難易度や記述問題の分量が本試験と近く、本試験のシミュレーションとして最適でした。答案の添削についても、細かい点までしっかり見てくれているなと感じました。TACの模試は非常に多くの受験生が利用しているので、成績表に記載される得点や順位から受験生全体の中での自分の現在位置がわかり、モチベーションの維持につながりました。私は添削された答案を印刷し、メモを書き加えて本試験直前の見直しに活用していましたが、一方で、外出先でふと気になる点を思い出したときにも、添削答案や採点表をネット上ですぐに確認できるので便利でした。
■勉強以外の部分
育児をしながらの学習だったので、子供と遊んだり散歩したりするなど、家族との時間がよい息抜きになっていました。小さい子供は吸収が早く、毎日のようにできることが増えていくので、親も頑張らなければと勇気づけられることもありました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
試験合格のために何より大事なことは、学習を「自分に合った正しい方法」で「継続」することだと思います。司法書士試験はとても難易度の高い試験ですが、途中で投げ出さず、最後まで学習を続ければ、合格への道は開けると思います。思うように理解が定着しないときは、ただ漫然と勉強するのではなく、一歩引いて自分に合った学習方法を探しなおすこともよいと思います。頑張ってください!
初学者向けコース出身者 合格体験記
「難関試験」のひとつと言われる司法書士試験。
しかし、初学者からのスタートで合格している人も少なくありません。
中には、法律知識ゼロから始めて短期で合格する人もいます。
合格者は、どのようなことに気を付けて自分の学習スタイルを見つけたのでしょうか?
「初学者向けコース出身」、「中上級者向けコース出身」は過去3年分(2023年合格目標以降)の受講講座につき分類しています。
受験回数、学習時間等の内容は、体験記ご提出時にご本人様に申告いただいた内容をもとに記載しております。また、受講講座名は原則として過去3年分の受講講座について、最新年度の名称(現在同一講座がない場合は当時の名称)で表記しています。
各種コースや講座のカリキュラムは、受講生を対象に実施しているアンケートをもとに、毎年見直しを行っております。そのため、体験記に記載されているものから名称・内容等が変更される場合や販売を終了する場合もございます。最新情報は案内書等をご確認ください。
大出 燎 さん 試験に必要な知識のみを効率的に学習できた
2025年合格目標:山本オートマチック<速修本科生>

【主な受講講座】
●「山本オートマチック<速修本科生>」Web通信講座
●「山本プレミアム上級本科生」Web通信講座
●「4月答練パック」Web通信講座
【受験回数】3回
【学習開始時の職業】学生 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】不動産登記法 【不得意科目】民事執行法・刑法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】2500時間~3000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
大学が法学部だったこともあり、将来は法律を扱う仕事をしたいと考えていました。司法書士は、身近な法律問題で困っている方々の役に立つことで地域貢献でき、働き方に自由が利きやすい点に魅力を感じ、挑戦しようと決めました。
<学習時の環境>
大学4年の秋頃から本格的に勉強を開始したので、学習初期は、大学と予備校の両方に通う、いわゆるダブルスクールの環境でした。大学卒業後は、専業受験生でした。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
司法書士試験の科目数の多さ、問題の難易度、合格率の低さなどの試験自体の難易度を考えた時に、独学で合格をすることは難しいと考え、受験指導予備校を利用しようと決めました。
<TACを選んだ理由>
大学の先輩に山本先生のオートマで合格した方がいて、その方にオートマを薦めてもらったことがきっかけです。法律は難しいイメージがあったのですが、初めてオートマを読んだときに、そのイメージが一気に払拭されて感動し、これしかないと考え、TACを選びました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
その年の3月末までの期間と4月からの期間の2つに分けていました。
3月末までは講義の受講、テキストの読み込みなどのインプットとでるトコや過去問を解くアウトプットを行うことで、各科目の全体像の理解に努めました。アウトプットに関しては、間違えた問題に印をつけて短期間で反復し、何度も正解できる問題は飛ばしました。この時期までに各科目の全体像の理解に重視していたので、暗記が必要なものに関しては後回しにしていました。年内は主要4科目、記述、民訴のみを勉強しました。
4月からの直前期は過去問を引き続き解くことと、講義の急所というオートマのまとめ教材を反復して基本的な知識を固めていきました。講義の急所の活用法は、まず1周目は全部に目を通し、失念、理解できていない箇所に色ペンで印をつけます。2週目はその印をついた箇所のみに目を通し、未だ失念、理解できていない箇所に別の色ペンで印をつけていき、3週目以降もそれを繰り返していきます。そうすることで、最終的に目を通す箇所が徐々に減少し、短期間で各科目を1週できるので効率よく学習できました。この時期に後回しにしていた暗記が必要なものを詰め込みました。直前期は毎日全科目を勉強しました。
記述対策は、オートマ記述を反復し、申請書の書き方を間違えたときは、ひな形集に印をつけて何度も確認しました。直前期には過去問に取り組み、間違いノートを作成して同じ論点が出題されても対応可能の状態にしました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
周りの友達が皆働き始める中で、自分のみ社会に属せず勉強していることに関して多少の焦りや不安、金銭的な厳しさは正直ありました。そう感じた時は「人間生きていれば悩みの一つくらいあるし、お金は合格さえすればなんとかなると」楽観的に考えて切り替えていました。
勉強面に関しては、山本先生の講義がとても面白く、勉強法も西垣先生に丁寧にご指導していただいたのでそこまで大きな苦労は感じることなく取り組むことができました。
常に支えてくれた家族や仲間には心から感謝しています。
■TACの良かった点【講師】
山本先生の講義は、暗記を強いて細かい知識を取り上げるのではなく、楽しく理解でき、受験に必要な基礎の知識のみを効率的に教えてくださるのでとても良かったです。西垣先生の個別相談もとても丁寧に対応していただけて良かったです。また、事務局の方々や校舎のスタッフの皆さんも親切に対応していただけたので嬉しかったです。
■TACの良かった点【教材】
オートマシリーズは、受験に必要な基礎的な知識のみをとても分かりやすく掲載されているので、文章を読むことが苦手な僕でもスイスイ読むことができました。テキストが固い口調で書かれていない点も良かったなと感じています。
■TACの良かった点【カリキュラム】
記述講座の中で、本試験の記述式の問題文の読む順番、着眼箇所、時間内に解くコツといった受験テクニックを教えてくださる講座が用意されていたことが非常によかったです。
■各種答練・模試の活用方法や良かった点
今まで学んだ知識が正確に身についているかどうかの確認のために活用しました。過去問にもない未出の知識は、改正部分を除いて全て無視していました。受験した日から一週間以内に成績表を確認できる点が良かったです。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
勉強方法や進捗で悩みがあるときに、西垣先生の個別相談を利用していました。相談事に対して丁寧に寄り添って共に解決していただけたことが嬉しかったです。また、質問メールの返信も常に迅速に対応していただけて良かったです。
■勉強以外の部分
仲間は司法書士になってから作ればよいと考えていたので、受験仲間はいませんでした。勉強に疲れた時は仮眠や運動をしてリフレッシュしました。一日の勉強が終わったらお酒を飲んで自由に過ごしていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
僕は勉強が嫌いでしたが、山本先生のおかげで勉強の楽しさが理解できました。この経験は僕の宝物です。山本先生が愉快で楽しい講義をしてくださり、悩み事は西垣先生が真摯に対応してくださるので、是非楽しくポジティブに挑戦してほしいです。応援しております。
中上級者向けコース出身者 合格体験記
司法書士試験の最大の特徴でもある「基準点」。
この基準点を突破し、さらにプラスアルファの点数を上積みするためには、
苦手分野を克服するのと同時に、全科目をバランス良く学習することが必要です。
合格者は、どんな学習方法でこの課題をクリアしたのでしょうか?
「初学者向けコース出身」、「中上級者向けコース出身」は過去3年分(2023年合格目標以降)の受講講座につき分類しています。
受験回数、学習時間等の内容は、体験記ご提出時にご本人様に申告いただいた内容をもとに記載しております。また、受講講座名は原則として過去3年分の受講講座について、最新年度の名称(現在同一講座がない場合は当時の名称)で表記しています。
各種コースや講座のカリキュラムは、受講生を対象に実施しているアンケートをもとに、毎年見直しを行っております。そのため、体験記に記載されているものから名称・内容等が変更される場合や販売を終了する場合もございます。最新情報は案内書等をご確認ください。
記載されているコースの他に受講されていたコースがある場合がございます。
荒木 隆介 さん 網羅されているテキスト+過去問で合格
2025年合格目標:上級総合本科生

【主な受講講座】
●「上級総合本科生」Web通信講座
●「答練本科生記述対策プラス」Web通信講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】自営業 【合格時(合格年の直前期)の職業】自営業
【得意科目】民法 【不得意科目】商業登記法
【1日の平均学習時間】4時間 【学習開始時からの総学習時間】4000時間~4500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
ロースクールを中退した後に、司法書士合格を目標としました。これまで学んだ民法などの知識が活かせると思いましたが、そんなに簡単とはいきませんでした。
<学習時の環境>
在宅ワークをしながらの学習でした。専念の方よりは時間がなく、フルタイムで働いている方よりは時間があったと思います。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
最初は独学で学習を始めました。オートマチックを読み、書いてあることは理解できた感じはありました。しかし、過去問を解いてみると実力不足を痛感したため、TACを利用することを決めました。
<TACを選んだ理由>
山本先生のオートマチックから学習を始めたので、TACを選びました。どの講座が自分に合っているかは毎年迷い、様々受講しましたが、合格の年は姫野先生の上級総合本科を受講しました。
以下では、記憶の鮮明な上級総合本科について書いています。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
私の学習スタイルで特徴を挙げるとすれば、インプット期(択一式対策講座理論編)は講義・テキストを丁寧に学習することよりも、過去問を軸に本試験で問われる部分を強く意識した点です。事前に過去問演習を行い、講義では苦手な部分を集中して聞きました。
4回目の受験でインプット講義は複数回体験していましたので、民法権利能力から全てを丁寧にやることはモチベーションにつながらないと思いました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
(主要科目)
パーフェクト過去問集を1~2周してから、理論編講義を見ました。この際、得意な部分は倍速だったり、飛ばしたりで、時間をかけていません。一方で苦手な部分は随時一時停止したり、戻して理解できるまでやることを意識していました。また、復習は講義から少し時間を置いて、パーフェクト過去問集を用いて行っていました。
実践編は、講義を見てから一問一答を回しました。出題予想を信じて、出ないと言われた論点は一切見ていません。
(マイナー科目)
出題数が少ないので、主要科目に比べて掛けられる時間が少ないです。過去問中心なのは変わりませんが、講義の理解を優先せず、直前期の詰め込みで対応しました。
(重視したポイント)
全科目を通じて過去問が一番大事と思います。答えにたどり着けるだけでは足りず、未出論点が混じる中で過去問を見つけ出すことができるようにしました。
(記述式)
記述式対策は記述式対策講座どおりに進めました。理論編・実践編・実践総合編の教材以外のことは一切していません。問題の読み方、メモの取り方などの一切を姫野先生と同じにできるようになる事が、記述式で合格点を取る確実な方法だと思います。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
学習を始めてすぐの時期に、虫垂炎で入院しました。また、退院後は帯状疱疹になり、年内は学習リズムが作れませんでした。乗り越えたというよりは、出遅れていることは分かっていたので、とにかく始めるしかなかったといった感じでした。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生は合格にフォーカスした講義をしてくれます。ついて行けば合格できるはずと、信じることができました。サイクルに従った出題予想を出してくれて、論点ごとのメリハリがありました。
■TACの良かった点【教材】
教材の良い点は、網羅性だと思います。未出論点もテキストに記載されていますし、出題実績も記載されています。講義の教材以外に使用したのは、パーフェクト過去問集だけでした。
■TACの良かった点【カリキュラム】
科目の順番、科目ごと講義回数の割り振りなど、考えられていると思います。カリキュラムをペースメーカーに学習スケジュールを考えることができるように組まれていると思います。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
カリキュラムに含まれている全国実力Check模試、全国公開模試を受講しました。間違った問題は、出題可能性が低いと言われたものを除いて、問題及び解答解説を写真に撮り、スマホに入れ、試験前日まで何度も見返しました。
解説に過去問番号が記載されていて、参照しやすい点が良かったです。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
私は、本試験分析セミナーを見て、過去問を中心に学習しました。その成果が出て合格することができました。何をすべきか迷っている方は、一度本試験分析セミナーを見ることをオススメいたします。
N.S さん 姫野解法のおかげで記述式を解くのが楽しくなった
2025年合格目標:上級総合本科生

【主な受講講座】
●「上級総合本科生」ビデオブース講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】その他
【得意科目】民法 【不得意科目】商法(会社法)・商業登記法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】3000時間~3500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
元々建築系の仕事をしていました。新築物件の際に司法書士の方と出会うことがあり、司法書士という資格に興味を持ち始めました。司法書士は資格を取ると独立も可能で、長く続けられるお仕事とうかがい、このまま会社勤めを続けていくことに悩んでいた時期でもあったため、最初は軽い気持ちで試験を受けてみようと思い勉強を始めました。
<学習時の環境>
試験勉強を始めた後、夫の転勤もあり、会社員の仕事は辞めて勉強に専念しました。基本的には、朝晩は家事などをし、それ以外の時間は勉強に費やしました。大学、職場も理系の環境で過ごしてきたため、法律に関しては言葉や考え方に慣れるまで大変苦労しました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
司法書士の資格を取る前に、まずは行政書士の資格を取得しようと思い、その時にTACに通っていました。元々理系でもあるため、法律用語にも慣れず、どのように勉強を進めて良いか、またどのようなテキストを購入したら良いかも分からない状態だったため、スケジュール管理やテキストも一式で購入できる受験指導校を利用することにしました。
<TACを選んだ理由>
文章が多いテキストは苦手で、表などにまとまったテキストを探していた際に、TACで姫野先生が講義で使用されているテキストを見せていただき、とても見やすく勉強しやすいように感じたため、行政書士から引続き、TACを受講することにしました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
2023年、2024年と上級総合本科生でしたが、2年間は講義を聞いていても分からないことや覚えることも多く、とにかく講義を受けることに必死で、全ての科目で中途半端な印象でした。択一については基準点に届いていましたが、記述が足を引っぱっていました。
2025年も上級総合本科生のコースを受講しました。極力学校に通い、自習室で勉強するようにしました。過去2年間は中途半端に学び、全ての科目でやり切った印象も無かったため、今一度基礎から学び直そうと思い、講義は理論編を丁寧に学びました。特に自分でスケジュールを立てることはせず、基本的に動画の配信スケジュールに沿って、勉強を進めました。動画を見たら復習と過去問を解くという繰り返しでした。また、4月からはTACも模試も始まるため、本番同様という気持ちで取り組みました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
主要4科目は特に理論編で丁寧に勉強し、ただ覚えるだけではなく、理解することに注力しました。理解した内容で問題が解けるかは随時パーフェクト過去問集で確認しました。択一実践編が始まってからは、基本的には択一実践編のテキストのみを使用し、ひたすら問題を繰り返しました。また、講義の中で、出題可能性が高いと言われた論点だけは択一実践編の問題演習にプラスしてパーフェクト過去問も解きました。
マイナー科目は、理論編の受講の後、択一実践編を繰り返し解くのみでした。
記述対策は、姫野先生の解法を覚えてそれを言われた通りに使いこなすことに注力しました。記述の点が取れていなかったときは、中途半端に覚えた解法だったため、やはり抜け漏れがあり、ミスをしてしまっていため、先生が言われた通りに解き進めることだけを考えていました。解法の練習は、講義で使ったテキストにプラスして、模試や答練でフルサイズの問題を解いて、とにかく解法を自分の身につける練習をしました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
法律の勉強をほぼしたことが無かったため、とにかく聞き馴染みの無い言葉も多く、慣れるまで非常に苦労しました。慣れるために、法律に関する漫画やドラマを見て、苦手意識をなくすことや、どのような場面なのかをイメージできるようにしました。民事訴訟法などは、裁判に関するドラマや漫画で、かなりイメージすることはできるようになったと思います。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の講義は、ただテキストを読むような講義ではなく、どのような場面でどのようなことが起きているのかなど、イメージしやすい講義で、とても楽しく、記憶に残る講義でした。
記述対策講義は、姫野先生の解法を自分の身につけることができたら、記述の問題を解くのが楽しくなるほど、成長を感じられました。これ以上に解きやすく抜け漏れの無い解法はないのでは?と思うほどでした。早めに解法を身につけて、後は論点の勉強に費やせた点も良かったです。
■TACの良かった点【教材】
択一実践編に関しては文章ばかりではなく、図でまとめられている部分が多く、非常に勉強しやすいテキストでした。また、細かいところが勉強したいと感じたところは、理論編に丁寧に書かれているため、自分が苦手なところは、理論編に戻ってみたり、頭が整理出来ていない部分は択一実践編の表を使ったりと、使い分けも出来て、非常に助かりました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
自分でスケジュールを考えなくても、基本的に動画配信スケジュールに沿って勉強を進めれば良いので、良かったです。また、Web上でもスケジュールが分かるため、予定も組みやすいと感じました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
上級総合本科生のカリキュラムに含まれている模試を受けました。模試は、特に午後の時間配分の練習になりました。短い時間で緊張感ある中、集中して解くのは、模試以外に家ではできないことでした。
記述の添削指導が細かく丁寧であったので、記述式の採点ポイントが分かり復習時に活用できました。模試を受講して、1週間経たずにWebで添削内容が見られるところも良かったです。また、解答冊子にポイント整理という項目で、表にまとめて復習しやすくなっているため、都度テキストを確認しなくても復習しやすく使いやすいと感じました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
自習室をよく利用していましたが、いつも綺麗で、勉強しやすい環境でした。ロッカーもあり、重たいテキストなどはロッカーを活用していました。
■勉強以外の部分
直前期は、家族も資格の勉強をしていたので、それぞれが自室で勉強に集中できたのでそれも良かったように思います。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
中途半端に勉強していたときは、やはり不合格でしたが、初心に帰り、基礎から地道に理解していくことを続けた今年は合格をすることができたので、やはり基礎をじっくり学ぶことが大切だなと改めて思いました。
鴇田 征也 さん 質と量を兼ね備えたカリキュラムが合格への道標に
2025年合格目標:上級総合本科生、答練3種パック

【主な受講講座】
●「上級総合本科生」Web通信講座
●「答練3種パック」Web通信講座
【受験回数】6回
【学習開始時の職業】学生 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】不動産登記法 【不得意科目】商法(会社法)・商業登記法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・供託法
【1日の平均学習時間】7時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
中学生の時、恩師から司法書士という職業を教えていただいたことが原点です。成長と共にその専門性と魅力に惹かれ、「この道で生きていきたい」と決意しました。初心を忘れないよう、大学在学中から本格的に学習を開始しました。
<学習時の環境>
学習開始当初は、大学の講義や生活リズムとの両立が非常に困難でした。思うように勉強時間を捻出できず、計画が形骸化してしまうなど、理想と現実のギャップに悩み、何度も挫折しかける不安定なスタートでした。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
当初は独学を想定していましたが、司法書士を目指す友人の存在が転機となりました。友人の話から予備校の存在を知り、調べるうちに試験範囲の膨大さを痛感しました。効率的に合格を目指すなら、プロの指導が不可欠だと確信しました。
<TACを選んだ理由>
友人と違う環境で切磋琢磨したいという思いから他校を検討する中で、TACに出会いました。圧倒的な実績はもちろん、窓口の方の対応が非常に丁寧で、迷いが払拭されました。最後は「ここしかない」という直感で決めました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
2024年11月から退職し、受験に専念する環境を整えました。自宅では気持ちの切り替えが難しかったため、コワーキングスペースを契約。周囲の社会人の方々が働いている時間に合わせ、「通勤」するような感覚で通うことで、生活のリズムを一定に保ちました。
学習計画はカリキュラムを軸にしつつも、進捗が遅れた際は好きな科目を優先して進めるなど、あえて状況を楽しみながら柔軟に調整しました。一つひとつの項目を「今日のタスク」として軽やかに捉え、焦らず淡々とこなすことを意識しました。自分に合った環境を確保し、日々の積み重ねを習慣化したことが、長い試験期間を乗り切る支えになったと感じています。
学習時は常に時間を計測し、「今、この時間を使っている」という実感を持ちながら進めました。択一式は過去問をベースに、姫野先生の「択一式実践編」のよくまとまった図表を活用し、知識を丁寧に定着させていきました。
記述式は、記述式対策講座の問題をゲーム感覚で解き、不明点は即座に択一テキストに戻って確認しました。論点確認は効率よく、ペース配分の練習はじっくりと、メリハリをつけることを大切にしました。また、「試験当日の自分がこれを持っていれば安心できる」と思える自分専用のまとめノートを作成したことで、知識が整理され、本番も落ち着いて問題に向き合うことができました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
一つひとつの論点に納得してから進みたい性格が災いし、全科目の完了に多大な時間を要したのが最大の失敗でした。そこで後半は「まず全体像を掴む」ことに意識を切り替え、学習の停滞を打破しました。最後の一年は環境を整え、一点集中で挑みました。学習の「回転数」を上げたことが合格への鍵となりました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の受験生目線に立った誠実なお人柄と、メリハリのある指導が魅力でした。試験に出ない箇所を明確に指摘してくださるため、細部に固執して立ち止まりがちな私にとって、効率的に学習を進める大きな支えとなりました。
■TACの良かった点【教材】
慎重に学習を進めたい私にとって、各記述に根拠法令や先例、過去問の出題実績が網羅された教材は非常に心強い存在でした。根拠が明確なので迷いなく読み進めることができ、納得感を持ってメリハリのある対策に繋げられました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
膨大な試験範囲を網羅するカリキュラムは決して楽ではありませんでしたが、合格に必要な要素が凝縮されていました。この質と量を信じて食らいつくことが、結果として合格への確かな道標になったと感じています。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
上級総合本科生の講義を主軸に、答練・模試は苦手分野の補強や直前期の確認として細分化して活用しました。記述式は制限時間内のペース配分を掴む練習に特化させるなど、自分に必要な部分を戦略的に抽出したことが、学習の効率化に繋がりました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
自分一人で調べると時間がかかる箇所や、学習上の細かな疑問の解消に質問制度を活用しました。プロの回答を得ることで、自分の性格に不可欠な「納得感」を持ちつつ、深入りしすぎずに学習を効率化させる大きな助けとなりました。
■勉強以外の部分
実務経験から不動産登記が大好きになり、学習に行き詰まるとあえて不動産登記法を解いてリフレッシュしていました。無理に勉強以外で息抜きを作らずとも、好きな科目を追求して楽しむことが、私にとっては最高のリラックス法であり、継続の秘訣でした。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
長期戦であっても、その歩みに無駄なことは一つもありません。長く頑張り続けている方にこそ、苦労の先にある「別格の価値」を掴み取ってほしいと願っています。自分と予備校を信じて継続すれば、合格の日は必ず来ます。心より応援しています。
N.T さん 過去の頻出論点が分かるテキスト
2025年合格目標:上級総合本科生

【主な受講講座】
●「上級総合本科生」教室講座
●「1月答練パック」ビデオブース講座
【受験回数】6回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】会社員
【得意科目】商法(会社法)・商業登記法 【不得意科目】刑法
【1日の平均学習時間】3時間 【学習開始時からの総学習時間】4000時間~4500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
専攻も最初の職業も理系でしたが、元から文系の適性の方が高かったと思います。病気休職中に試しに勉強を始めたところ、理系とも親和性があり面白いと感じ、そのまま続けました。親族に司法書士と登記官がいたことも理由の一つだと思います。
<学習時の環境>
成績が伸び悩んだので、一度、受験指導校中心の生活に切り替え、成績がある程度に到達したことで受かるまで続ける覚悟を決めたため、正社員に戻りました。受験生でいられる安定した生活基盤を持つことに努めました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
試験範囲と内容を見て、受験指導校を利用したほうが効率がよいだろうと感じました。勉強を始めたのは30歳を過ぎてからだったので、早く合格して次のキャリアをスタートしたいという気持ちが強かったと思います。
<TACを選んだ理由>
立地、通学(模試開催)校舎の有無、価格、教材サンプルなど諸々を比較したときに、一番希望に近い内容だと思いました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
講義は時間都合がつけやすいビデオブースかWebを利用しました。自習は図書館やカフェなどを利用しました。テキスト類は持ち歩くと重いので、iPadアプリに取り込んでノートもそこに取りました。直前期以外は家ではほぼ勉強せず、家事や家族との用事に時間をあてていました。受験指導校中心の生活をしていた頃でも、上級総合本科生コース初年度の前半は講義の消化に追われて復習に時間を割けませんでした。巻き戻して聞きなおしたりするので、1コマ3時間では終わらないことがほとんどでした。2年目以降からは既知の部分が増えて少し余裕ができました。年度の後半になっても講義消化に追われましたが、復習時間を取ることにはこだわらず、問題を解く時間を多く取るようにしました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
勉強法は全科目共通でした。使用したのは上級総合本科生のテキストと、最後の年度はパーフェクト過去問集を追加しました。
択一対策は択一実践編テキストの一問一答を時間の許す限り解きました。解いたNo.の横に理解度を表すマルやバツなど印をつけ、直前期にはバツ印の出題可能性が高い論点を優先的に解きました。全ての理解は不可能と割り切り、本当にわからない問題は捨てました。覚える手助けにと、正しくなくてもいいから自分なりに答えに理屈をつけるようにしていました。
記述式はどの年も講義時間と答練・模試以外では、問題を解く時間をほとんど取れませんでした。それでも解法を覚えると点数は伸び、3年目頃から成績は安定したと思います。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
年を重ねるごとに心身の負担は増す一方で、特に超直前期は常にうっすら動悸を感じるような状態でした。対策は「余計なことは考えない」しかないと思ったので、毎日の勉強タスクの消化に集中することにしていました。タスクは必ず達成できそうな量にしておくのがよいと思います。「今日の分と決めたことは完了したから大丈夫」という安心材料が作り出せるので。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生にはいつも前向きな気持ちにしていただきました。試験内容だけでなく、受験生を取り巻く環境や心理についても熟知されているのだと感じました。
■TACの良かった点【教材】
択一理論編テキストと択一実践編テキストで、過去出題年度が記載されているのが便利でした。年度部分をマーカーで色付けしておくと、テキストを読み返すときに過去頻出の論点を見つけやすかったです。
■TACの良かった点【カリキュラム】
1つの講座の中で理論(インプット)→実践(アウトプット)と、アプローチを変えて試験範囲を2周できる点が、知識を定着させるのにとても有用だったと思います。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
模試の記述採点結果が返却されるまでの日数が短く、解いた感覚を覚えているうちに復習できるので大変助かりました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
Webトレーニングを利用していました。本気で解かずに電車内などの隙間時間にざっと読むだけでも、知識の定着の助けになってくれたと思います。
■勉強以外の部分
受験仲間を作りたいとはあまり思わなかったです。応援し、支えてくれる方々にはずっと感謝していますが、それでも受験はやはり孤独な戦いと思います。時折、全く違う分野の友人知人に会って話すと気分転換になり、また頑張ろうという気持ちになれました。あとは月並みですが、体調管理は睡眠・食事・運動のバランスだと思います。なかなか難しいですが、少し心がけるだけでも気分的に違うかなと思います。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
努力がすぐに実を結ぶとは限らない試験ですが、努力なしに実を結ぶこともない試験と思います。長く孤独な戦いの日々も、決して無駄ではないはずです。合格する日のために、健康だけは大切にしてください。
M.K さん 出題予想を踏まえたメリハリある姫野講師の講義
2025年合格目標:上級総合本科生

【主な受講講座】
●「上級総合本科生」教室講座
●「上級本科生」Web通信講座
【受験回数】8回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・憲法 【不得意科目】民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
法学部出身ということもあり、セカンドキャリアを考えた時に、法律の知識を活かした仕事をしたいと考え、法律系の国家資格に興味を持ち、身近な市民の法律家としての司法書士に興味を持ちました。
<学習時の環境>
勉強開始時は、フルタイムでの仕事をしながらでしたが多忙だったこともあり、退路を断つために退職し、勉強に専念することにしました。その後は家庭の事情で中断することもありましたが、合格することができました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
司法書士試験の勉強を開始する前年に行政書士試験の資格を取得しましたが、その際、最初は独学で頑張ろうとしましたが難しいと考え、受験指導校を利用して合格できました。その為、司法書士試験も受験指導校を利用しました。
<TACを選んだ理由>
他校を数年利用していましたが、記述で安定した点数を取りたいと考え、解法の重要さを強調していた姫野先生の記述式対策講座を受講しようと思い、また、行政書士試験の時もTACを利用していたこともあり、TACを選びました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
令和5年度、6年度と2年連続で午後択一の基準点割れでした。要因は過去問の知識の正確性と午後の戦略にあると考え、答練本科生ではなく、択一式対策講座【理論編】と記述式対策講座がある上級総合本科生を受講しました。択一式対策としては、過去問を繰り返し、知識の正確性を高めることを中心にしました。一方で、未出知識や周辺知識も必要と考えていたため、理論編の講義のスケジュールに沿って受講しました。記述については、姫野先生の講義をベースに解法を習得し、論点を押さえるようにしました。直前期も択一は過去問を回すことを中心に、記述は初見の問題と前年の模試等を活用して毎週2問づつ解くようにしました。
<科目別勉強法>
民法、マイナー科目は、過去問と条文、不登法は過去問、会社法・商登法は過去問と過去の模試等や他資格の過去問も加えていました。
<学習時に重視したポイント>
過去問は、オートマ過去問とパーフェクト過去問を組み合わせ、オートマ過去問をベースとしました。同じ知識でも異なる問われる方をしていることがあるため、複数回出題されている場合は全てパーフェクト過去問で確認、オートマ過去問に掲載されていない肢はパーフェクト過去問で解きました。その際、キーワードを意識し、間違った場合は思い出し方を考えるようにしました。
<記述式対策>
記述式対策講座で習得した解法を活かして解くことを意識し、ひな形は模試当日にひな形集でざっと確認し、間違えたひな形を確認する程度でした。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
他校で受験した模試では、合格判定を取れていましたが、TACの模試では、記述は高得点にもかかわらず、午後択一が思うように点が取れず、全て合格判定を取れませんでした。それでも、過去問知識の正確性の向上を重視し、本試験前日まで過去問を繰り返すことに専念しました。本試験では、午前、午後とも基準点プラス15点(5問)の上乗せ点を取ることができ、信じて諦めずに良かったと思いました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生は、テキストの内容を黒板で分かりやすく表や図を使用して解説していただき、また、出題予想を踏まえたメリハリのある講義をしていただいたので、自分自身もメリハリをつけた勉強をすることができました。
■TACの良かった点【教材】
テキストの冊数と厚さに圧倒されましたが、その分テキストは網羅性が高く、模試等で初めて見る知識を問われても、このテキストで確認すればよく、改正点や新しい先例も補足資料で提供されるので、安心感がありました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
記述式対策講座は、他の受験指導校よりも、多くの時間をかけ、かつ段階を踏んでしっかりと講義をしていただき、また解法をどのように使うかも説明していただき、どんな問題でも対応する自信につながりました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
模試は、本試験のシミュレーションとして会場受験を選択しました。昼休憩時間は何を食べるかも含めて何をするかを考え、また、午後については時間配分、解く順番を意識して受験しました。全ての受験回において、記述は、解法を活かして良い点数を取れていましたが、午後択一の点数が芳しくありませんでした。しかし、模試は模試と割り切って、復習はあまり時間をかけず、普段の学習に戻るようにしていました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
教室講座を受講していましたが、専業で勉強していたこともあり、通学せずWebフォローを有効活用していました。倍速再生や聴きたいところだけを視聴したりと効率的に受講するようにしていました。
■勉強以外の部分
規則正しい生活をすることを心掛け、睡眠時間を削らないようにしました。また、1日中だらだらと勉強することはしないようにし、決めた範囲の勉強をしたら、後は自由に過ごすことにしていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
日々の勉強では、計画を立てて、コツコツと積み重ねることや、確固たる知識になるよう繰り返すことが、試験当日については時間配分、解く順番を含めた戦略も重要だと思います。そして、最後の最後まで諦めない気持ちが大事だと思います。
N.M さん 未出分野も対策することができた
2025年合格目標:上級総合本科生、記述式過去問解説講座

【主な受講講座】
●「上級総合本科」Web通信講座
●「記述式過去問解説講座」Web通信講座
【受験回数】10回以上
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】補助者
【得意科目】不動産登記法・商法(会社法)・商業登記法 【不得意科目】民法・民事保全法・民事執行法・司法書士法・供託法・憲法・刑法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
新卒から勤めた会社で一生サラリーマンをやることに漠然と不安を感じていました。将来のこと、転職を考えるにあたって資格を取って独立できる仕事で司法書士を見つけました。法律の勉強を始めると、案外面白かったので、これなら、一生好きなだけ働けると思い、転職を決意しました。
<学習時の環境>
家族がいるので専業受験はありえませんでした。そのため、最初から最後までずっと働きながらの受験でした。最初の3年ほどは基礎講座と答練や単科を受講していましたが、その後は金銭的に厳しく、ずっと独学でした。合格の6、7年前からTACの本科生やパックコースを毎年受講して、やっと合格できました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
独学では、過去問以外の既出分野の習得ができず、予備校利用なしに合格はありえないと考えました。
<TACを選んだ理由>
TACの姫野先生なら、分析はすべてお任せできて、自分は覚える努力をするだけでいいからです。幸いなことに、択一式対策講座も記述式対策講座も公開模試の解説講義もすべて、姫野先生が担当されていたので、教え方に一貫性があり助かりました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
合格直前の6、7年前から合格年まで勉強を休んだ日はほぼありません。4年前だったか、自己採点で合格を確信して夏から合格発表まで遊んでしまったら、せっかく高まった知識が瞬く間に消え去り、その後の立て直しに死ぬほど苦労した経験があるので、確実に合格発表を見るまでは絶対勉強を中断させないと決めていました。
とにかく過去問演習をひたすら繰り返しました。姫野先生のアドバイスで、パーフェクト過去問集をアウトプットでなく、インプットで利用することをとにかく繰り返しました。なかなか固まらなかった民法がこれによって最後の年はやっと固まったので合格できたのだと思います。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
私の勉強方法は独特なので、他の受験生はあまりマネしない方がいいと思います。
まず、姫野先生の講義は当然すべて受ける。択一式対策講座【理論編】から始まって記述式も、公開模試ももちろんすべて受けます。本科生コースでさえ、もう何年も毎年受け続けたので、各講座の復習はあまりやらなかったです。
私の毎日の勉強は、
・会社法、商登法、司法書士法除く全教科のパーフェクト過去問全部を速読的にインプット
・民法、不登法は毎日、商登法、会社法、その他科目はなるべく、択一理論編テキスト全ページを速読
この2点の繰り返しです。
具体的には、民法なら問題全肢をパッと見てすぐに正解と論点を思い出す、そして数秒で次の問題に移る。もちろん、初めは分からない問題も数多くあるのであまり気にせず続けます。
択一理論の民法、不登法、会社法のテキストも速読的に流し読みします。ただし、それぞれの内容が薄い分、絶対に1日のうちに全部終わらせて、ひたすら毎日繰り返しました。それをおそらく3~4年ほど毎日続けていました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
一番の失敗は、自己採点で合格だと確信して、夏の本試験後、合格発表まで勉強を中断させたことです。直前期にあれだけ苦労して仕上げた知識が、見事にきれいさっぱりなくなってしまいました。知識の暗記レベルは、数か月かけないと上がらないのに、何も勉強しなければ数週間で下がってしまうことを身をもって知りました。
合格した今年の夏でも、試験勉強の火種は絶やさないようにするため、来年度向けの本科生コースを受講していました。万が一不合格だったらやばいから、この講座だけは最低限の勉強を続けられるようにするための配慮です。といっても最初の7月は講義以外にテキストを読んだり、会社法の昨年講義を再度Web視聴したりしていましたが、8月以降はさぼってしまいました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生は、もう10年以上も前から知っているし、理論編や実践編の前身となる(?)tune-up講座を受けたりもしていました。そのころから、過去問知識だけでなく、未出分野の出題分析にも、他の講師より長けておられたので、この先生しかいないと私は思っていました。司法書士受験界の1~2歩先をいくのが姫野先生です。姫野先生が今教えている未出知識が数年後出題されます。本試験が、あとから姫野先生に追いつくのです。
■TACの良かった点【教材】
択一式対策講座【理論編】、記述式対策講座のテキストは、私の合格に欠かせませんでした。過去問解説だけ、基礎知識だけの薄っぺらいテキストは確かに飲み込みはいいかもしれませんが、未出分野が出題されると全く歯が立ちません。未出分野にも十分対応できる理論編テキストは傑作でした。
また、記述式対策講座は姫野先生の解法をフルに利用できるので、当然欠かせませんでした。
■TACの良かった点【カリキュラム】
スケジュールは姫野先生が監修されているので、乗っかってしまうのがベストなので、あまり気にしたことはありません。姫野先生の言われるがままに勉強進めればいいからです。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
模試の成績は全く関係なく、特に高得点をとっても全然あてにしませんでした。しかし、悪い点数を取った時は、自分の弱点を示しているので注意した方がいいと思いました。数年前、不合格だった時の模試は、実力Check模試から公開模試までの流れで見ると、見事に下落基調にあったことが後から振り返ると分かりました。合格年度の模試は、実力Check模試が人生最高、公開模試はかろうじてキープの状態でした。
■勉強以外の部分
私は専業でなく兼業受験生だったので、朝から晩まで毎日勉強できるわけではありませんでした。そのため、土日祝祭日は貴重です。朝起きて、食事風呂以外はずっと勉強時間にあててました。こんな贅沢な時間を使える自分は恵まれていたと思います。よって、勉強以外にあまり思い出はないです。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
「合格者の言葉はあまり信じるな。特に鵜呑みにしたらだめだ。」逆説的ですが、受験生にはそうお伝えしたいです。信じられるのは、信頼できる講師の言葉と講義だけです。合格直後にいきりだす合格者の受験論は参考程度に聞き流すべきです。
酒巻 創史 さん 記述式対策講座なしでは合格はなかった
2025年合格目標:上級本科生、記述式過去問解説講座

【主な受講講座】
●「上級本科生」教室講座
●「記述式過去問解説講座」Web通信講座
【受験回数】3回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法・民事訴訟法
【不得意科目】商業登記法・刑法
【1日の平均学習時間】10時間以上 【学習開始時からの総学習時間】3500時間~4000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
仕事で弁護士・司法書士とやり取りする機会があり影響を受けました。法学部出身で、もともと法律の勉強をすることが好きでした。また、父が亡くなった際に相続登記を本人申請した際に、不動産登記により興味を持つようになりました。
企業で仕事をしていたが、会社の利益よりもお客様のことを第一に考える仕事をしたいと考え、公益性のある仕事ができる司法書士になりたいと考えたのも動機の1つです。
<学習時の環境>
学習開始時は兼業受験生でした(勉強時間は、平日は2~3時間、土日祝日は10時間程度)。昨年の9月に早期退職制度を利用し退職。以後9ヶ月間、専業で毎日10時間以上TACの自習室で勉強しました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
宅建士・行政書士・FP1級は独学で合格できましたが、司法書士試験は記述式問題があり、独学での合格は厳しいと考えたからです。
<TACを選んだ理由>
行政書士試験はTACの市販テキスト(合格革命)を使用し、司法書士試験の講座を受講する前はTACのオートマシステムテキストを読んでいたので、TACのテキストのレイアウトに慣れていたこと、記述式問題が時間内に解答することができなかったため、定評がある姫野先生の記述式対策講座を受講しようと考えたからです。また、自習室が遅くまで利用することができたことも大きいです。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
上級本科生(記述式対策講座・択一式対策講座【実践編】)を受講しました。
姫野先生から「記述式対策講座が始まるまでは択一をやっておいてください。」とガイダンスで事前に話があったので、講座が始まるまでは、オートマテキストを全科目読み直しました。講座を受講した目的の一つとして、学習のペースメーカーにすることもありましたので、記述式対策講座 → 択一式対策講座【実践編】 と、講座の内容に合わせて勉強を進めました。
年内に主要4科目と民訴3法の過去問(TACのパーフェクト過去問)も並行して解き、択一式対策講座【実践編】が始まってからは、択一の勉強は講座のテキストのみを繰り返し(3周)ました。年明けからマイナー科目の過去問も解きました(3周)。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
【択一式】
・民法・会社法・不登法・商登法
過去問(TACのパーフェクト過去問)と択一式対策講座【実践編】のテキストの繰り返し
・マイナー科目
過去問(TACのパーフェクト過去問)の繰り返し、と択一式対策講座【実践編】のテキストは1周のみ。
模試を受ける際は、記述の時間を確保するために午後択一は50分で解くように意識しました。
【記述式】
記述式対策講座【理論編】テキストの繰り返しと、記述式対策講座実践編・実践総合編の問題(講義でやらなかった問題も解きました)に取り組みました。
姫野先生から「実践編の小問だけを繰り返しても本試験に対応できない。逃げずにフルサイズの問題を解くべき」との指摘があったため、2月頃から実践総合編のフルサイズの問題と過去問を繰り返しました。時間を気にせず書き切りたい気持ちを抑え、時間を1時間に区切って、書けるところまで書くことで、常に時間を意識しました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
去年の10月からTACの自習室で朝9時から終了時刻まで毎日勉強しました。座りっぱなしだったため、日を追うごとに両膝が痛くなり、自習室に痛み止めや塗り薬を持ち込んで勉強しました。記述の書き過ぎで右手が腱鞘炎になり、痛みで年明けにペンが握れなくなり、姫野先生に相談したところ「書かなくても記述の勉強はできる。不登法・商登法とも解答例を見て、必要な添付書面を思い出したりする方法もある。」とアドバイスをもらいました。整骨院に行き治療を受け、模試は右手にテーピングを巻き受験しました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の記述式対策講座を受講していなければ、合格することはできなかったです。
記述が苦手(時間内に解くことができない)だったため、藁をもつかむ気持ちで受講しましたが、テンポのいい講義でわかりやすく、先生自ら記述の問題を解くのを間近で見ることにより、解法を習得することができました。本試験では不登法を40分で解くことができました。姫野先生の記述式対策講座は合格するために必須になっていると断言していいと思います。
■TACの良かった点【教材】
記述式対策講座の理論編のテキストが秀逸でした。過去の本試験で出た登記できない事項、添付書面、イレギュラー事案、出題ミスなどが明記されており、記述のインプットに関しては、理論編のテキストのみを繰り返しました(3周)。記述式対策講座の実践編のテキスト(問題)には、過去の問題を分解した問題(小問)が載っており、全ての論点を網羅していたため、本講座と過去問以外は使いませんでしたが、本試験に対応することができました。
択一式対策講座【実践編】のテキストは未出の問題や重要な先例が載っており、直前期は実践編のテキストのみを繰り返すことで本試験に対応することができました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
記述式対策講座の理論編(不登法・商登法各6回)で答案作成に必要な知識やインプットを最初に行い、実践編で小問を解くことで、論点を理解することができ、実践総合編でフルサイズの問題を解くことで、登記すべき事項を把握することができます。実践総合編では姫野先生自ら記述の問題を解くのを間近で見ることにより、解法を習得することができました。択一式対策講座【実践編】では未出の論点や新しい先例も取り上げており、本講座のみで過去問以外の問題に対応できます。実践編の最終回に過去の答練の問題(五肢択一)を講義中に解くことで、スピードアップを図ることができました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
記述の答案の採点が早かったので助かりました。実力Check模試から第3回公開模試までの結果が成績表にまとめて載っており、第3回公開模試が終わった段階で4回の模試の結果が時系列に確認できたのが良かったです。今年は初めて総合判定Aを取ることができ、回数を重ねるにつれ評価が上がることでモチベーションを上げることができました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
竹内先生の月1回のオンラインホームルームに助けられました。Zoomを使用したライブで行われましたが、アーカイブも残っており、リアルタイムで視聴できなくても後日確認することができました。受講生からの事前質問に答えてくれることはもちろん、「この時期に受験生が陥りやすい点」などを教えていただきました。直前期の「みなさん、記述も大事ですが、午後択一は大丈夫ですか?」との指摘がなければ、受からなかったかも知れません(まさに記述対策ばかりやっていました)。
■勉強以外の部分
自分は50代後半の年齢ですが、最終合格後直ぐに司法書士法人から内定をもらいました。年齢的に就職できるか不安になることもありましたが、現在は司法書士の有資格者が足りない状態であり、就職に関しては心配しなくても大丈夫です。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
人生を賭ける価値のある資格ですが、生半可な覚悟では合格できない試験であり、人生を棒に振る危険性もあります。姫野先生についていけば必ず合格できると思いますが、相当な覚悟を持って挑んで下さい。健闘をお祈りします!
丹波 翔太 さん モチベーションが上がる姫野講師の講義
2025年合格目標:上級本科生

【主な受講講座】
●「上級本科生」Web通信講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】アルバイト・パート 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法・憲法 【不得意科目】民事訴訟法・民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】7時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
30代にさしかかったとき「果たしてこのままの人生を続けてよいのか?」という問いを考えたときに「いやダメだな」と思ったことがきっかけです。恥ずかしながら、私の20代の経歴は決して社会人として誇れるものではなく、それを覆すには何か資格を取る必要があると考えました。
数ある資格の中で司法書士を選んだのは、第一にそもそも法律に興味があったこと、第二に将来独立に強い職であること、第三に社会への貢献度の高さに魅力を感じたからです。
<学習時の環境>
前職は辞め、アルバイトを週2~3日ほどしながら勉強に割ける時間を可能な限り多く確保していました。直前期にはアルバイトを退職し、完全に受験に専念しました。そして、不合格だった場合はまた同じような条件のアルバイトに勤務、ということを繰り返して受験期間中の生活をやりくりしてました。アルバイトについては、勉強中心による運動不足対策とメリハリをつけることを考え、あえて補助者などは選ばずに肉体労働系をやっていました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
予備校の利用を決めた理由は明確で、ズバリ『独学で3年やってもダメだったから』です。受験勉強を開始した当初から「3年独学でやってみてダメなら予備校を利用しよう」と決めていました。独学で挑戦してみて思ったこととしては、独学でも合格することは十分可能だが、やはり確実性に欠けるということ。なので、予定通りに予備校を利用するという決断に至りました。
<TACを選んだ理由>
独学時代から市販されているTACのテキスト類を活用していたことと、講師の勉強に臨むうえでの考え方に共感できる点が多かったことです。私は姫野講師の講座を選択したのですが、姫野講師は「合格に必要な勉強を100とするなら、目指すべきは130以上の勉強だ」という趣旨の話をされており、私はこの考え方にとても共感しました。確実に合格を目指すならやはりそうだよなと。単なる合格を目指すのではなく『確実な合格』を目指すところが最大の決め手だったと思います。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
とにかく過去問を「軸」としたテキスト学習を徹底していました。これでは分かりにくいと思うので、具体的に説明します。
大前提として、問題の論点がわかるレベルまでのテキスト学習は当然にやるものとして、その段階を越えたらひたすら過去問を解きまくります。各肢ひとつひとつを検討し、正解できた肢はひとまずはOKとして放置し、間違った肢についてはなぜ間違えたのか、なぜわからなかったのかをテキストに戻って確認し、該当箇所に色ペンで下線を引くなどして間違えた論点であることを一目でわかるようにします。必要があれば、自分なりのわかりやすくする解説や間違えた理由なども加筆していました。そして、1週間後に同じ問題の肢を解いてみて、正解できたらOK、間違えたらまた同様にテキストに戻って確認と下線を引くようにします。下線の色については、間違い1回目は赤、2回目は青、3回目は黄色蛍光ペンといったように間違えた回数によって線を引く色を変えて、よく間違える苦手な論点は結果としてカラフルになるようにしました。
こうして育てたテキストは毎日1~2時間は読み込むようにし、それ以外の時間は上記の過去問演習をひたすら繰り返してさらにテキストを育てます。
少々迂遠な方法かもしれませんが、このように育成したテキストは直前期に非常に役立ちます。直前期はとにかく苦手を潰すことが重要になってきますが、その苦手な論点ほどカラフルに目立つようになっているためテキスト周回がしやすくなります。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
科目別に勉強法を変えるといったことはせず、全科目において上記のようなアプローチをとっていました。ただ、各科目に割く時間の割合に関してだけは気を使っていました。メジャー科目については、穴のないようとにかく念入りに時間を使い、マイナー科目については「正直、よくわかってないけど過去問は正解できてるから良いか」くらいの気持ちでそれほど時間を割かないようにしました。
記述式は、とにかく姫野講師の解法を会得するに尽きると思います。この解法が身についてくると択一の実力を伸ばせば、同時に記述も伸びるという自信がついてくるはずです。結果として「択一対策こそ最たる記述対策である」という図式ができあがると思います。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
受験時代の苦労としては、やはりストレスを原因とする体調不良がしばしばみられたことです。特に記憶に残っているのは、ストレス性の不整脈が出るようになった時期があったことです。症状自体は、薬の服用で抑えることができたのですが、根本のストレスを少しでも軽減するために、休息はしっかりとるよう心掛けるようになりました。
また、受験の苦労を真に共有できる人が周りにいなかったことも、少しつらいところであったと思います。受験仲間を作ることを考えたこともあるのですが、私の性格上きっと成績など比較して勝手に落ち込むことが目に見えていたので、友人に愚痴を聞いてもらうにとどめていました。
■TACの良かった点【講師】
姫野講師の講義は非常にテンポが良く、板書と解説もとても分かりやすく感じました。そして、毎回とても熱意のある講義のため、講義を受けると同時に自分の勉強のモチベーションが上がるのも感じられました。そのため、カリキュラムが開始してから本試験まで、勉強のモチベーションが上がらないといった悩みは皆無だったように思います。
■TACの良かった点【教材】
特筆すべき点はやはり圧倒的な網羅率だと思います。正直「これはさすがにやりすぎなのでは?」と思うくらいに細かい論点まで網羅しています。だからこそ「この教材以上のことはやらなくていい」という信頼感があります。論点を深追いして疑問点が出てきたとしても、教材内に何の言及もないのであれば、少なくとも試験では必要ない知識なのだと切り替えることができる。そういった点がとても役に立ちました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
基本的にひたすら流れに身を任せるだけで、適切な時期に適切な科目の学習に入れるようになっているな感じました。特にマイナー科目に関しては「いつ頃から手を出そうか?」と悩むところですが、とりあえずカリキュラム通りのタイミングで開始して、良い具合に本試験までに仕上がったと思います。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
私は上級本科生を受講していましたが、これには計4回の公開模試が含まれていました。
この模試の活用については、すべて本試験当日の予行練習と捉えて受けていました。会場受験を申し込んでいたため、起床時間から家を出るまでの過ごし方や持参する物など、本試験当日の行動の流れをシミュレーションすることに徹底していました。
模試の解説講義は、主に記述式問題に焦点を当てて解説してくださるので、直前期に記述が心配な方にとってはとても有益な講義になるのではないかと思います。
■勉強以外の部分
勉強以外の部分で気を付けていたことは、直前期を除いて週に1日くらいは勉強を離れて息抜きする日を設けるようにしていたことです。私はサイクリングや登山を趣味にしているので、日帰りできる範囲で遠出して、自然に触れることでリフレッシュしていました。
ほかにはSNSを禁止していました。特に司法書士試験や他の受験生の情報が目に入ることは徹底的に避けました。これは予備校や講師陣の発信も含みます。そういった情報を目にすると、少なからず一喜一憂する自分がいるので、そんなことで心を揺さぶられるなら避けたほうがマシだと判断したためです。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
とにかく持てる全力を尽くして頑張ってください。それでダメだったときは、きっととても落ち込むことになるでしょう。しかし、全力を尽くした失敗であればあるほど、次の課題や自分の弱点が明確になります。課題や弱点が明確になれば対策を考えることができる。対策が見つかれば、次はそれを乗り越えることに注力する。私はその繰り返しでなんとか合格することができました。
決してスマートなやり方ではないと思いますが、不合格を過度に恐れる必要もないと思います。その経験は将来の糧に必ずなります。
これを読んでいるあなたが、いつか合格されることを心からお祈り申し上げます。
髙橋 一輔 さん 目から鱗の連続 姫野講師の実践的なテクニック
2025年合格目標:上級本科生、記述式過去問解説講座

【主な受講講座】
●「上級本科生」Web通信講座
●「記述式過去問解説講座」Web通信講座
【受験回数】5回
【学習開始時の職業】自営業 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】不動産登記法・商法(会社法)・商業登記法 【不得意科目】憲法・刑法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
会社経営や不動産所有の経験を通じ、登記手続き等で司法書士と関わる機会が多くありました。専門知識や知見に感銘を受け、年齢を重ねても社会的需要があり、自身の経験を活かしながら法律家として社会に貢献したいと考え受験を決意しました。
<学習時の環境>
学習当初は専業ではありませんでしたが、途中から退路を断って、受験対策に専念する決断をしました。一日中学習できる環境を活かし、規則正しい生活リズムで長時間集中して勉強に取り組みました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
司法書士試験は学習範囲が膨大であり、受験が複数年度にまたがると法改正もあります。ある程度基礎力はあったので、特に実践的な解答テクニックを体系的に学ぶため、指導校の利用は必須だと考えました。
<TACを選んだ理由>
前年の受験で実践的な解法不足を痛感したため、実践的テクニックが鍵だと考えました。YouTubeで拝見した姫野先生の講義は、知識確認だけでなく本試験で確実に点を取る解法を惜しみなく教えてくださると確信し、TACを選びました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
前年試験後の10月から学習を再開し、途中から専業に切り替えたことで、規則正しい生活リズムを確立しました。再開直後は、本番で失点したマイナー科目を過去問演習中心に徹底的にやり直しました。その後は、上級本科の実践編のカリキュラムに沿って学習を進めました。直前期の6月からは、模試がない日には毎日、不動産登記法または商業登記法の記述式過去問を1時間で1問解く実践練習をルーティン化。試験直前一週間は、毎朝50分以内を目標に午後の択一式過去問を解き、本番の時間感覚を体に染み込ませました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
択一式対策は、実践編の一問一答形式のテキストを使用し、一度全肢を解いた後は「理由が思い出せない肢」だけを潰す形式で3~5周繰り返しました。知識のアウトプット力を高めることを重視しました。記述式対策では、それまで身につけた解法を捨て、姫野先生の解法へ完全に移行しました。論点は既習であったため、本番で速く正確に解答することに重点を置き、記述式過去問解説講座も受講し2~3周反復しました。姫野先生の解法の習得と実践的な反復練習が合格に直結したと感じています。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
前年の択一基準点落ちが判明した頃、学習と並行して司法書士補助者としての実務経験を積もうと考えました。しかし、実務未経験のため、応募した事務所から書類すら見てもらえないという悔しい経験をしました。この挫折を「絶対に合格してリベンジする」という強いエネルギーに変え、より一層学習に集中する原動力としました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の上級本科生では、無料のYouTubeチャネルでは明かされない実践的テクニックが盛りだくさんで毎回目から鱗でした。しかも、一コマ3時間と時間が決まっていたため、時間の無駄なく効率的に学習が進められ、受講した甲斐がありました。
■TACの良かった点【教材】
上級本科生のテキストは、択一実践編ではテキストが一問一答形式で、アウトプット重視の学習スタイルに最適でした。また、記述式の理論編では実務でも役立ちそうな知識が満載でした。
■TACの良かった点【カリキュラム】
上級本科生は、基礎の総ざらいから直前期の実践的な演習まで、合格から逆算された完璧な構成でした。直前期は得た知識を解法に当てはめながら実践的に過去問を解くことで、本番で時間内に正確に解ききる力が身につきました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
模試は特に午後の解答手順を変えながら受け、本番のシミュレーションとして利用しました。また、択一では答えが2択まで絞れていれば、たとえ間違えたとしてもそれが過去問の肢でなければ良しとして点数は気にしてませんでした。
単科の記述式過去問解説講座も受講しました。姫野先生の解法は、例年と異なる出題形式の今年の不動産登記記述でも全く動じることなくほぼ完答できるほどの信頼性でした。過去問の記述式問題を数多くこなしたことで、合格が確実なものになりました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
テキストだけでは解決できない細かい論点や、間違えた原因について質問できる体制が大変助かりました。独りで悩みをかかえること無く、速やかにプロの回答をいただけたため、学習を円滑に進めることができました。
■勉強以外の部分
勉強に専念する環境であったため、生活リズムを乱さないよう意識しました。リラックス法としては、夜9時以降の学習は寝入りが悪くなるのでやめて朝方に切り替えたのと、毎日欠かさなかった晩酌です。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
TACの指導と自分を信じ、試験日まで続けてください。高地トレーニングを積んだように、気がつくときっと合格点を突破できる力が身についています。ただし、合格は20人に1人。進むべきか退くべきかの冷静な判断も大事だと思います。
Y.U さん カリキュラムに沿って迷いなく学習
2025年合格目標:上級本科生

【主な受講講座】
●「上級本科生」Web通信講座
【受験回数】10回以上
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】会社員
【得意科目】民法・不動産登記法・商法(会社法)・民事訴訟法 【不得意科目】・商業登記法・民事執行法・憲法・刑法
【1日の平均学習時間】2時間 【学習開始時からの総学習時間】3500時間~4000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
なんとなく、難しい試験の勉強をしたと考えたのがきっかけでした。どこかで見かけた資格の情報をもとに、本当になんとなく学習を始めてしまいました。
<学習時の環境>
働きながら、家事や育児の隙間時間を使用して勉強していました。仕事中も本を読んでいられる待機時間など、家にいるときは食事の準備や掃除中などのながら勉強といった感じで、隙間時間を有効に使うようにしていました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
長いこと模試も受講せずに本試験を受けていました。今年度は、合格後に実務に関わりたいと考え、改めて体系的に学習することを目的として予備校の使用を検討しました。
<TACを選んだ理由>
動画配信サイトで拝見していた動画で、姫野先生の記述式講座に惹かれたことが決め手です。教育訓練給付制度が利用可能だったことも、TACを選んだきっかけの一つです。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
学習初期の頃は、細かい知識まで押さえようとする反面、きちんと暗記せずおおざっぱに覚えることばかりしていて、かえって効率の悪い学習をしていたように思います。今年度は、上級本科生のカリキュラムに沿って学習を進めるよう意識しました。講義の配信が終わったあとも、姫野先生の出題予想にしたがって、過去問とテキストをまわしていました。択一式対策講座にせよ、記述式対策講座にせよ、分量がたいへん多く、フルタイムで働きながらの受験生にとっては、こなしていくだけで十分すぎる学習量だったと思っています。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
科目別の勉強方法も特にこだわりはなく、今年度はとくに択一式対策講座や記述式対策講座に乗っかって勉強しました。間違えたり、宣言できない問題やあやふやな論点にはふせんを貼って、何度も繰り返しました。今年度特に重視したポイントは、択一式問題でも同じ論点が記述式で出題されたらどうなるか毎回短時間想像することや、午後科目は早く正確に解くことなどでした。記述式対策は、記述式対策講座を信じて、とにかく姫野先生の解法を使いこなせるよう、練習することに専念しました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
上でも書いたとおり、本当になんとなく勉強を始めてしまったので、困難に直面してばかりの受験勉強でした。マイペースに勉強していたので、苦労と感じたことはあまりありません。試験内容の具体的な困難は午後の時間配分ですが、この点は、上級本科生の講座に大変救われました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生には、本当に感謝しています。説明も分かりやすいです。記述式対策講座は、記述式”試験”の考え方を抜本的に見直し、その上で、解法を教えてくださる講座でしたが、解法を作ったご本人が実践し、解説してくださるので、理解が進んだように思います。
■TACの良かった点【教材】
択一式対策講座と記述式対策講座は、テキストのページ数が膨大なものでした。合格に必要な範囲はすべて網羅してあったのだと思います。講座で触れる部分、今年度は触らなくて良い部分なども指摘していただけて、使いやすかったです。
■TACの良かった点【カリキュラム】
講義のペースについて、兼業の受験生にとっても、こなすだけならばついていけるカリキュラムだったかと思います。年明け辺りから本格的に講義が始まる予定となっており、勉強のペースメーカーとしても大変役立ちました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
模試のみ利用しました。4回の模試のうち、2回は会場受験、2回は自宅受験としました。会場受験については、会場で受験することのシミュレーションを意識しました。4回通じて、特に午後の時間配分の練習を意識しました。姫野先生が「模試の出来不出来は関係ない」とおっしゃってくださっていたので、択一では少しでも曖昧だと感じた問題はマークしないで不正解とすることで、点数の上振れを防ぎ、気分が緩まないようにしました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
質問メールなどは特に利用する機会がありませんでした。出題の趣旨の分かりにくい問題などについては、質問メールを利用して、どう考えるべきか、フォローしていただくほうが良かったかもしれません。
■勉強以外の部分
超直前期などは特に、空いている時間を少しでも勉強にあてようとして、かえって焦りすぎてしまうので、毎日短時間でも、子どもたちをテレビゲームを一緒にやるなど、休憩するようにしていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
司法書士試験は難易度の大変高い試験です。受験勉強も大変で、覚えたはずの知識がすぐに抜けて、モチベーションが下がることもあると思います。ですが、やりがいも大きい試験です。頑張ってください!
荒井 幸治 さん とにかく分かりやすい山本講師の講義
2025年合格目標:山本プレミアム上級本科生

【主な受講講座】
●「山本プレミアム上級本科生」ビデオブース講座
●「1月答練パック」ビデオブース講座
●「山本オートマチック<1年本科生>」ビデオブース講座
【受験回数】2回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法・商法(会社法)・民事訴訟法・民事執行法・司法書士法・憲法・刑法・供託法 【不得意科目】・商業登記法・民事保全法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】2500時間~3000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
働いていた会社では、金銭的にも体力的にも働き続けるのは厳しいと思いました。このままでは厳しいと思いつつ、経歴的にもあまり良い転職先は見つからないだろうなと思い、手に職をつけようと考えたました。その際、あまり簡単な資格では意味がないと思い、難関資格である司法書士試験を受験しようと思いました。
<学習時の環境>
最初の受験時は、働きながら休みの日に講義を受けていました。2年目は受験に専念し、朝からTACの自習室に通い、日々の勉強をルーティン化しました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
いくら頑張っても、努力の方向性を間違えてしまっては時間の無駄になります。予備校を利用すれば学習の質が担保されると考えました。また、日常生活で勉強のペースを作るのがあまり得意ではないため、予備校の講義をペースメーカーとして利用しようと思いました。
<TACを選んだ理由>
山本先生の本を読んで理解しやすく、また合格者の実績も高かったため、「この講義をしっかりやれば合格できる」と思ったからです。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
初期の学習スケジュールは、講義を受けたらその日のうちに講義範囲の一問一答をやり、次の講義を受けるまでに最低でも2回は復習しました。時間があれば、講義の急所に記載されている部分をオートマテキストに下線を引きながら軽く読み返しました。優先順位としては、本体の過去問部分が最優先、次に一問一答です。基本的には、過去問が理解できてれば問題ないと思います。
主要科目の講義が終わったくらいの段階から過去問集を始め、記述式のひな形を毎日5個くらいづつ書き取りを行いました(書く分量によって数は前後します)。
直前期は、ひたすら過去問とひな形に取り組みました。記述式は、模試と答練で「どのような手順で解けば良かったか」を確認し、知らなかった知識の吸を行いました。記述式の過去問は、最後の2週間、毎日1問解いてました。
過去問をやった回数は、3月までに主要科目は2回、マイナー科目は民事訴訟法のみ2回です。4月以降の直前期は、主要科目は4回、マイナー科目は毎日20ページくらいずつやってました。
勉強法としましては、満員電車でも手軽に勉強できるように講義の急所などの配付物や特に覚えなければいけないなと感じた箇所を写真にとって眺めてました。
記述式対策は、ひな形と基本的な知識は過去問や講義の復習で身につきました。後は模試や過去問で問題になれれば、問われてる知識は似たようなことばかりなのだなと感じました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
マイナー科目を後回しにしてしまったことで、直前期に主要科目をやる時間を圧迫してしまったことです。
マイナー科目は一見とっつきにくいとこはありますが、過去問を見ると同じようなことばかり出題されているので、講義を受けたら記憶が新しいうちに過去問集を買って解いておくべきだったと思います。特にオートマ過去問は、分野別に似た問題を並べているため、その傾向が顕著にわかると思います。
また、マイナー科目の問題は知識をストレートに問うものが多く、考えるような問題は少ないので、同じページ数でも労力は主要科目よりかなり少なくて済み、繰り返すほどに楽になっていくと思いました。
■TACの良かった点【講師】
山本先生の語り口が楽しそうで、聞いていてリラックスできました。判例や難しい論点に関しても、過去の実例を交え、わかりやすさ重視でかみくだいて説明してくれます。講義の中でも過去問を解説してくれるため、問題を解く上での着目点や考え方を学べる。ことができました。
■TACの良かった点【教材】
オートマは独学でも合格者数が多いと言われているだけあって、非常に分かりやすいです。さらに、講義を受けることでより勉強時間を大幅に圧縮できると思います(といってもかなりの努力量は要するが…)。
過去問に関しては、オートマで学習するならオートマ過去問が山本先生流の解説なのでいいです。記述式に関しては、収録数が多いパーフェクト過去問が時間のある方にはオススメです。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
記述式は、問題の流れや分量、難易度が本試験に即したレベルになっており、時間制限のある中でかなり充実した内容だと思いました。時間がない場合は、記述式だけでもやっておくだけでも価値はあると思います。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
毎月行われるオンラインホームルームで、各種の告知(出願の時期等)をしてくれるのでありがたかったです。
過去問をや解いていると、解説だけではどうしても理解できない問題があったので質問メールを送りましたが、返答が早くポイント押さえたもので非常にわかりやすかったです。
■勉強以外の部分
専業受験生だったので、1週間のルーティンを作り実行していました。勉強があまり進まない日もありましたが、そのルーティンを守り続けました。日曜日だけは完全に休んでいました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
非常に難しい試験ですが、その難しさゆえに、合格したときのリターンも非常に大きいです。TACは実績もいいので勉強の質は担保されてます。合格後の人生を想像し、ひたすら努力すれば合格できるので頑張ってください。
K.N さん 山本講師の身近な事例や実務話が法律を「楽しい」に
主な受講歴:山本プレミアム上級本科生

【主な受講講座】
●「山本プレミアム上級本科生」DVD通信講座
【受験回数】3回
【学習開始時の職業】その他 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・商法(会社法)・刑法 【不得意科目】商業登記法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】3時間 【学習開始時からの総学習時間】2500時間~3000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
長年投げやりに生きてきてしまったのですが、これからの人生をやり直したいと思い、宅建をはじめとして複数の資格を取得してきました。しかし、実際には何も変えることはできませんでした。そんな中、YouTubeで山本先生の体験講義を拝見し、大学時代の講義を思い出しました。そこで、「自分のやりたかったことはこれではないのか」「この勉強をやり遂げて司法書士になれたのなら今までの人生を糧にして誰かの力になれるかもしれないのではないか」と思ったのがきっかけです。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
書店でオートマシリーズを揃えて独学し、初めて受験したとき、択一基準点を午前はクリア、午後は2問足りず、記述は手が回らなかったという結果でした。そこから「山本先生の本が自分に合っているんだ!」と思い、今よりも深く理解できるようになるためにきちんと講座を受けたいと思いTACを選びました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
TACで提案されている2か月で5回繰り返すという方法をベースにしていました。
配信スケジュールに合わせて講義を聴き、配付されていた学習計画表に書き込み、それに沿ってでるトコとテキストを5回復習していました。直前期はオートマ過去問10冊を24回に区切り(総ページ数約3600ページ、1回当たり約150ページ)同じように2か月で5回繰り返しました。
スケジュール帳にも復習日を転記し、終わったら可愛いスタンプを押していくことで進捗状況を可視化するとともに、今日もこれだけがんばったとモチベーションを上げていました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
択一式対策は、でるトコとオートマ過去問のみを使い、山本先生がおっしゃっていた「5回連続して正解するまで繰り返す」という方法をやっていました。苦手なところは「厳選 講義の急所総まとめ」でチェックし、その近辺も一緒に読み直して理解していきました。
記述式対策も講義に合わせてオートマ記述を同じように繰り返し、間違いノートで苦手部分を復習していました。ひな形は、ひな形集を書くことである程度覚え、記述式論点データベースで補強していきました。記述の本試験対策は配付された過去問5年分と模試の問題をコピーして繰り返しました。どのくらいの時間で解き終わるのかを意識し、どうしたら時間短縮できるのか試行錯誤しました。
択一、記述とも、どうしても間違える箇所は105×75のリーガルブロックメモに書き出して、何度も見直していました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
立て続けに両親の介護と看取りがあったために、予定通りに勉強していくことが時間的にも精神的にも難しかったです。「私に司法書士という立場があったならもっとスムーズに物事が進むだろうに…」と悔しいことも多かったので、その悔しさがやり遂げる原動力にもなりました。
どうしてもやる気になれないときは思い切って何もしない日を作り、頭を切り替えていました。
■TACの良かった点【講師】
山本先生が、現実にありそうな事例や実務での経験談を交えながら話してくださるので、講義を聴いているだけで理解が進みました。山本先生の講義を聴いているうちに、大学時代に受けた法律の概念的な講義の意味が分かってきて、歯車が噛み合ったような感じがして楽しかったです。
■TACの良かった点【教材】
講義の急所は、毎回の復習時から直前期までよく見返していました。「厳選 講義の急所総まとめ」は、あやふやなところを確認するために直前期の横断本として使っていました。
Webトレーニングはやる気が出ないときにもクイズ感覚でできたのでよかったです。
■TACの良かった点【カリキュラム】
独学で記述式のテキストをやっただけでは本試験問題の形式に慣れることができなかったため、講義の中で実際の本試験問題を使って丁寧に教えてくださったのがよかったです。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
受験生生活はとにかく孤独だったので、オンラインホームルームはなごみでした。質問メールにも丁寧にご回答くださって心強かったです。
オンライン口述模試で西垣先生に直接お礼を言うことができたときは感動しました。
■勉強以外の部分
愛犬と散歩したり遊んだりすることがリラックスでした。限定モデルやちょっとお高いペンを買い、今日はどれで勉強しようと選ぶことでモチベーションを上げていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
勉強し始めの頃は勉強方法を迷いましたが「川中島にならない!」を常に頭に置き、オートマで確実に知っている事柄を一つでも多く増やしていきました。山本先生、西垣先生を信じてオートマで「基礎の完成」をしていくことが合格への近道だと思います。
K.M さん 段階別の答練がモチベーションの維持につながった
2025年合格目標:答練本科生記述対策プラス

【主な受講講座】
●「答練本科生記述対策プラス」Web通信講座
●「上級総合本科生」Web通信講座
●「記述式過去問解説講座」Web通信講座
【受験回数】3回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】会社員
【得意科目】商法(会社法)・商業登記法 【不得意科目】民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・司法書士法・供託法・憲法
【1日の平均学習時間】5時間 【学習開始時からの総学習時間】4000時間~4500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
行政書士試験合格後、更に法務関連の資格試験に挑戦したいと思いました。
<学習時の環境>
一般企業から司法書士事務所に転職し、アシスタントとして働きながら勉強していました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
独学で勉強していた初期に会社法の勉強に課題を感じていた頃、姫野先生のYouTube上の会社法演習講座を通じて、会社法の成績を上げることができました。これをきっかけに、姫野先生が講師をされているTACの講座に興味を持ち、その翌年からTACの講座を受講しました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
上級総合本科生の頃は、講義で学んだ部分の過去問を解いて、インプットとアウトプットを交互に繰り返していました。TAC受講開始後の2年目は答練で得点することを目標に、毎週答練の範囲を復習して答練に臨むことを繰り返ししていました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
記述の配点変更があり、より重要性が高まったので記述式問題対策を重視しました。答練、記述式過去問集等を用いて、本番でどのような問題が出ても解答できる力を養うため、網羅的な演習を心掛けました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
令和6年度の不合格の主な原因は不動産登記法の記述式問題の点数が悪かった点でしたので、答練や、記述式過去問集、姫野先生が個人で著作した古い不動産登記法記述過去集や過去受けた模試の問題を数多く解くことで、本番でも通用する回答力を身につけることができました。
■TACの良かった点【講師】
解答時間が限られる中で、効率的且つ再現性の高い記述式の解法を教えてくださる点が姫野先生の魅力の1つであると思います。
■TACの良かった点【教材】
・上級総合本科生の択一式対策講座【実践編】の解説と問題がセットになっている教材
・記述式対策講座の問題集
・オプションの記述式過去問解説講座の過去問集及びその解説冊子
が良かったです。
■TACの良かった点【カリキュラム】
総合力底上げ答練から合格力完成答練までの各段階別に出題される答練のカリキュラムにより、長期戦となる司法書士試験の勉強においてモチベーションを維持しながら勉強することができました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
記述式過去問解説講座は、実際の本番の問題を記述式対策講座で学んだ解法を用いて解答する工程を学ぶことができ、本番におけるリアルな現場での解答のイメージを持つことに繋がりました。
■勉強以外の部分
時短料理を毎日作り自分自身を労わることで、長期戦となる司法書士試験の受験期を心身ともに健康で乗り切ることができました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
周りの受験生の成績や生活環境などとつい比べしまい、焦る場面が自分自身多かったので、自分にあったペースとやり方で一つ一つできることを増やしていき、それがいつしか合格に繋がることを願っています。
岡久 未央 さん 答練がペースメーカーになり学習サイクルを構築
2025年合格目標:答練本科生、記述式過去問解説講座

【主な受講講座】
●「答練本科生」Web通信講座
●「記述式過去問解説講座」Web通信講座
●「上級総合本科生」Web通信講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】自営業 【合格時(合格年の直前期)の職業】自営業
【得意科目】民法・不動産登記法・供託法 【不得意科目】商業登記法・憲法・刑法
【1日の平均学習時間】5時間 【学習開始時からの総学習時間】4000時間~4500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
父が司法書士で、子供の頃から司法書士という職業は身近な存在でした。大学進学時に司法書士になりたいと思い法学部に進学しましたが、その時は司法書士の勉強をする決心がつかず、卒業後10年以上経って、やはり司法書士になりたいと思い勉強を始めました。
<学習時の環境>
自営業で自宅兼職場、予約制の仕事ということもあり勉強時間は確保しやすかったです。仕事が入っていない時間は勉強に充てることができましたが、仕事の繁忙期には勉強時間があまり確保できず、両立の難しさを感じたことも多かったです。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
司法書士は非常に難関試験で科目数も多いため、まず独学は難しいだろうと思っていたので、最初から独学の選択肢はありませんでした。予備校を利用した方が独学より合格までも早くたどり着けるとも思いました。
<TACを選んだ理由>
一年目は他校の基礎講座を受講しており、本試験後に中上級講座の受講を検討していたときに個別相談で姫野先生からアドバイスをいただき、YouTubeの動画や体験講義を拝見してとても分かりやすかったことから受講を決めました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
仕事の日は3時間、休みの日は7~8時間の勉強時間でした。試験直前2週間は仕事を休み、1日10時間の勉強時間を確保しました。休みが固定ではないので、答練を受ける日をまず決めて、1週間ごとに予習・復習の学習スケジュールを立てていました。年内は予習を理論編テキスト+過去問、復習はあいまいな問題や間違えた問題を理論編テキストに戻って確認しました。年明けからの科目別答練では、出題科目に集中して予習・復習をしていました。年明けからは実践編テキストを反復していました。超直前期(6月、7月)は実践編テキストはそこそこに、パーフェクト過去問を回すことに重点を置きました。2024年の本試験で過去問知識で解ける問題を多く落としたことが一つの敗因になっていたからです。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
主要4科目は年内から過去問とテキストの反復学習をしていました。マイナー科目は民事訴訟法のみ年内に過去問を解きましたが、それ以外は年明けから過去問を解くことに重きを置いて、分からないところのみテキストに戻りました。
記述は、答練が始まるまでに2024年合格目標の記述式対策講座理論編を聞きなおし、解法と論点を再確認しました。答練では毎週解法の訓練ができ、力がついていくのを実感しました。3月からは『記述式過去問解説講座』を受講していたので、毎週、商登法・不登法の過去問各1、2問を解きました。答練は返却答案に、過去問は解答用紙に、間違えた箇所の訂正と間違えた理由を書いてストックしておき、超直前期(6月以降)に何度も見直しました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
日々の体調管理が難しかったです。仕事の繁忙期や試験のプレッシャーもあり、体調を大きく崩してしまったことが何度かありました。勉強しないと、と焦れば焦るほど悪化してなかなか体調が戻りませんでした。そのような時はまずは体調を整えることに専念し、仕事が忙しく勉強時間があまり確保できないときは最低限の勉強のみで落ち着いたら遅れを取り戻そう、と割り切るようにしました。
また、遅れが出たとき等は質問メールで姫野先生に学習計画の相談をしてアドバイスをいただくようにしていました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の講義は分かりやすいのはもちろん、とても楽しく、3時間の講義があっという間でした。講義のコマ数は多かったですが苦痛に感じることはありませんでした。また、記述式の解法はもちろん、択一式の解法も教えてくださるので、午後択一の時間短縮、正答率アップにもつながりました。
■TACの良かった点【教材】
まず理論編のテキストは網羅性が高く、このテキストを繰り返せば必ず合格できる、という安心感がありました。実践編のテキストは表などを用いてまとめられているので、知識が整理されていて記憶に残りやすく、回しやすかったです。
■TACの良かった点【カリキュラム】
上級総合本科生は年内の理論編で基礎を固め、実践編で重要なところを固めつつアウトプットも一緒にできてより知識が定着しやすかったです。
答練は良いペースメーカーとなり、出題範囲に沿って予習→答練→復習をこなすと全科目を満遍なく学習できるようになっていたのが良かったです。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
<各種答練・模試の活用方法や良かった点>
地方に住んでいますが、模試は必ず1,2回会場受験をするようにしていました。自宅受験とは違う緊張感があり、本試験と同じ解き方、お昼の過ごし方などのシュミレーションができたことで本試験も落ち着いて受けられたと思います。
<単科講座の活用方法や良かった点>
記述式過去問解説講座を受講しましたが、過去問を解くことで本試験レベルの問題に慣れることができてより記述式の力がついたと思います。また、過去問から同じ論点が出ることもあるのでその対策ができたことも良かったです。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
質問メールをよく利用させていただきました。知識で分からないところだけでなく、今何をすれば良いかなどの学習計画に迷った時にも相談もできて、姫野先生から直接アドバイスを頂けたのが良かったです。
■勉強以外の部分
友人と食事に行ったり、年に2,3回は旅行に出かけていました。また、勉強の合間に気分転換にウォーキングをしたりもしていました。旅行先にテキストを持って行くことはやめられませんでしたが…適度な息抜きはやはり必要だと思います!
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
この予備校、この講師のもとで勉強する、と決めたら、あとは疑わずに言われた通りに淡々と勉強をこなしていくことが一番の合格への近道だと思います。司法書士試験は諦めなければ必ず受かる試験だと思います。試験当日も最後の最後まで諦めないことが本当に大切です。頑張ってください!
加藤 健太 さん らせん階段を登るように実力がつくカリキュラム
2025年合格目標:答練本科生

【主な受講講座】
●「答練本科生」Web通信講座
●「上級総合本科生」DVD通信講座
【受験回数】8回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】会社員
【得意科目】商法(会社法)・商業登記法 【不得意科目】民法・刑法
【1日の平均学習時間】2時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
新卒で一般企業(インフラ系の会社)に就職し、営業部門の道を歩んでいました。しかしながら、自分に営業部門は合わないと思うようになり、もともと法律関係の仕事に興味があったことから、司法書士試験を目指すようになりました。
<学習時の環境>
上記の通り、私は一般企業で働きながらの勉強でしたが、ある程度勉強が進むと(択一で基準点を超えられるくらい)、法務部門で働くことも選択肢となり得ると考えるようになりました。そして、希望叶って法務部門へ異動となり、合格するまでの直近の約5年間は法務部門で働いていましたが、今考えると相応に相乗効果があったものと感じます(ちなみに、この間、自社の商業登記申請を担当させていただくこともありました)。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
勉強開始時は独学でしたが、午後の択一で基準点に届かないことが続いたことから限界を感じ、記述式対策含め午後科目の強化を目的に、受験指導校を探すことにしました。
<TACを選んだ理由>
まず、絶対的な知識量が足りていないと感じていたことから、まさに「オール・イン・ワン」の教材を誇る上級総合本科生(2022年合格目標)を受講し、その後、問題演習の必要性を痛感したことから答練本科生(2025年合格目標)を受講しました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
妻と二人の子供がいて家庭生活が充実していたこと、また上記の通り希望叶って法務部門で仕事ができていたことには満足していたことから、「仕事や家庭を犠牲にして」というスタイルではありませんでした。勉強を始めるのは、土日を含めて基本的に子供が夜寝てからで、勉強時間は平均して2時間/日程度だったと思います。結局、上級総合本科生(2022年合格目標)の講義・テキストを3年かけて習得し、その後に答練本科生(2025年合格目標)を受講しましたが、その際は答練をペースメーカーとして、空いた時間を上級総合本科生のテキストの復習に充てていました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
講義の内容や演習でつまずいた部分はテキストに書き込む(何かあれば、都度テキストに戻る)といったスタイルで勉強していました。また、午後科目の時間不足の原因は、つまるところ知識不足にあると考えたため、午後の択一式対策としては、瞬時に、かつ全肢検討をするまでもなく正解を選べるレベルの正確な知識を習得しようと心がけました。本試験の択一の平均点としては、午後より午前のほうが高い傾向ですが、やった分が成果として表れやすいのは午後択一のほうだと個人的には感じています。
記述式対策に関しては、姫野先生の解法の伝授を受けた上で、それを実践できるよう答練などで繰り返し演習するということに尽きるかと思います。ある程度のレベルに達すると、記述式対策の勉強は楽しくなるとおっしゃる方も多いですが、私もそのように思います。この点、択一式対策の勉強(特にインプットや知識のメンテナンス)に関しては、本番直前まで地味でつらい作業の繰り返しにならざるを得ないと思いますが、そこから逃げないというのが大切だと思います。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
仕事や家庭とのバランスを重視したスタイルとは言いつつも、子供も成長していくので夜寝る時間が徐々に遅くなっていく(ゆえに勉強時間が減っていく)ことに焦りを感じたり、受験回数を重ねることによりプレッシャー(私は8回目の受験での合格です)が大きくなっていくことはありました。
私の場合、最後の1年は模試の成績も安定してきていたことも救いでしたが、司法書士試験は他の難関試験と比べても努力が実りやすい(知識や経験のアドバンテージが活きやすい)試験だと考え、頑張り続ければ受かるときが絶対に来る!と自分に言い聞かせて、気持ちを落ち着かせていました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の記述式対策の解法を学ぶことができたこと、これに尽きると思います。令和7年度の記述式問題(特に商業登記法)は非常に難しく、これまでやってきたことが通用しなかったようにも感じました。しかしながら、ふたを開けてみればみんなできていなかったということのようで、すなわち、問題の傾向が変わろうが難易度が変わろうが、姫野先生の言うとおりにやっていれば、合格はできるということです。
■TACの良かった点【教材】
上級総合本科生のテキストには「オール・イン・ワン」の安心感があり、「自分が知らないことは、他の受験生も知らない」と思えるほどです。答練や模試の出題レベルも高いと思いますが、これに慣れることで、いわば「高地トレーニング」のような効果が得られた気もしており、本試験本番でも余裕が生まれたように感じます。
■TACの良かった点【カリキュラム】
私は答練本科生(2025年合格目標)でしたが、「総合力底上げ答練」「科目別全潰し答練」「合格力完成答練」という3ステップでは、まさにらせん階段を登るように、気がついたら自然と実力がついてきているというのを感じました。また、「科目別全潰し答練」では、マイナー科目も含めて集中的に問題を解くことになりますが、その時期に集中的に問題演習を行うことで、直前期のマイナー科目対策の負担も軽減されたように思います。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
よく、「TACの答練や模試は難しい」と言われるかと思います。しかも、なかなかA判定は出ません笑(上位5%くらいでも、Aがつかなかったような記憶があります)。「模試の結果は気にしないほうが良い」という意見もあると思いますが、私は、好成績を残すことを目標(モチベーション)にして、毎回の答練・模試を時間を真剣に受けていました。今振り返れば、なかなかA判定が出なかったところも、油断をしなくてよかったと感じます。
■勉強以外の部分
幼いころから水泳を続けているのですが、やはり、何より健康が大事ということで、週に1回のペースでプールで泳ぐようにしていました。勉強の集中力を保つためにも、適度な運動は非常に有効だと思います。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
私は、今も一般企業の法務部門で働いていますが、今後も働きながら、司法書士の仕事もしたい(登録をしたい)と考えています。また、合格後に各種の新人研修を受講されると感じられるかもしれませんが、司法書士の仕事は決して登記だけでなく、想像以上に幅広いものです。ぜひ、自分なりにやりたいことや目指す姿をイメージしながら、勉強に励んでいただきたいです。
M.S さん 答練の解説冊子が有用だった
2025年合格目標:答練本科生

【主な受講講座】
●「答練本科生」Web通信講座
●「上級総合本科生」Web通信講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】会社員
【得意科目】司法書士法・供託法・憲法 【不得意科目】商業登記法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】3時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
社会保険労務士に合格した時に、周囲から司法書士を目指すのか聞かれたことがきっかけです。また、父が亡くなったときのことを考え、相続する不動産の登記を自分でできるようになればと思ったことが一番の動機です。
<学習時の環境>
働きながら、自室で、講義に関しては通信での学習でした。幸い、仕事がさほど忙しくはならず、残業も少なく、家庭環境も落ち着いており、特に時間をとられるような行事関連もなかったので、安定した学習時間をとることができました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
以前、社会保険労務士資格を取る際に、TACの通信講座を受講して合格することができたので、多数ある科目を「見て、聴いて、読んで」といった学習スタイルで効率よく勉強できるという成功体験から、難関資格である司法書士も受験指導校主体を利用しようと決めました。
<TACを選んだ理由>
司法書士を受験する前に、TACで社会保険労務士、行政書士の講座を受講し、合格していました。そのため、講座の割引制度が使えることができ、また、これまでの経験からあまり他社を考えることなくTACを選びました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
平日は、夕食後~就寝までの約3時間を学習にあて、休日は午後と夜間に約7時間の学習時間をあてました。生活のリズムは、仕事と学習を中心に構築しました。前半では、講義を聴き、テキストの読み込みをした後に、過去問を解いていましたが、後半は過去問などの問題演習を中心に行いました。
記述対策としては、オートマシステムのひな型集を毎日少しずつ書いて覚え、こちらは何度も繰り返しました。また、講義音声をダウンロードし、携帯プレーヤーで通勤時間に何度も繰り返し聴いていました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
特に科目で異なった勉強法はしていません。どちらかといえば、令和7年度の学習では、過去問を中心とした問題演習に重点をおきました。過去問題集は3回転ほど行い、正解に至らなかったところは、基本テキストにマークや、書き込みを行い、さらに、間違った問題のみを繰り返し解きました。直前期には、択一式対策として、科目別全潰し答錬を中心に再度行いました。記述式対策の方は、答錬・模試の各問題を活用し、不動産登記なら「登記の目的」「登記の原因」を、商業登記ならば「登記すべき事項」のみを約1時間で書き出す練習を行いました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
昨年の本試験は、合格点に3点及ばず総合落ちでした。択一式の基準点発表後は記述式がそれなりにかけたので、自信を持っていました。そのため、筆記試験の合格発表で自分の受験番号なかったときは非常に落胆しました。実は、択一式で各肢の○×は合っていたのに、マークの選択肢を間違えたものが一つありました。また、考えすぎた結果、当初は正しい選択肢を選んでいたのに、誤ったものに変更した問題が2問もありました。
自分は合格基準を十分に満たしているという自信を持ち、余裕をもって学習を進められるように切り替えていきました。
■TACの良かった点【講師】
姫野寛之講師。記述式の問題解法、注意する点などが非常に参考になりました。ただ、不動産登記の記述式で登記識別番号を登記簿の順に番号まで指定しなければならない場合、特に第2申請などでは、その番号を間違えました。これは、姫野講師の申請リスト作成からだけでは、その後の登記順位が職権抹消などが入るとその順位が自分の頭の中だけでは整理できなかったからで、第1申請後の登記簿の状態を書いたりする必要があると思いました。
■TACの良かった点【教材】
上級総合本科の実践編テキストが特によかったです。過去問主体ですが、姫野講師自身が言及されているように、過去問だけでは足りない会社法、商業登記法、民訴3法、憲法の問題演習がたくさんできた点が良かったです。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
問題演習の総まとめとして活用しやすかったです。解説冊子のまとめ表などは、直前の知識確認として役立ち、自信のない所をコピーして持ち歩くなどしました。記述の添削指導に関しては、「よくできている」などと評価されると自信につながり意欲がわいてきました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
デジタル教材が提供されており、かさばるテキストを持ち歩かずに気軽にタブレットなどで外出の際に持ち出すことができたのが良かったです。
■勉強以外の部分
基本的には、通信での学習ということもあり、一人で受験勉強を続けてきました。そのため、仕事、受験勉強を中心とした生活を繰り返してきました。休みの日も午後3時くらいからは勉強時間にあてるなど、だいたいの予定を立て、それまでに家事などを行うなど、犠牲にしてきたところもかなりありました。今後は、姫野講師も言っていましたが、人間力の回復に努めたいところです。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
まずは1日、1週間の大まかなスケジュールを組み立て、それに沿って行動して学習時間を慣習化させてください。進められる学習量などが大体わかれば、やむを得ず勉強できなっかたときのフォローもできるようになると思います。よく言われますが、何よりも、日々の積み重ねが力となるのですから。
大久保 真行 さん オートマと答練で暗記ではなく理解しながら学習
2025年合格目標:4月答練パック

【主な受講講座】
●「4月答練パック」教室講座
【受験回数】2回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・商法(会社法)・民事訴訟法・憲法・刑法 【不得意科目】民事執行法・供託法
【1日の平均学習時間】8時間 【学習開始時からの総学習時間】3000時間~3500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
平成23年に終了した旧司法試験にチャレンジしていた方は、会社勤めをしながら法律家となる夢を心の奥に隠し持つ一方で、自身の法律知識を活かして税理士等との連携、金融機関との折衝、ガバナンス構築などに携わっているかもしれません。わたしもそうした会社員の一人で、58歳で会社都合退職を余儀なくされたとき、司法書士試験のチャレンジを決意しました。
<学習時の環境>
旧司法試験にチャレンジした当時に存在しなかったタブレットやスマホは当面のところ必要なく、必要なのは、狭い納戸で構わないから集中できる一部屋です。勉学に専念できることについて、家族への感謝を忘れないでください。そうでないと点数が伸び悩んだ時に「今年落ちたらどうするの!」攻撃が襲います。やや面倒ですが、失業給付金の申請も忘れずに。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
退職後半年で挑んだ1回目の受験結果は、午前25(基準点26)・午後19(基準点24)でした。択一基準点未達にもかかわらず、わたしは、主要4科目+民訴法のインプットにはおそらく問題はなく、午後の部の時間短縮が課題と分析しました(根拠のない自信)。そこで、わたしは、実力チェック・合格力完成・公開という3種の答練・模試について受験指導校を活用することにしました。
<TACを選んだ理由>
旧司法試験チャレンジ組の中には、TAC出身者はもちろんL社、Ⅰ塾、T所と所縁が深い方などがいます。わたし自身は、L社の出身ですが、答練パック受講の目的はあくまでも午後の部の時間短縮だったので、姫野講師の解説動画視聴が決め手となりTACの4月答練パックを選択しました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
旧司法試験チャレンジ組なら、記憶に走ることの危険性と理解納得中心の学習の重要性という経験知があります。わたしのDNAの中にも理解中心学習が刻まれてますので、オートマを色分けしながら読み進める方法を採りました。色分けは「問題の所在(緑色)」「理由・根拠・制度趣旨(橙色)」「記憶すべき知識(黄色)」「学習指針等(青色)」の4色で、読むスピードが速くなることを目標に通読を繰り返しました。暗記はしません。それよりも制度趣旨を理解納得するのを優先しました。ご存じのように山本講師も「覚えようとしないのに覚えてしまう」勉強法の提唱者です。
学習スケジュールは、10~12月はインプット、1月からアウトプットを増やし、4月から答練を加えるというノーマルなもので足り、奇策を弄するのはやめましょう(笑)。適宜のタイミングで条文素読の日を作ると点数アップします。わたしは答練前日や直前期ほど条文素読を取り入れました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
旧司法試験チャレンジ組は、科目間のメリハリをはっきりさせることが可能でしょう。たとえば、民法、会社法、民訴法は条文素読しながら副読本を参照するだけで何とかなるかもしれません。憲法と刑法もテキスト不要です。
こうして時間を節約して、記述式対策に注力するのは楽しみでもあります(ホントです)。ここで思い起こしてほしいのは、旧司法試験で論証ブロック・論証パターンを暗記して失敗したという黒歴史…(個人の感想です)。重要なのは考える勉強をすることです。自力で回答する前に解答解法を見るのが危険だということは、今年の本試験記述式不登法をみれば、自明です。普段から考える勉強をしてないのに本試験当日だけ考える自分に変身するのは、わたしには無理です。本試験前日まで、この考える勉強を続けました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
肝心の記述式で焦ってしまいボロボロになっていました。本試験の答案用紙を前にしただけで慌てるという悪癖を治すため、記述式過去問演習では、答案用紙を本番と同じA3に毎回プリントアウトして、本試験用のペンで回答することを徹底しました。ペンは、姫野講師の全検証動画で優勝したモノです。
「記述式間違いノート」には、答練・模試だけでなく記述式演習で「やっちまった」ミスを漏らさず記入。ジャンル分けをせずに、とにかく記入しました。このノートが徐々に点数アップにつながりました(もっとも本試験の記述式商登法ではミスを連発しました。それでも合格はできる。以上)。
■TACの良かった点【講師】
姫野講師の記述式解法は、相性の良し悪しはともかく、再現性が高く実践的な解法です。わたしは姫野解法とは全く異なる自己流の解法でしたが(姫野解法でも時間不足を補えないわたしが悪い)、比較対照することにより、自身の解法が安定しました。もしも姫野講師の解法に触れなかったら、受験期間が延びていたと感じています。
■TACの良かった点【教材】
・オートマ不登法・商登法
テキストを読み進める理解中心の学習法に向いていると感じます。たしかに見出し・項目・段落分け・改頁などは完璧に整理されていない印象を受けますが、この未完成のサブノート的な性格を利用して「自分だけの一冊」を創ることが可能です。
・オートマ記述式問題集
山本講師のオリジナル作問はどれを取っても「考える勉強」になり、全問題と取り組みました。これを直前まで活用して、今年の本試験記述式不登法に対応できました。的中とか短絡的なことではなく、現場で考える力が身に付きました。
・記述式パーフェクト過去問集
他社の過去問集を購入したのだが直近10年分しか改正対応されていないこと及びそれだけでは足りないことを姫野講師の動画で拝聴し、パーフェクト過去問集を急ぎ購入し即日演習開始しました。やはり全問題に取り組みました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
実力チェック模試・合格力完成答練・公開模試はセットになっている4月答練パックを受講しました。答練は、全6回でしたが、必要十分でした。とくに不登法で考えさせる良問が出題され、解き直したことが令和7年度本試験対策として役に立ちました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
「答練や模試の成績は本試験の結果とは無関係」という慰めには耳を貸さず、答練・模試の成績には拘泥しました。旧司法試験論文式とは異なり、司法書士試験記述式には「正解」があります。正解のある問題を模試で解けないのに、本試験で解けるはずはないと考えました。
この点、TACの成績表は返却が早く、一喜一憂するのも時間差がなくて良いです(笑)。TACの添削答案および成績表のアップロード期日は他社より早いだけでなく、実際の運用では更に一日早く閲覧可能でした。TACのスタッフ陣のご努力に感謝します。
■勉強以外の部分
直前期特有の焦りに襲われたとき、「今の自分」と区別された「当日の自分」をイメージし、後者により強くなるためのアイテムを供給するのが「今の自分」のミッションなのだと考えました。似たような内容をボクシングの井上尚弥選手、大リーグの大谷翔平選手も口にしたことがあり、姫野講師も「答案構成している自分」と「それを筆記している自分」を分けて考えています。わたしは、このロールプレイングゲームをしている感覚で淡々と直前期を過ごすことができました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
大リーグの大谷翔平選手や佐々木朗希選手が「メンタル面を含めて技術の範囲内である」みたいなことを言っているのを聞いたことがあります。技術(学力)が上がれば、仮にメンタルが落ち込んでいるコンディションでも必要な得点力を維持できるという意味だとわたしは解釈しています。他方では、司法書士試験の12科目目は精神面テストだと主張している受験指導校もあるようですが、そのような情報には耳を貸さずとも、技術(学力)の向上だけで勝ち抜ける試験です。
新谷 隆紘 さん 姫野講師の記述解法にもっと早く出会いたかった
2025年合格目標:4月答練パック

【主な受講講座】
●「4月答練パック」資料通信講座
●「答練本科生記述対策プラス」Web通信講座
●「山本オートマチック<1.5年本科生>」Web通信講座
【受験回数】3回
【学習開始時の職業】学生 【合格時(合格年の直前期)の職業】受験専念
【得意科目】民法・不動産登記法・商法(会社法) 【不得意科目】商業登記法
【1日の平均学習時間】7時間 【学習開始時からの総学習時間】3500時間~4000時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
親戚に司法書士がいたこともあり、その親戚と同じ資格を持って一緒に働きたいという気持ちから、司法書士を目指し始めました。その中で、本格的に勉強を始めたのはコロナで大学が休校になった大学2回生の冬頃でした。
<学習時の環境>
大学生という事もあり、本来は学業との両立が難しいと考えられますが、運よくコロナの時期と重なりましたので、比較的司法書士の勉強に専念することができる環境だったと思います。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
公認会計士を目指す友人のアドバイスで、難関資格の取得は独学では厳しいとのことだったので、予備校に通うことに致しました。
<TACを選んだ理由>
やはり山本先生のオートマテキストが他の参考書と比べて格段に分かりやすかったからです。法律を初めて学ぶ人でも抵抗なく、かつ平易な言葉で説明してくださるため、とてもおすすめです。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
学習スタイルは、とにかく過去問を回しました。学習はそれに尽きると思います。スケジュールは、初学者の時期は、基礎を固めるための講義視聴と問題演習を交互に行い、定期的に模試や過去問を組み込む形にしました。大学の講義等もありましたので、1日平均5時間を目安として学習に取り組んでいました。合格年度の勉強方法は上記にも記載した通りに、とにかく過去問を回しました。また、勉強ばかりではなく、旅行や友人と遊びに行くなどメリハリをつけて学習していました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
民法は基本的な理解を深めることに重点を置き、具体例を交えて覚えることで実践的な対応力をつけました。不動産登記法は手続きの流れを図式化して理解し、書式問題を繰り返し解くことで実践力を高めました。商業登記法については、姫野先生のYouTube動画を視聴して理解を深めました。マイナー科目は、必要であれば他の予備校の講義を取り入れるなどしていました。記述式対策としては、姫野先生の記述式対策講座を活用し、実際の問題に近い練習を重ねました。これもとにかく過去問をベースに学習し、答練などは間違えたポイントを徹底的に潰すような活用方法を採っていました。学習全体を通しては、繰り返しの復習と理解が曖昧な部分の見直しを重視しました。試験本番で動じないように、試験のシミュレーションも定期的に行い、心構えを整えることも重要視しました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
姫野先生の記述式の解法にもっと早く出会うことができれば良かったなと感じています。やはり記述式試験は、散漫する情報をいかに正確に読み取ることが出来るかにかかっていると思います。そんな中で、私は、闇雲に学習を進めて、いたずらに時間を浪費してしまいました。記述式の勉強こそ、しっかり型を確立して学習を進めていくべきであると思います。
■TACの良かった点【講師】
TACの長所といえば、その講師陣の層の厚さにあると思います。山本先生や姫野先生を始めとした信頼のおける講師陣にすべてを任せ、その通りに学習を進めていけば、必ず合格できます。
■TACの良かった点【教材】
山本オートマチックの理解のしやすさは、他の教材の追随を許さない程であると感じます。初学者が学習を進めるには、まずはオートマから入るのが鉄則かと思います。
■TACの良かった点【カリキュラム】
TACのカリキュラムは、主要科目を学習した後に記述式の学習を行います。そうすることで、記述式の学習を進めながらも択一の復習が出来るカリキュラムになっており、その点が非常に良かったと感じています。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
答練の解説講座では、復習のみならず、姫野先生の確立した記述式の解法を学ぶことができます。その中で、実際に答練の問題を使用した解法の説明を行ってくれるため、より実戦形式で解法を学ぶことができました。また、模試は会場受験にすることで本番さながらの緊張感を味わうことができました。自宅受験では養うことのできない試験慣れの側面を大事にできた点は凄く良かったと感じています。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
講師に24時間質問できるという環境はとても贅沢なものであったなと感じています。疑問は疑問が生まれたその瞬間に質問することが大切ですので、そのようなフォロー体制があった事が良かったです。
■勉強以外の部分
勉強以外の時間は、基本的には遊んでいました。家族や友人を始めとした、応援してくれている人と過ごす時間はやはり大切にするべきであると思います。メリハリを持って学習に取り組まないと行き詰まってしまいます。遊ぶときはしっかり遊び、勉強する時は集中して勉強するようにしていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
この試験は、天才が受かる試験ではありません。長い時間血反吐を吐くような努力をし、継続に継続を重ねた人間が合格する試験です。逆に言えば誰でも合格の可能性を、自分の頑張り一つで人生を変える可能性を持てる試験です。合格して人生を変えましょう。私は人生変わりました。
C.O さん 家事・育児&働きながら時間をやりくり
2025年合格目標:記述式対策講座、予想論点セット他

【主な受講講座】
●「記述式対策講座」Web通信講座
●「予想論点セット」オンラインライブ講座
●「午後択一式タイムトレーニング」Web通信講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】会社員 【合格時(合格年の直前期)の職業】会社員
【得意科目】民法・不動産登記法 【不得意科目】憲法・刑法
【1日の平均学習時間】4時間 【学習開始時からの総学習時間】3000時間~3500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
行政書士試験合格後、知識を更に深めたかったので司法書士試験を受験しようと思いました。法律を扱う仕事のため、仕事にも実際に知識が活かされるのも勉強を始めたことの動機の一つです。
<学習時の環境>
フルタイムで働きながら、5人家族プラス飼い犬暮らしのリビングで勉強することが多かったので、集中することと勉強時間を作ることが何よりも大変でした。どうしても集中したい時は図書館へ出向き、多くの人が黙々と勉強している環境に身を置いて頑張りました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
独学ではポイントを掴むまでに時間がかかるので、今年を最後の受験したくて受験指導校を利用しました。
<TACを選んだ理由>
マークシートで安定して点数が取れるようになり、あとは記述で得点を増やしたいと思ったため、姫野先生の記述式対策講座を選びました。先生のYouTubeで「記述は僕にお任せを!」と言っていたので、それを迷わず信じて受講しました。解法を持ちたいと思っていたので、まさにバッチリ合った感じでした。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
通勤電車を各駅に変えて電車の中で勉強していました。電車はあえて各駅停車に乗り、到着するまでに何をやるかを毎朝決めて乗り込みました。仕事の休憩時間も全て勉強に使い、朝は料理をしながら姫野先生の講義の音声を聴いていました。休みの日は終日図書館に籠り、集中できる環境を作り、とにかく生活に必要な時間以外はすべて勉強に使うよう意識していました。年明けからは過去問を多く解くことに集中できるようにしていきました。また、直前期では特に午後の部については早く解く練習を意識しながら対策しました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
民法はコンスタントに復習を重ね、商法会社法は紛らわしいポイントを整理することに時間をかけました。不動産登記法は過去問をひたすら回すことで知識と理解を深め、かなり細かい点まで押さえました。商業登記法は商法会社法と同時に進めました。民訴系は自分で流れを図にしてみると体系的に頭に入りやすいことに気付き、それぞれおおまかな流れの図を作りました。そこに細かく書き込む感じで仕上げたのですが、私にはかなり効果的でした。その他の科目はテキストを何回も読みながら過去問を解きました。記述対策は記述式対策講座の中で姫野先生に言われた通りに進めていきました。解法が身についてからは早く確実に解けるようになっていきました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
フルタイムで仕事をし、朝のお弁当作りから夕食まで5人分の食事を用意し、その他の家事もほぼ全てこなしていたため、勉強時間の捻出と睡眠時間をきちんと取ることが日々の課題でした。乗り越えた方法としましては、常に勉強する意識を持ち、1分でも多く勉強に使うようにしました。そのように過ごして1ヶ月ほど経過した頃に急に成績が伸びて来たような感覚がありました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の講義は、毎回目から鱗が落ちるかのように分かりやすく、とてもインパクトがありました。気をつけるべきポイント、絶対に覚えなくてはいけないポイントが明確で、効率よく勉強を進めることができました。
■TACの良かった点【教材】
テキストの大きさがよかったです。書き込みもでき、網羅的に記載されているので何度も復習するのにとてもありがたかったです。小さめの教材が多い中、読みやすく分かりやすく、よかったです。
■TACの良かった点【カリキュラム】
記述式対策講座だけでもかなりのボリュームがありましたが、直前までに自分のものにできるだけの時間もありました。記述式対策講座は姫野先生の進め方がとても分かりやすくて頭にどんどん入っていきました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
直前対策講座と午後のための対策講座も受講しました。どちらもポイントが明確で絞られており、全てが本番で役に立ちました。受講していなかったら危なかったと思います。本当に感謝しております。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
通学出来なかったため、メールで質問できるシステムにとても救われました。丁寧にお返事をいただき、このシステムが無かったら大きな誤解をしていたこともあったので、本当に感謝しています。
■勉強以外の部分
娘が大学受験生なので一緒に受験勉強をする日々でした。お互いに励まし合いながら難関の試験に向けて頑張った時間は財産となっています。家族に支えられながら頑張った直前期でした。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
登り始めはキツくて挫折しそうになりますが、一度全体を見渡せる場所に到達すると、そこからどう進めれば良いのか、何が足りないのかが見えて来ます。そこからが楽しいのでまずはそこを目指して頑張ってみてください!
K.H さん 子育てと両立しながら勉強時間を捻出
2025年合格目標:記述式対策講座

【主な受講講座】
●「記述式対策講座」Web通信講座
●「山本オートマチック<1年本科生>」Web通信講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】その他 【合格時(合格年の直前期)の職業】その他
【得意科目】不動産登記法 【不得意科目】商法(会社法)・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・供託法
【1日の平均学習時間】5時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
過去に司法書士法人の補助者経験があり、法学部出身でもなく未経験だったので、曖昧な知識だとお客様の問題を解決できず、不甲斐なさを感じる場面が多くありました。そこで、きちんと法律の知識を身に着けたいと思うようになりました。
上の子が10ヶ月の時に本格的に勉強を始め、妊娠・出産・2人の子育てと並行した受験生活でした。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
限られた時間の中で勉強方法に迷いたくなかったので、受験指導校を利用しない選択肢はありませんでした。
<TACを選んだ理由>
3回の受験で択一は自信があったのですが、記述で伸び悩んでいました。そこで姫野先生の個別相談を利用し、落ち込んでやる気をなくしていた私の背中を押してもらいました。先生はご自身の講座を推すわけでもなくあくまでも自分にあった方法で、と仰っており「この先生なら信頼できる」と思い受講を決めました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
平日の日中は、保育園の一時保育と義母にお願いして子どもを見てもらうことで勉強時間を捻出してました。それでも子どもの体調不良など、思うように預けられない日も多かったため、朝4時に起きて、子が寝ている静かな時間に集中して取り組む朝型が私にはあっていました。その日思うように勉強時間が捻出できなくても、最低限の勉強は朝済ませてるという安心感、モチベーション維持に繋がりました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
択一式では、民事訴訟法が苦手でした。超直前期はほぼ毎日テキストを読み、本試験までに3周させました。すると覚えにくいところも記憶を維持でき得点も安定するようになりました。
記述式は、姫野先生が言うノルマを必ず消化することを徹底していました(特に過去問演習)。この先生についていけば大丈夫という安心感があったので、遅れたときは記述式を最優先に時間を割き追いつくようにしました。記述式は解き方が人によって千差万別ですが、研究し尽くされた姫野先生の解法に素直に乗っかれば間違いないです!
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
可愛い盛りの子どもとの時間を割いて、勉強に充てることに何度葛藤したかわかりません。それでも、ここで諦めたら一生悔いの残る経験になってしまう、それだけはしたくないと自分を奮い立たせてきました。子どもとのお出かけには隙間時間で見れるようにテキスト等を持ち歩いていましたし、常に頭の片隅には「勉強しなきゃ」という思いがあり勉強を忘れて何かに没頭するということができなかったのは辛かったです。
■TACの良かった点【講師】
時々関西弁で冗談を言ってクスリと笑わせてくれながらも、常にテキストよりプラスαの知識を記憶しやすい方法で教えていただいて、とても密度の濃い授業でした。最初はついていくのは大変ですが、段々と並走できるようになると自分の知識がついてきたのを実感できます。
■TACの良かった点【教材】
実践編→実践総合編というように段階を踏んで解く問題のボリュームが大きくなるので、無理なく解法を身につけられました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
択一式などの他の勉強も並行して進められる余裕のあるカリキュラムだった点が良かったです。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
姫野先生の記述式講座ほど、細やかに解法を教えてくれる講座はないのではないかと思います。択一の知識は足りているのに、解法が確立してないために記述で伸び悩んでる全ての方におすすめしたいです。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
少しでも疑問に思ったら質問メールを利用していました。今の時代ネットで調べたら出てくることも多いですが、思うような答えがヒットしないこともあり、そこに時間を費やすのは勿体無いと思っていたのでとても助かりました。
■勉強以外の部分
私の場合は、子どもと過ごす時間が息抜きになっていました。いつも頭の片隅には勉強があったので、早く全力で子どもと向き合って存分に遊んであげたい!という気持ちを勉強へのモチベーションに繋げていました。
それでもやる気が出ない日は、思い切って家族で遠出をして勉強をほぼしない日もつくっていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
生半可な気持ちでは合格できない試験ですが、努力し続ければ必ず光は差します!私も何度諦めようと思ったか分かりませんが、番号を見つけた瞬間全てが報われたような気がして涙が止まりませんでした。応援してくれる周りへの感謝を忘れずに、どうか走り続けて下さい。一緒に司法書士になりましょう!
塩野 浩之 さん 姫野解法でどんな問題にも対応
2025年合格目標:記述式対策講座

【主な受講講座】
●「記述式対策講座」Web通信講座
【受験回数】4回
【学習開始時の職業】公務員 【合格時(合格年の直前期)の職業】公務員
【得意科目】民法・不動産登記法 【不得意科目】供託法
【1日の平均学習時間】3時間 【学習開始時からの総学習時間】3000時間~3500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
<司法書士受験のきっかけ・動機>
元々学生時代に受験を検討していた時期があったこと、普段の仕事の中で士業の方と連携することが多く、自分も専門的な知識を身に付けたいという思いで勉強を始めました。
<学習時の環境>
普段はフルタイムで勤務しており、子どもも小さいため、仕事と育児を両立させながらの受験生活でした。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
昨年度までほぼ独学で勉強しておりましたが、記述式の得点をあまり伸ばせず、苦手意識がありました。
合格のためには記述式の対策が必要と感じ、講座を探していたところ、姫野先生の評判が高く、また積極的にYouTubeでも情報発信されていたため受講を決めました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
平日は仕事があるので、通勤時間、昼休みの時間を勉強に充てていました。夜は、家事を少し進めて勉強して、また家事に戻って…を繰り返し、家族が寝た後に再度勉強を再開する、といったリズムで、とにかく家事の合間、細切れの時間を使うことを意識していました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
択一はとにかく過去問を重視し、平日は主要4科目を中心に、平日の隙間時間や週末はマイナー科目の過去問にも触れるようにしていました。主要4科目といっても、例えば民法だけで総則、物権、債権、親族と範囲が広いため、頭から順番に解くだけでなく、1科目の中でも色々な分野を少しずつ区切って広く触れ続けるという意識を持って勉強しました。
また、姫野先生より「記述式は任せてください。皆さんは択一に集中してください。」とのお言葉があったので、記述式のことは講座にお任せし、択一式に集中することができました。具体的には、オートマ過去問と出るトコを徹底的に潰し、解説まで覚えるつもりで対策しました。細切れの時間で勉強するスタイルのため、一問一答式である同書が自分には合っていたと思います。
記述式対策は姫野先生に指定された問題を解き、直前期は15年分くらいの過去問を解くなどしていました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
試験範囲が膨大であり、進んでは忘れての繰り返しで「忘れたまま進んで良いのか?」という葛藤が常にありました。
また、最初のうちは、前回正解した問題を間違えることも多く、精神的にきつかったです。次第に記憶が定着してきたからは大丈夫でしたが、「忘れるのは当然」というある種開き直りのマインドで取り組むことが大切と思います。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の講座はまさに「解法を授ける」といった内容で、どんな問題が出題されたとしても、淡々と同じ工程を踏むことで対応できるものとなっており、とても良かったです。
■TACの良かった点【教材】
講座動画をダウンロードできるため、通勤時間が主な勉強時間帯であった私にとっては非常にありがたかったです。また、速度調整もできるため、限られた時間を有効に使うことができました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
記述式に関しては、とにかく講座に出てくるものを素直に順番に解くことで力が付く構成になっていると思います。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
ひな型の書き方など、参考書によって若干異なる表現をしているものがあったため、その点をお聞きすることができました。実際に予備校に通っていたわけではなく、相談できる人もいなかったため、とても助かりました。
■勉強以外の部分
仕事をしていたこと、家族がいたことが自分にとっては良かったです。勉強だけでは気持ちも塞がってしまいますし、仕事があり、家庭があるという状況の方が「時間を有効に使おう」という気持ちが強くなり、無駄を省けたと思います。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
合格のためには難しい知識の習得というよりは、基本的な事項を落とさないことの方が何倍も大事であり、覚えるべきは基本的な事項に限られると思います(そうは言っても量は膨大ですが・・)。
ただ、司法書士試験は相対評価の試験であり、とにかく1問の重みが大きく、「何となく知っている」程度の知識で肢を切ると即座に失点に繋がるため、そこが怖いところです。とにかく反復あるのみです。頑張ってください。
J.E さん 姫野講師の記述解法で苦手克服
2025年合格目標:予想論点セット

【主な受講講座】
●「予想論点セット」オンラインライブ通信講座
●「記述式対策講座」Web通信講座
【受験回数】2回
【学習開始時の職業】受験専念 【合格時(合格年の直前期)の職業】アルバイト・パート
【得意科目】民法
【不得意科目】商業登記法・民事訴訟法・民事保全法・民事執行法
【1日の平均学習時間】4時間 【学習開始時からの総学習時間】2000時間~2500時間
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
一般事務に近い経理事務に長く従事していましたが、会計分野の仕事がそれほど好きではなく、知識をつけていこうとすることもなく毎日すごしていることに、なんとなく不安を感じていました。方向転換できるきっかけを探していましたが、年齢も上がっていく中で、未経験での転職は資格でも取らないと難しいだろうと考え、その中でも法律分野に興味があったことから司法書士を目指し始めました。ただ、科目数が多く、講座受講だけでもかなりの時間を要することが分かり、思い切ってそれまで勤めていた会社を辞め、一年の期限を決めて勉強に専念することにしました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
<独学でなく受験指導校を利用することに決めた理由>
まず、科目数が多く、範囲も広いので自分で教材を選んでテキストを読むより、予備校の用意したカリキュラムにある程度委ねたほうが良いと思いました。実際、私の場合は独学では合格は無理だったと思います。
<TACを選んだ理由>
受験初年度の冬頃に記述式対策が全くできておらず、どうにかしないといけないと考えていたところ、記述対策に定評のある姫野先生の講座の存在を知ったからです。あの長い問題の読み方すら分からなかったところ、解法手順から教えてもらえるところが良かったです。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
初年度は受験に専念していましたが、一日時間があるといっても集中できる時間は限られているので、あまり勉強時間は目標にせず、講座を見るスケジュールや問題を解く量などだけは決めて、それをなるべく守るようにしていました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
択一は基礎のインプットが終わってからは過去問を何度もやることで模試なども解けるようになったように思います。民法、会社法、登記法などメイン科目は何度も解くので、自然と身についていく感じがしましたが、マイナー科目はあまり時間をかけない分、理解が薄く、特に民事訴訟・保全・執行法が苦手でした。それは最後まであまり解消はできなかったですが、根本的な理解ができなくても、ある程度割り切って試験対策においての重要性のバランスを測りながら取り組むようにしていました。
また、私にとっては記述が一番対策が難しかったので色々試行錯誤しました。1年目は、記述の基準点に数点足りていなかったので、2年目は本試験の問題形式に慣れるため記述の過去問を複数回解きました。ひな型も覚えなければ素早く書くことができないので、とても面倒に感じましたが、Excelで一覧を作るなどして、少しずつ覚えました。記述式対策講座では、解法、引っかけのポイント、午後の時間対策など様々なことを教えてもらうことができ、そこで得た情報量はとても多かったです。結果的には1年目は不合格となりましたが、2年目は苦手だった記述に助けられるような形で合格することができました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
午後の時間が足りずに書ききれないということが、どうしたらよいか悩みました。速く解こうとすると焦ったり読み違えたりして、点数が落ちてしまうと感じていました。それについては、最後まで時間は足りないままでしたが、解く順序を不動産登記記述→択一→商業登記記述に変え、択一は午後のみ全肢検討をやめて組合せで解く方法に変えました。これも姫野先生が言われていたやりかたです。それにより、ギリギリ各1時間ずつにおさめることができるようになりました。あとは、模試などで毎回その方法で練習をしました。
■TACの良かった点【講師】
姫野先生の記述式対策講座は、記述が苦手な人でもこのやり方なら解けるようになるということを教えてもらえました。話を聞いていると問題作成者の意図のようなものがイメージできるようになったことが、問題を解く上でとても役立ったと思います。
■TACの良かった点【教材】
教材は表などで要点がきれいにまとめられています。また、過去問ででたことがある論点が網羅されているため、ボリュームがあり全て消化しようと思うと大変ですが、講師が重要だと言っている箇所だけを重点的に読んだり、解いたりするだけでも十分効果があったと思います。
■TACの良かった点【カリキュラム】
記述式対策講座は講義回数はそれほど多くはないため、択一式の対策と並行して進められる点が良かったです。開講時期もちょうど択一の基礎のインプットが終わる頃になるので、記述の勉強を本格的に始めるのに適していました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
記述式対策講座では、上述したように、解法など記述を解く上での基礎を身につけることができました。
また、択一のほうも、全てに対して全力でやる時間がないように思ったため、予想論点セットを追加で申し込み、受講しました。出題間隔などを自分で分析する労力を考えると、教えてもらったほうが効率よく、直前期に的を絞って対策をすることができて良かったです。マイナー科目も含めて、広めの範囲で予想論点を提示してもらえるため安心感がありました。
■勉強以外の部分
初年度は勉強に専念していましたが、2年目からは司法書士事務所でパート勤務をしていました。仕事をする中でも日々関連知識に触れられたこと、私にとっては試験にもプラスになったと思います。また、勉強ばかりだと嫌になり効率が落ちた時もあるため、時には数日間勉強から離れて休むようにしていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
受験をする上での環境や勉強のスタイルは人それぞれだと思いますが、色々調べて、合いそうな教材や講師の先生を見つけることができると、効率や時間の使い方がかなり変わってくるのではないかと思います。最近は配信などでお試し受講などもあるので、色々見てみた上で、合いそうなものを見つけられると良いなと思います。
Y.M さん 働きながら再挑戦 姫野解法で記述攻略
2025年合格目標:全国模試4回フルセット

【主な受講講座】
●「全国模試4回フルセット」会場受験
●「記述式対策講座」Web通信講座
【受験回数】10回以上
【学習開始時の職業】学生 【合格時(合格年の直前期)の職業】会社員
【得意科目】商法(会社法) 【不得意科目】民法・不動産登記法・民事訴訟法
【1日の平均学習時間】3時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
将来、法律にかかわる仕事がしたいと思っていました。大学に資格取得講座があり、司法書士という資格があることを知り、司法試験は無理そうだけど司法書士なら受かりそうという安易な考えで学習を始めました。
大学4年から学習を始め、その後新卒で就職しましたが、なかなか全科目をまわすことができず、3年後に退職して専業受験生になりました。しかし数年頑張りましたが合格には至らず、一度受験から完全に撤退し、10年後に働きながら勉強を再開しまして4回目で合格することができました。(以下、勉強再開後について書かせていただきます。)
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
以前勉強していたので司法書士試験の難しさは理解していますし、独学は自分と合わないと思っていたので、他校の基礎講座を通信講座で受講しました。その通信講座では記述対策がなかったので、市販されている本を使い独学で記述式対策を行っていたのですが、苦手な不登法の点数が安定せず「枠ずれする」「事実関係を整理できない」「時間が足りない」等多くの問題を抱えていました。このままでは基準点を越えられないと思い、解法を習得したいと思って受験指導校を利用することをしました。
姫野先生の記述式対策講座がわかりやすいと口コミをSNS上で拝見し、解法を教えてくれる、ただの問題演習で終わらない、理論編があり択一にも役に立ちそうという点が決め手となり受講を決めました。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
<学習スタイル・スケジュール>
平日は仕事があるため多くて3時間、休日は5~6時間、週に21時間勉強することを目標にしました。出勤前と通勤時間中(電車&徒歩)は必ず勉強するようにして習慣づけていきました。出勤前は前日の続きを、電車に乗っているときは、まとめ本やアプリで一問一答の問題演習、歩いているときは、暗記したことを唱えていました。帰宅してからは疲れて勉強できないことが多々ありましたが、勉強できたらラッキーくらいに思って自分で自分を追い込みすぎないことを重視しました。
若い時のように集中力が続かないので、25分勉強5分休憩を1セットにして、やる気を低下させないように工夫しました。
<科目別勉強法、学習時に重視したポイント、記述式対策>
択一:全科目基礎をキチンと覚えていれば全肢わからなくても得点できると思っていたので、基礎講座終了後はテキストで内容を確認したら、「まとめ本で論点を整理」⇒「でるトコで基本固め」⇒「過去問を解く」ことを1セットとして合格まで毎年5周はしていました。答練は一度も受講したことがなく、この方法で3年連続基準点+10問以上とることができたので、この方法は間違っていなかったと思います。
記述:記述式対策講座を受講した年は、講義についていくだけ精一杯で商登法は総合実践編の問題は全部こなせず、解法も完璧にすることができませんでした。翌年は、解法のブラッシュアップすることを目標にし、不登法商登法ともにひな形・論点に不安はなかったので、実践編の小さな問題で論点を確認したら、解法を使えるようになるために総合実践編や過去の模試の問題を何度も演習しました。姫野先生は「毎日問題演習しなくてもいい」とおっしゃっていたので、5月末までは週に3問くらいにとどめ、通勤中に解法を脳内で確認して解法をより強固なものにしていきました。過去問の演習は3月中旬から始めました。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
以前受験勉強をしていたときと比べ、集中力がかなり落ちていたので何時間も続けて勉強することができなくなっていました。そこでポモドーロテクニック(25分間の勉強と5分間の休憩をはさむ時間管理術)を利用して細切れで勉強することで、多い時は7時間くらい勉強できるようになりました。
問題が解けないと心身ともにダウンすることがあったので、疲れているときはとにかく寝ること・得意な科目の問題を解いて自己肯定感を上げるなど、自分で自分の調子を上げることを意識していました。
■TACの良かった点【講師】
姫野講師は受験生に対して甘言をおっしゃらず、現実をお話してくださっていたので、とても信頼できる講師だと思います。あと話し方がとても聞き取りやすく、1.5倍速で聞いてもはっきり聞き取れてよかったです。
■TACの良かった点【教材】
記述式対策講座理論編のテキストは、あいまいな論点や似ている論点を整理するのにとても役に立ちました。実践編の気が遠くなるような問題数をこなすのは大変でしたが、全部こなせると論点漏れもなくなって自信につながりました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
記述式対策講座は、ただ問題演習をして解説だけの講座ではなく解法をしっかり教えてくれたおかげで、記述式に対する迷いや恐怖はなくなり、本試験では不登法63点、商登法46点取ることができました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
実力Check模試、公開模試(3回)を会場受験し、各模試をペースメーカーにして学習計画を立てました。記述の採点者さんのコメントは励みになりました。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
通信での受講でしたが、いつでも質問メールで疑問点を聞くとこができ、返信も翌日には届いていたので、勉強が滞ることなく進められてよかった。また、3時間の講義がが3コマに分かれていたので、勉強時間がとれない中少しずつ進められるのがよかったです。
■勉強以外の部分
健康管理には特に気を付けていました。あまり根を詰めすぎないようにして、休日は18時以降は勉強しないでのんびりする時間にあてて心身のバランスをとっていました。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
受験指導校(特に基礎講座)を利用したほうが合格に早く近づけます。決して安い金額ではないですが、はじめから講座を受講した方がコスパはいいと思います。独学で合格できる人は本当にわずかです。SNS等の甘い言葉に惑わされないようにしてくださいね。
N.K さん 最新の法改正を踏まえた論点も出題され本試験のイメージができた
2025年合格目標:全国公開模試

【主な受講講座】
●「全国公開模試」会場受験
【受験回数】10回以上
【学習開始時の職業】公務員 【合格時(合格年の直前期)の職業】公務員
【得意科目】民法・不動産登記法・商法(会社法)・商業登記法・刑法 【不得意科目】民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・司法書士法・供託法
【1日の平均学習時間】2時間 【学習開始時からの総学習時間】5000時間以上
■司法書士受験のきっかけ・動機・学習時の環境
専門職に対する憧れがあり、自分の強みで困っている人の力になりたいという思いが強くありました。さらに、専門的資格を有していれば、住みたい場所で仕事ができる自由さも魅力的でした。私は正規職員としてフルタイムで働きながら、子育てをしながら勉強を続けてきました。仕事や育児と両立を図りながらも、スキマ時間をつなぎ合わせることでなんとか合格できました。
■独学でなく受験指導校を、またその中からTACを選んだ理由
山本先生のオートマチック不登法、商登法の記述式問題集を使用していました。この問題集を何回も繰り返し解くことで、確実に力がついていきました。しかし、本試験では基準点は超えるものの、合格点には届かない状態(記述の点数は安定して取れているが、択一の出来が良くない状態)が続きました。
どうしたらよいか悩んでいたところ、妻からの「受験予備校の模試を利用してみたほうがいいのでは?」というアドバイスを受けました。TACの模試は、回数が多く、内容も良さそうだったので利用することにしました。直接校舎に行って本番さながらに受けることもでき、本試験の予行演習がしっかりできたと思います。
■学習スタイル・スケジュール、科目別勉強法、重視したポイント
私の場合は正規職員としてフルタイムで仕事を続けながら勉強を続けていたため、合格するのにかなりの年数を要しました。記述対策に関しては山本先生のオートマチック記述問題集を使用しました。繰り返した回数は延べ百回をゆうに超えていると思うほど、何度も繰り返し解きました。プロ野球選手が常に素振りを怠らないのと同様に、私も記述式問題集を毎日のように解いて力をつけていきました。本試験で安定的に記述の点数を取れるようになってからも、この問題集は繰り返し解いていました。基礎編・応用編ともに何度も解いて基本を定着させました。このような基本を定着させたことは、本試験でも大いに役立ちました。
また、フルタイムで仕事をしている私にとって大きな課題は択一知識を維持することでした。仕事をする中で知識を忘れていくことをどう防ぐかが特に課題であり、合格してみて思ったのは、やはりスキマ時間をつなぎ合わせて繰り返し参考書を読んだり問題演習をすることなのだということです。
■受験時代の苦労・困難・失敗談、それを乗り越えた方法
私の場合は正規職員としてフルタイムで仕事を続けながら勉強を続けていたため、合格するのにかなりの年数を要しました。特に司法書士試験は、とても細かい択一知識を要求される試験であり、その知識をしっかり維持・定着させる点が特に大変でした。仕事する前に覚えたことも、仕事を終えて家に帰ってきたころには忘れているという繰り返しで、いかにスキマ時間を見つけ、知識を定着させるかが課題でした。
■TACの良かった点【講師】
とにかく山本先生のオートマチック不登法・商登法の記述式問題集の完成度は素晴らしいの一言に尽きます。これを百回以上も繰り返して解くことで、記述の力をつけていきました。記述対策としてはこの問題集と過去問だけでよいと言っても過言ではありません。プロ野球選手が素振りをするように、私も毎日の勉強で素振り感覚で解いて力を定着させていきました。このおかげで記述の点数も安定して取れるようになっていきました。
■TACの良かった点【教材】
模試を利用しましたが、択一は本試験以上に難しく、点数が取れないことで焦りを感じました。しかし、そのくらい難しい問題を直前期に解いたことで、本試験は簡単に感じられました。また、模試の記述についても最近の民法の法改正を論点として取り上げるなどとても新鮮で、これは独学では難しいと思いました。また、山本先生のオートマチック不登法・商登法の記述式問題集は、とにかく何度も解いて力を定着させることができました。
■TACの良かった点【カリキュラム】
TACの模試は他の予備校よりも回数が多く、多くの問題演習をすることができる点がとても良いです。また、記述式の問題も最近の法改正を踏まえた論点も取り上げられており、このように本試験でも出題されることがあるのだと自分なりに予想しながら試験に向かうことができました。
■各種答練・模試、単科講座の活用方法や良かった点
「受験予備校の模試を解いたりして、不合格であった昨年と違うことを取り入れたほうがいいんじゃないかな?」という妻のアドバイスから、模試を利用してその年に合格することができました。妻のアドバイスに感謝しているとともに、完成度の高い模試は受験生にぜひおすすめしたいものです。
■フォロー制度の活用方法や良かった点
フォロー制度もしっかり整えられており、いつでも丁寧に対応してもらえる点がとても良いです。日々の勉強で行き詰まった時や、本試験に向かう上でとても不安になることも多いと思いますが、そういう時も気軽に相談に乗ってもらうことも良いと思います。
■勉強以外の部分
勉強に関してはそれぞれのスタイルがあるため、自分に合ったやり方をやり通すことが大切です。私は平日はフルタイムで仕事をして、帰宅後もまだ小さい娘(2歳)の遊び相手になり、土日も家族サービスをしながら勉強を続けてきましたが、そうした家族の支えも自分の目標達成への良い活力になったと思います。
■これから勉強をはじめる方へのアドバイス
司法書士試験はとても難しい試験ではありますが、私のように正規職員としてフルタイムで働きながら、子育てをしながらでも十分合格は可能です。合格するためには、常に目標に向けて一歩ずつ着実に歩みを止めず、勉強をし続けることに尽きると思います。試験勉強をしているときは不安になることも多いかもしれませんが、予備校を利用しつつ、目標達成に向けて頑張ってほしいと思います。