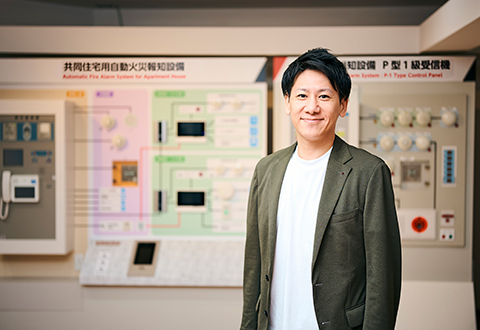特集 先生と生徒が切磋琢磨する神戸商業高校簿記部
〜「簿記チャンピオン大会」で優勝したその理由〜
2024年10月27日(日)のTAC主催「簿記チャンピオン大会」で、3級全国個人戦、団体戦ともに優勝を果たしたのは、兵庫県立神戸商業高等学校(以下、神戸商業)簿記部の1年生(大会当時)だ。神戸商業は2026年度には創立150年を迎える日本で最も歴史のある商業高校。「簿記チャンピオン大会」で優秀な成績を収めた3名に簿記を始めたきっかけや大会の感想を、3名を指導された簿記部顧問で会計科主任の中川靖隆先生、会計科クラス担任の松下雄紀先生に簿記部の指導方針などについてお聞きした。
(取材は2025年3月)

兵庫県立神戸商業高等学校 会計科1年(取材当時) 簿記部
左から
■前田 謙太(まえだ けんた)さん
■原田 律(はらだ りつ)さん
■青木 奏馬(あおき そうま)さん
※「簿記チャンピオン大会」成績 2024年10月27日(日)開催
【3級 全国個人戦】
1位 原田 律さん
5位 青木 奏馬さん
6位 前田 謙太さん
【3級 全国団体戦】
1位 3色だんゴ ※上記3名からなるチーム
◤ 簿記チャンピオン大会とは?◢
日商簿記検定試験合格をめざす方はもちろん、簿記の実力を高めたい公認会計士や税理士をめざす学生なら誰でも参加できるTAC主催の簿記試験競技大会。日商簿記検定試験と同じ問題数&試験時間で設定した試験問題で、各個人の成績を競う個人戦と、3~5名でチームを組んでそのメンバーの平均点を競う団体戦で、1・2・3級ごとの全国個人戦優勝者や全国団体戦優勝チームを決める。
第1部:チームメンバーにインタビュー
「簿記の知識は将来への大きなアドバンテージ」
簿記はまるでパズル
──みなさんは高校入学後に簿記を学び始めたということですが、簿記部に入部した理由を教えてください。
青木 簿記の授業についていけるか不安だったことが一番にあります。簿記部が強いと聞いたので、入ってみようと思いました。
原田 簿記を勉強したくてこの学校に入ったので、簿記を極める目的で簿記部に入りました。いろいろな大会で結果を残したいという気持ちもあります。
前田 最初は音楽部に入ったのですが辞めてしまい、どこか部活に所属したかったので、簿記の授業を受けて楽しいと感じたので簿記部を選びました。
──1年間勉強をしてみて、簿記のおもしろさはどこにあると思いますか。
前田 貸方、借方の数字が合うと、うれしくて気分が上がります。
原田 初見の問題を解いていると、解けなくて答えを見たりしますが、なんでこんな問題が解けなかったんだろうと悔しくて……。逆に次に似たような問題を解けたときは、とてもうれしくなります。それが簿記のすばらしさです。
青木 計算したら絶対に答えにたどりつくことができる簿記は、パズルのようで楽しいです。
「簿記チャンピオン大会」ではスピードアップに集中
──「簿記チャンピオン大会」に参加した感想を教えてください。
前田 初めてだったので、最初はとまどいもありました。でも、なんとか結果を残せてよかったです。
原田 大会前はメチャクチャ緊張していましたが、練習通りにやろうと決めたらスラスラ解けました。練習よりも解くのが遅くて焦りましたが、時間内に間に合ってホッとしました。なにより100点満点で1位を取れたのがうれしいです。
青木 大会本番で焦ってしまい、終わってから見直したらもっと点数が取れた問題がありました。そこが悔しくて残念です。
──「簿記チャンピオン大会」で高得点を上げるために工夫したことはありますか。
原田 100点まであと少しという感覚があったので、練習量を増やしました。大会の3級には完璧な自信がありました。
青木 僕も大会の3級には自信がありました。
前田 僕は基本的に書くのが遅いので、大会前にそこを重点的に練習しました。
──「簿記チャンピオン大会」前は部活の時間以外にも勉強しましたか。
原田 部活が終わったあとも学校に残って、もう1問解いてから帰るようにしました。逆に家ではまったくしなかったです。
前田 大会前は基本的に自宅でやることが多かったです。部活でも問題を解く時間を測る「計測」をしますが、平日は自宅でも1日1計測するように決めていました。自宅だと誘惑があるので勉強時間中はスマホから距離を置き、自分で決めた1計測は絶対こなすと決めて、やり通しました。
青木 大会前は部活のあとも学校に残ったりしましたが、普段から平日は家に帰って必ず1時間やろうと決めていました。土日は気分によって集中できるときはやりました。

▲「簿記チャンピオン大会」当日
──「簿記チャンピオン大会」後、皆さんは日商簿記2級に合格されましたが、重点的に勉強したことはなんですか。
原田 大会が終わってから日商簿記2級の勉強に本格的に取り組み始めた結果、12月に合格できました。
青木 日商簿記2級は工業簿記が苦手なので、商業簿記60点、工業簿記10点の配点をねらうくらいの勢いで勉強しました。
前田 日商簿記2級でも正確性はもちろんですが、時間内に間に合うように書くスピードを上げることに集中しました。
2年生の目標は日商簿記1級合格
──4月から2年生ですが、次の目標を教えてください。
青木 今、高校在学中に日商簿記検定試験1級の合格をめざす「日商簿記1級プロジェクト」に参加しています。11月の統一試験で1級合格をめざすのが簿記部の2年生の目標です。
原田 青木さんと同じで11月に1級合格をめざします。簿記部は公益財団法人全国商業高等学校協会(以下、全商)の2024年全国高等学校簿記競技大会(以下、競技大会)兵庫県予選、団体の部で28年連続優勝しました。個人の部でも優勝、準優勝、3位、8〜10位に入賞しています。2025年は29連覇を達成したいと思います。
前田 僕はふたりよりもあとから「日商簿記1級プロジェクト」に参加したので、まずはその勉強と競技大会の両立ができるようにがんばります。早くふたりに追いつきたいですね。
──試験と競技大会では勉強方法が違いますか。
原田 競技大会はスピード重視なのでどれだけ早く解けるかが重要です。日商簿記検定試験は時間に余裕があるので、どれだけ正確に100点に近い点数を取れるかが鍵です。
高校で簿記を学ぶことは大きなアドバンテージ
──今後の進路や将来の夢を教えてください。
青木 大学進学を希望しています。まだ、具体的には決めていませんが、春のオープンキャンパスでいろいろな大学を見て考えます。
原田 やはり簿記が好きなので簿記を極められる大学に行きたいと思います。
前田 僕は大学へ行って経営を学び、将来は地域密着型の企業を起業したいと思っています。
──簿記を学んだ先に、公認会計士、税理士という選択肢はありますか。
前田 今はまだ考えていませんが、将来的には考えていきたいと思っています。
原田 公認会計士や税理士は、漠然と将来の選択肢に入ってきています。ただ公認会計士は超難関資格だと聞いているので、果たして自分が合格できるのか不安はあります。
青木 僕は公認会計士試験合格が目標です。公認会計士の小島一富士(こじま かづふじ)先生の講演を聞いて、「すごい!やりたい!」と思いました。
原田 僕たちは普通高校の人たちより3年間早く、そして多く簿記を勉強します。簿記の知識が身についていることは、大学進学でも将来の就職でも大きなアドバンテージになると思います。
──みなさん、おめでとうございました。これからのそれぞれのご活躍を楽しみにしています。

▲部活動では、各自が何を勉強するかを自分で決めている
第2部:先生にインタビュー
「1年生で日商簿記2級、
2年生で1級合格を目標に、生徒と切磋琢磨」
自作の過去問題集で日商簿記2級攻略
──現在、簿記部は何名在籍していますか。
中川 1年生11名、2年生6名、3月卒業の3年生6名(2025年3月現在)です。神戸商業には商業科・情報科・会計科の3学科があります。簿記部には基本的に会計科の生徒が入ります。商業科でも簿記が好きな生徒がいるので、見学会やオープンスクールで興味を持った生徒には入部を勧めています。
──簿記部の活動時間を教えてください。
中川 基本的に週5日で、月・火・木・金は16:00〜18:00、土曜日は9:00~12:15が活動時間です。私は平日21:00ころまで、土曜日もほぼ日中は学校にいるので、その間は教室を開放しています。活動時間外は1級の補習や各個人で課題に取り組んでいます。
──教材などで工夫されたことはありますか。
中川 日商簿記2級・3級は一般社団法人日本商業教育振興会(以下、日商振)の「会計サポート」のテキストを活用し、さらに2級は、過去の問題から類似問題を省いて自作した「過去問100回」を活用しています。
クラス担任が生徒と一緒にチャレンジ
──中学時代、簿記にまったく触れたことがない生徒に、どのように簿記教育を広めていかれますか。
中川 2026年度からは中学生向けに簿記の授業を計画しています。そこで簿記に興味を持ってもらい、会計科や商業高校に進むきっかけ作りをしていきます。また本校では、日商振の代表理事で公認会計士の小島一富士先生に「簿記を学ぶ意義」の講演を毎年していただいています。今回の「簿記チャンピオン大会」で1年生が成果を出せたのも、日商振の「会計サポート」を活用したからこそと感じています。
──「簿記チャンピオン大会」で3級で全国優勝・上位入賞した3名は、1年生で日商簿記2級に合格しましたね。
中川 何より大きかったのは簿記部の顧問でもあり、クラス担任でもある松下先生が、計測した問題の得点を一覧にして教室掲示等を継続してくれたことで、生徒の中に負けたくないという気持ちが芽生え、切磋琢磨できました。また、夏休みに日商簿記3級にチャレンジしたこと、「簿記チャンピオン大会」が10月下旬だったことも追い風でした。11月の日商簿記検定の統一試験やCBT試験で各自がじっくり集中して取り組んで合格をすることができました。
松下 私は本校の会計科卒業生ですが、放課後は野球部でずっとボールを追いかけていました。ですので改めて生徒と同様に簿記を学びなおして、2025年6月には日商簿記1級を2年生と一緒に受験します。この環境に身を置けたことをチャンスと思って勝負しますが、プレッシャーは大きいです(笑)。
──「簿記チャンピオン大会」への参加が後押しとなったのですね。
松下 成功体験があるのは大きいです。大会を通じて合格ラインの70点ではなく、90点、100点をめざして突き詰める経験があったからこそ、スッと2級の合格ラインを越えていけました。3級のできていない部分をそのままにしておかなかったことも、よかったと感じています。

中川 靖隆(なかがわ やすたか)先生
兵庫県立神戸商業高等学校
第一学年主任・会計科長 簿記部顧問(取材当時)
1年生で日商簿記2級、2年生で1級合格が目標
──簿記部ではどのような目標設定をしていますか。
中川 1年生は夏の日商簿記3級合格、12月の2級合格と、1年生のうちに2級まで合格するのが目標です。これはほぼ全員クリアしています。続けて日商簿記1級合格をめざす生徒もいます。
──2年生から日商簿記1級合格をめざすのですか。
中川 日商簿記1級をめざす生徒が半数いる中で、大半は全商の全国高等学校簿記競技大会(競技大会)に目を向けていています。2024年の兵庫県大会、団体の部で28年連続で優勝しているので、2025年は29連覇をかけて取り組んでいます。
──日商簿記検定試験と競技大会では、学習のアプローチは違いますか。
中川 違います。特に日商簿記1級は複雑な判断基準があるので、それを知っていると競技大会の簡単な設問で逆に考えこんでしまい、処理に悩む生徒がいます。加えて競技大会ではスピード感やパズル的要素も出てくるので、柔軟性、判断力といった頭の違う部分を使います。
でも、そのスキルを身につければ1級にも柔軟性を持って対応できるはずです。そこで本校では、1級だけに専念せずに競技大会との両輪で考えています。また、1級商業簿記の総合力を上げる目的で税理士試験の簿記論を学ぶ生徒もいます。
──税理士試験の簿記論も学ぶのですね。
中川 そうですね。2025年3月に会計科を卒業した長山恭子さんは、2024年11月の日商簿記検定試験1級、2024年8月の税理士試験簿記論に合格しました。競技大会では県大会優勝、全国大会入賞、日商簿記甲子園で県予選、近畿予選を突破し、全国大会にも進んでいます。
税理士試験の簿記論や財務諸表論を勉強することは、1級商業簿記の総合力を上げ、公認会計士や税理士をめざす道にもつながります。そして、簿記論の合格者であることは、将来の就職など社会人としての選択肢が広がると考えています。
松下 神戸商業には先生と生徒が切磋琢磨する校風があります。そこがすごく楽しくて、刺激になるし、子どもたちに教えるやりがいにつながっています。

松下 雄紀(まつした ゆうき)先生
兵庫県立神戸商業高等学校
会計科クラス担任 簿記部顧問
日商簿記1級合格の加点枠で大学進学も
──将来像として公認会計士を意識する生徒もいますか。
中川 入学当時から公認会計士の仕事について紹介しているので、公認会計士になりたいという生徒はかなり多いです。1年生で日商簿記2級まで学ぶので、よりリアルにイメージできるようになってくるのが2年生です。
──卒業後の進路は進学が多いのですか。
松下 学校全体では進学が約7割、就職約3割ですが、会計科は進学がかなり多く、40名クラスのうち就職は5〜6名で、残りは半数ずつ大学と専門学校への進学です。
日商簿記1級合格なら兵庫県立大学、関西学院大学、関西大学などの大学で、選考時に加点される枠を活用できます。山口大学や福島大学では、1級の勉強をしている過程を評価してもらえます。
中川 会計科は四年制大学に進学する生徒がとても多く、大学入試にチャレンジしていくプロセスで、公認会計士をめざして専門学校に行く選択肢も並行して進路指導しています。四年制大学に進学する覚悟を決めた上でダブルスクールで公認会計士をめざす、あるいは会計系資格の受験指導がある学校に進める環境をきちんと作ってあげたいと考えています。
簿記教育の向上に尽力
──簿記を学びたいと考えている方にメッセージをお願いします。
中川 簿記は基本的に足すか引くかの概念しかないので、非常にシンプルです。活躍する公認会計士や税理士の姿がめざすべき像になれば、たとえつまずいても簿記は通過点として乗り越えていけるはずです。
松下 公認会計士や税理士の姿を認知した上で高校3年間簿記を学んで過ごせたら、大学に入ってから簿記を始めるよりも大きなアドバンテージになります。本腰を入れて簿記ができる環境を用意して、今後この学校の継続と県の簿記教育がさらに向上することが私の一番の願いです。
──次回「簿記チャンピオン大会」でも、神戸商業高校のみなさんの活躍を楽しみにしています。

[『TACNEWS』 2025年6月|特集]