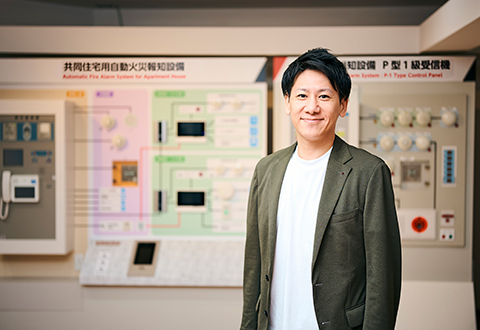特集 介護・福祉分野で活躍する弁護士

外岡 潤(そとおか じゅん)氏
法律事務所おかげさま 代表弁護士
保有資格:
ホームヘルパー2級(現・初任者研修)
レクリエーション介護士2級
1980年、北海道札幌市生まれ。2003年、東京大学法学部卒業。2005年、司法試験(旧)合格。その後、札幌で実務修習。2007年、弁護士登録(第二東京弁護士会)。同年、ブレークモア法律事務所入所。2009年、城山総合法律事務所入所。2009年4月、法律事務所おかげさま開設。同年、ホームヘルパー2級(現・初任者研修)取得。2017年、レクリエーション介護士2級取得。
「正義感の強さから弁護士をめざしました」。弁護士には、そういった高い志を持つ人が多い。独立して11年目の弁護士、外岡潤氏、40歳もそうしたひとりだ。ただ、外岡氏が人と違うのは、企業法務や刑事事件ではなく、民事事件の中で、介護・福祉の一点に特化した弁護士をめざした点だ。介護トラブル訴訟案件に数多く関わりながら、管轄裁判所は札幌、東京、静岡、名古屋、大阪など全国に及んでいるという。介護・福祉弁護士、外岡潤氏を通して、介護・福祉業界の現状に迫った。
マンガで「介護・福祉の弁護士」にめざめる
──外岡さんが弁護士をめざした経緯を教えてください。
外岡 中学、高校時代は特に何かに打ち込んだことはなかったですね。あまりほめられたことではないのですが、弁護士になったのも消去法からでした。東京大学文科一類に入学し法学部に進んだので、将来は司法試験か、国家公務員一種(国家一種:現・国家公務員総合職試験)か、一般企業に就職するか、ほとんどの学生はその3択から選ぶことになります。しかし就職活動は自分の中でしっくりこないし、国家一種試験を受けられるほど成績はよくありません。法学部の定期テストに合わせて法律を勉強していくうちに、それが司法試験にシフトしていきました。ですから、強い想いがあって弁護士をめざしたわけではないのです。
大学3年生で初めて旧司法試験を受けましたが、当時はちょうど旧試験から新試験に切り替わり、旧試験がどんどん狭き門になっていく時期でした。新試験に切り替えてロースクールに入る人もいましたが、私は新試験に切り替えようとは考えられなかったので、旧試験を受け続ける選択肢しかありません。合格するまでずっと受験を続けなければならない、追いつめられた状況で、2005年の4回目のチャレンジで旧試験に合格しました。
──合格後の実務修習はどこで受けたのですか。
外岡 北海道札幌市です。私の生まれは札幌市で、父の転勤で3歳のときに東京に引っ越してからは、ずっと文京区に住んでいます。札幌市には父方の親戚がいて親しみを感じていたので、修習の第一希望にしました。幸い、修習1年目で就職先が決まったので、その後は東京に戻って勤務することになりました。
──就職先はどのように決めたのですか。
外岡 父は転勤の多い仕事で、10歳のときに1年間だけ一緒に転勤先のアメリカに行ったことがありました。そのとき漠然と、父が海外で仕事をする姿はカッコいいなあと思い、英語を扱うビジネスに憧れを抱きました。弁護士になってからも海外への憧れがあったので、渉外法律事務所(外国や外国法が関係する国際案件を扱う法律事務所)に就職を考えていて、外国弁護士資格者のトーマス・L・ブレークモア先生が設立したブレークモア法律事務所に所属を決めました。
──渉外法律事務所に就職したあと、どのようにして介護・福祉系弁護士として独立されたのでしょうか。
外岡 ブレークモア法律事務所は、渉外法律事務所といっても外資系事務所ではなかったので、半数は国内の企業法務でした。企業法務は専門性も高く、会社法、金融商品取引法、独占禁止法や有価証券法など、それぞれの分野のエキスパートが次々育っていきます。その分野が好きで追求している人や、証券会社勤務経験者といったさまざまなバックグラウンドを持って活躍している弁護士が大勢いましたが、1年もすると「自分はこの世界では強みを活かせないし、情熱を持ってできないな」という葛藤が生まれ、別の事務所に移ることにしました。
──渉外法律事務所では将来が見いだせなかったのですね。
外岡 そうですね。自分の将来像が見えなくて悶々としていたときにたまたま出会ったのが、くさか里樹先生の描いた高齢者介護をテーマにしたマンガ『ヘルプマン!』でした。読み始めると止まらず、一気読みしてしまうほど衝撃を受けました。それまでは、高齢者はおだやかで、介護は平和で単調な世界だと思っていましたが、そのイメージが覆されたのです。認知症の高齢者の家族が混乱に陥っているところを、若い男性ヘルパーが機転を利かせて明るい方向に導く。かなり型破りで意外性のあるストーリーは、自分の思っていた介護の世界とはまったく違いました。
これをきっかけに、介護の世界で弁護士のニーズがあるかどうかわかりませんでしたが、「自分の力を発揮するなら介護の世界でやりたい!」と強く思い、後先を考えずにたった数ヵ月で独立しました。
「介護・福祉系法律事務所 おかげさま」誕生
──独立当初から「介護・福祉専門の弁護士になる」と決めてのスタートだったのですね。
外岡 はい。とにかく介護・福祉分野と決め、「介護弁護士」というコンセプトで独立しました。調べてみると、医療分野の弁護士は多かったのですが、介護・福祉が専門という弁護士は見かけませんでしたので、医療との棲み分けという意味合いで、介護・福祉に特化してスタートしました。
──事務所名が「おかげさま」というのもユニークですね。
外岡 『ヘルプマン!』を読んだ瞬間に「おかげさま」という言葉が浮かんで、これだと思いました。お年寄りはよく「おかげさまで」とあいさつ代わりに使いますし、介護の現場では日常的に使われる印象があったので、介護・福祉系弁護士事務所にはふさわしい気がしました。感謝を伝える言葉でもありますし、「あ行」で始まるので覚えやすい。独立する前からこの事務所名にしようと決めていました。ロゴのお地蔵様は「おかげ地蔵」といって、絵の得意な司法書士の友人が描いてくれました。
──場所はどちらで開業されたのですか。
外岡 「おばあちゃんの原宿」といわれる巣鴨地蔵通り商店街近くで、駅から商店街の間にある雑居ビルの1室で開業しました。実家のある文京区から近く、周りに弁護士事務所はあまりなかったですし、何といってもお年寄りにネームバリューがある場所でしたから。しかし巣鴨ではまったく仕事がありませんでしたね。巣鴨という観光地に来るようなお年寄りは、積極的にお金を払って弁護士に相談することがなかったようです。
──そこからどのようにして顧客開拓をされたのでしょうか。
外岡 当初Webサイトからの依頼がありましたが、件数はそれほど多くなかったので、日中は別の事務所で債務整理のアルバイトをしながら、ホームヘルパー2級(現・初任者研修)の勉強を始めました。介護・福祉専門の弁護士として、何か前進できるものがあれば何でもいいから挑戦してみたかったのです。講座に通う中で施設の現場職員の方と知り合うことができ、徐々に人のつながりができてきましたし、ヘルパーの勉強をすることで、介護の世界を知ることもできました。
──実際に介護の現場で働いたこともあるのですか。
外岡 現在は事務所を新宿に移していますが、まだ巣鴨にいたころ、地元の介護ステーションがスタッフを募集していたので、週1回だけ訪問介護をやってみました。エレベーターのない古いアパートの4階から1階まで、車いすを持ち上げて降ろし、デイサービスに送るというものでした。訪問介護にはその他にも食事介助や入浴介助など幅広い業務があり、専門性がかなり高いと感じました。

「和の弁護士」を掲げトラブル予防サービスを展開
──独立に際して、どのようなビジョンを掲げましたか。
外岡 私は「平和」の「和」の字にちなんで「和の弁護士」というスタンスで、介護施設などとその利用者側とが争わないためにはどうしたらいいかという部分に軸を置いています。そのため、依頼は施設利用者のご家族からの相談が多い一方で、顧問契約を結んでいる介護施設や障害者施設を運営する事業者からの相談依頼も多く、割合としては半々ですね。
──施設利用者側からの相談内容を教えてください。
外岡 典型的なのは、施設に入居している親が転倒、骨折、ケガをした、あるいは入院してしまったという事例です。また施設が不衛生であるといった苦情や、認知症で暴れる入居者がいるといった事例もあります。中でも多いのは、入居者が施設内で転んだりしてケガをした際、利用者側が求めても施設側が対応してくれない、きちんと謝ってくれない、あるいは説明をしてくれないといったケースです。施設内で事故などが起きても施設側が謝罪をしてくれないというケースは、利用者家族にとって重大な問題になっています。謝罪してきちんと対応していれば大きな問題にもならなかったのに、初期対応や家族対応が悪くて問題になり、裁判にまで発展してしまうケースが圧倒的に多いです。
──施設側に謝罪の姿勢がないというのは、補償など先々の裁判リスクを見越しての対応なのでしょうか。
外岡 それもありますが、理由のひとつは、居室などで誰も見ていないときに転んで骨折したのではないか、といったグレーなケースが多いことです。ひとりでいるときに誤って転ぶというのは、自宅にいても起こり得る不可避な事故です。謝罪するといっても、自分たちが一緒にいる最中に転んだわけではないとなれば、施設職員としてはどうしても「見てもいないことなのに、自分たちが悪いのか」「自分たちに責任はない」と思ってしまうのです。
──施設や事業者側からの相談ではどのような内容が多いのですか。
外岡 介護士には女性が多いこともあり、セクシャルハラスメントやモラルハラスメントを受けたというトラブルが多いですね。ひとりで訪問介護に出かけて、利用者の家族からセクハラを受けそうになって身の危険を感じたというケースです。
──そうした施設や介護現場でのトラブルを解決するために、何か特別なサービスは行っていますか。
外岡 今お話ししたような施設でのトラブルを未然に防ぐために、「謝罪訓練」というサービスを行っています。4人1チームで2手に分かれ、家族と施設職員を演じてもらうオリジナルの体験型実習で、家族役が施設職員役に対して「なぜ転ばせたんだ」「なぜ連絡が遅れたんだ」と詰め寄り、それに対して謝罪しつつうまくかわすという訓練です。
施設側はそうした交渉ごとの経験がないので、トラブルがあると右往左往して思考が停止してしまいがちですが、一度シミュレーションしておくことで、何か起きたときにトラブルを予防する心の準備ができるという水際対策になります。
セミナーや講演会で一番伝えたいのもそうしたトラブル対応で、最も典型的なのが現場でトラブルにならないための対処法、いわゆるリスクマネジメントです。私にできることは、この謝罪訓練やそれにまつわるセミナーといった、トラブルの予防サービスだと思っています。
ほとんどのトラブルは「心の問題」
──トラブルを未然に防ぐことができなかった場合、どのような対処がありますか。
外岡 現場でトラブルが起きた際の対応としては、施設側は損害賠償保険に入っていますから、保険会社と協議検討して結果をお伝えし、それでもうまく調整できなければ裁判という流れになります。しかし、賠償保険の処理方法のスキームが定まっていないので、結論が出るまでに時間がかかり、結論が出たとしても保険金が支払われないこともあるようです。
私はこれまで数多くの利用者側・施設側双方の相談を受けてきましたが、その根底にあるもののほとんどが「心の問題」であるとわかりました。一見、法律上のトラブルに見えても、家族の思いの根っこにあるのは「あのとき施設長から心ないひと言を言われた」とか「冷たい態度をとられて傷ついた」という素朴な不満で、それらが争いの根源になっています。
介護現場ではいろいろなトラブルが必ず起きます。大切なのは、何か事故が起きた場合、ご家族の不信感が裁判につながってしまうことを、施設側が普段から自覚しておくことです。先手を打って丁寧に対処する、あるいはコミュニケーションを密に取るといったリスクヘッジが必要です。普段からのご家族との向き合い方や、トラブルが起きた際の話し方ひとつで、結果が変わってくるのです。
こうした課題には、法的に正しいか否かとは違う面でフォーカスしていかなければなりません。相手の気持ちを読み取って感情のもつれを解きほぐすことで、法律問題に発展する前に争いを回避する。そのために、私は日々トラブルと向き合っています。
──実際に裁判になった場合は、どのような結果になりますか。
外岡 過去には、利用者が自分の居室で転ぶといった事例であっても、施設側の責任が認められたケースもあります。ただ、過失認定基準はまちまちですね。過失の有無については、担当する裁判官の感覚による部分も多く、最終的には法律だけではなんともならないというのが私の実感です。というのも、施設の管理不行き届きなのか、それとも不可抗力なのかは、見極めがつかない紙一重の部分だからです。
だからこそ、施設側が誠意を持ってきちんと真摯に対応することが大切なのです。そうすれば、多くの利用者家族が「いつもお世話になっているのだからもめ事は起こしたくない」と考えるはずです。
施設側は現場の判断で利用者側に謝っていいのか迷われると思いますが、現場では「道義的な意味で謝るのであれば、賠償責任には関係ないので安心して謝ってください」と、謝罪訓練でもセミナーでも話しています。
──施設側の謝り方や対応ひとつで、リスクはかなり小さくなるということですね。
外岡 そうですね。マニアックな話をすると、施設側の対応は、その施設の母体が社会福祉法人か、株式会社か、NPOか、医療法人かで、実はかなり傾向が違ってきます。
例えば社会福祉法人であれば公的な存在ですから「サービス業である」という点を現場職員らに強調して「2000年の介護保険制度導入によって介護は措置から契約に移行したので、利用者は契約の相手、イコールお客様として捉えなければなりません。夜中であっても安全配慮義務があり、賠償責任が認められた裁判例もありますよ」という流れで持っていきます。
株式会社の場合は基本は利益追求組織ですので「謝らないことで損をすることがあります。謝ったほうが合理的で、経済的ですよ」といった損得の観点から説明をします。このように、ひと口に施設といっても、その母体となる組織の特性や気質によって在り方がまったく違うので、それに合わせて説明することで謝るためのモチベーションを高めていきます。

新型コロナウイルスで変わる死生観
──介護・福祉に特化する中で、今うかがったリスクマネジメントのほか、どのような分野に挑戦されていますか。
外岡 古巣の事務所で経験した渉外関連の案件も扱っています。最近は介護系人材紹介会社から、特定技能の在留資格を使ってフィリピンやベトナムなどの外国人に日本で働いてもらうための手続について相談を受けました。国際渉外案件の世界から、介護というまったく畑違いの分野に来たと思っていたのに、実は繋がっていたのです。介護というフィールドにおいても、東南アジア等の人材導入が課題となってきており、そういった分野の話もあれば外国語の契約書チェックもあり、グローバルな話になってきています。その他、役員会議事録のチェックやM&A、医療の専門知識が問われる事故案件まで、範囲がとても広く果てしないという印象です。そうした意味で本当にいろいろな経験をさせてもらっているなと実感しますし、一つひとつの問題に答えが用意されていることもない。介護業界は定型的な事案などない、特殊な事案ばかりの業界だと感じています。
──高齢化に伴い介護施設も増加傾向にありますが、今後の介護・福祉分野ではどのような対応が必要だと思われますか。
外岡 私自身でいえば、医療介護の知識はもちろん、成年後見制度、相続や高齢者の財産管理といった問題も扱わなければならず、顧問先企業の土地や建物の賃貸借、施設を建てる建設契約もあり…と本当に幅広いので、常に勉強し多様な対応をしていかなければなりません。ちょうど今は新型コロナウィルスに関して厚生労働省が矢継ぎ早に最新情報を発信していますので、それにキャッチアップしていかなくてはいけない一方で、施設側に分かりやすく説明するための情報整理も必要で、やるべきことは無限にあります。
──新型コロナウィルスのクラスター(集団感染)が発生した施設もありました。
外岡 介護施設は医療機関と違って、医療物資もなければ、施設職員は感染予防の訓練も受けていません。入居者は高齢者ですから動けないし、認知症でマスクをつけられない方もいらっしゃるので、本当に無防備です。実際にクラスターが起きた施設では、入院させることもできずただ施設にとどまって治療し、そのまま観察を続けるしかない状態であるようです。
新型コロナウイルスによる非常事態宣言で、私への新規の相談も激減してしまいました。それまで施設からはクレームやハラスメントの相談が多かったのに、それどころではなくなってしまったのでしょうね。ポストコロナでこの業界がどうなっていくのか、まだ先行きは不透明です。
──介護・福祉特化に追従する弁護士はいますか。
外岡 いますね。実際に介護施設で働いていたという経歴を持つ弁護士もいれば、最近では施設向けの対応を打ち出している法律事務所の広告もよく見かけます。ただ、施設側の相談を受けるところはあっても、利用者側の相談を受け付けるところは少ないという印象ですので、市場は偏っていると思います。
──その背景にはどのような要因があるのでしょう。
外岡 まず介護・福祉の事案はいわゆる交通事故のようにパターンが決まっていません。記録や医療関連とのやりとりにおいても専門性が高く、かつ、結果いくらの報酬が見込めるかという目安が、労働審判や交通事故のようにありません。1円にもならないこともよくあるのです。「訴訟すればいくらもらえる」「裁判で必ず勝てばいい」という世界とも違う。うまく落としどころを見つけていく解決方法なので、まだまだ敬遠されがちなのでしょう。
──Webサイトの業務分野に「扱わない分野」を掲載している理由を教えてください。
外岡 「扱わない分野」には債務整理などを載せていますが、私はそれらの業務がどうしても機械的で好きになれませんでした。また大量処理のためにスタッフも雇わなければなりませんので、そうなると介護の専門的な仕事ができなくなります。私には、誰も考えたことのないような創造的な問題解決方法を模索するほうが合っている気がするのです。
例えば今は新型コロナウイルスの影響で「介護施設にお見舞いに行った家族が、入居者と面会できない」という問題が浮上しています。施設に行っても親に会わせてもらえないので、無理やり退去させ、無理心中したという痛ましい事件も実際に起きました。このようなとき、法律家であれば「家族には、入居者である親と面接する権利がある」などと構成し主張できますが、一方で施設側としては、権利だからといって面会を認めていると「三密」になりクラスターが起こるかもしれない。そういった危険から、全関係者の命を守るという要請があるわけです。そうなるとやはり安全を管理しなければならないので、そのことを家族にも説明しますが、そこで「施設管理権に基づき面会を禁止します」などと杓子定規なことを言っても、「会いたいのに会えない」という心の問題は解決しませんよね。では具体的にどこで落としどころを見つけていくのか。そうしたことを考えていきたいのです。
更にいえば、高齢で余命の限られた高齢者の終末期における「看取り」はどうするのか。「家族はひとたび親を施設に入れたら最後、死に目にも会えない」。果たしてそれでいいのか。新型コロナウイルスに感染してしまうと、お見舞いどころか通常のお葬式もあげられず、お骨になるまで会えません。このように新型コロナウイルスの影響で死生観も変わっていくと思いますが、施設はその生と死が日常的に繰り返される、まさに最前線なのです。
私は、看取りで大事なことは「スキンシップ」だと思っています。見送る側の喪失感を考えれば、ビニールカーテン越しに親を見るだけでは「会った」ことにはならないし、実際お別れをするときは手を握るなどしないと意味がない。一方で、新型コロナウイルスの持ち込みは当然ながら徹底阻止しなければならない。しかし感染を恐れガチガチに施設管理をした結果、ご家族から「一体何のための施設なんだ。これでは強制収容所と変わらないではないか」と言われてしまう、といったケースもあります。
新型コロナウイルス感染の危険があるとしても、そういう問題をどうやって乗り越えていくかを考え抜くことが、ヒューマニズム、人権擁護に必要な過程だと思います。
法律論から外れますが、今回のコロナ禍は、医学的な死生観を根底から変えるものであったのかもしれません。「1分1秒でも長く心臓が動いていれば人類の勝利か」といえば、実はそうではないという。これは持論ですが、すべてはいかに充実した人生を送れたかに尽きると思います。この概念を介護学ではQOL(クオリティ・オブ・ライフ)といい、現場でも重視されています。
こういった深い、しかし現場で今起きている問題は、厚生労働省の方針や、既存の法律の枠組みではもはや解決できない世界になります。介護現場における新しいコンセンサスを作っていく転換点ではないか。私はそういう課題を解決していきたいと考えています。
志高い人たちとの出会いが原動力
──外岡さんは現在弁護士歴11年目ですが、今後の方向性はどのようにお考えですか。
外岡 私の場合は本当に好奇心で始めて、今も介護・福祉の世界に興味が尽きません。ただ、ずっとこのまま介護・福祉だけに特化してやっていくか、やっていけるのかは、本当にわかりません。お話しした新型コロナウイルスと看取りの問題のように、解決しなければならない未解決の問題が次々と出てくるので、社会的問題の観点からは終わりの見えない世界です。
──介護・福祉に特化した弁護士として、仕事を続けていく上でのやりがいや、取り組んでよかったと思う点をお聞かせください。
外岡 利用者側がきちんと施設側と和解できて事件が解決したときは、感謝してもらえて大きなやりがいを感じますし、ひとつの区切りとして達成感もあります。あるいは自分なりに課題を見つけて情報発信したり、動画配信で解説したりした際に受け入れてもらえるとうれしいですね。
私の顧問先の施設や事業所は、個性的でポリシーと理想を高く掲げてがんばっているところが多いです。スーパーマンのような崇高な理想を掲げている意識の高い施設もあって、そうした方々とやりとりしていると、こちらも元気を分けてもらえます。その出会いが大きな原動力になっていますね。
──最後に、スキルアップをめざしている方々に向けてメッセージをお願いします。
外岡 新型コロナウイルスをきっかけに、今後は福祉のように社会に貢献しつつ収益もあげていけるソーシャルワーク的な資格が盛り上がってくることを願っています。
今スキルアップを考えているみなさんは、まず自分に正直になることが大切です。自分が本当にやりたいことは何か。私自身も経験したことですが、やはり生活の手段としてだけの存在では、仕事は苦痛になります。でも、少しでもやりがいを見いだせれば、それは天職になります。
最初から「この仕事なら年収がいくら見込める」といった外形的条件から逆算するとうまくいきませんが、何でもいいので自分のアンテナに引っ掛かる世界に出会うことが第一歩となるでしょう。その世界で、例えば法律であればどのような課題があるのかをリサーチしたり、実際に飛び込んでみたりすることで新鮮な発見があるものと思います。
自分が活躍できるフィールドを見つけられれば、そこで何かを組み立てるなど創造的でとても魅力ある世界が開拓できます。私自身、ノープランで企業法務から始め、紆余曲折あって介護・福祉分野にたどり着いたように、皆さんも先入観を持たずにいろいろな世界に触れてみてください。あらゆる経験は無駄になりませんから。
[『TACNEWS』 2020年9月号|特集]