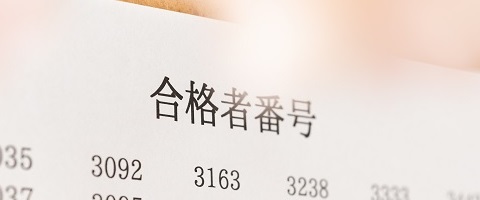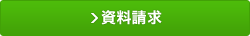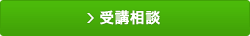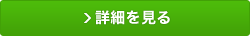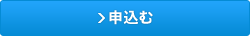賃貸不動産経営管理士の過去問は解くべき?入手方法や活用方法は?例題も紹介!
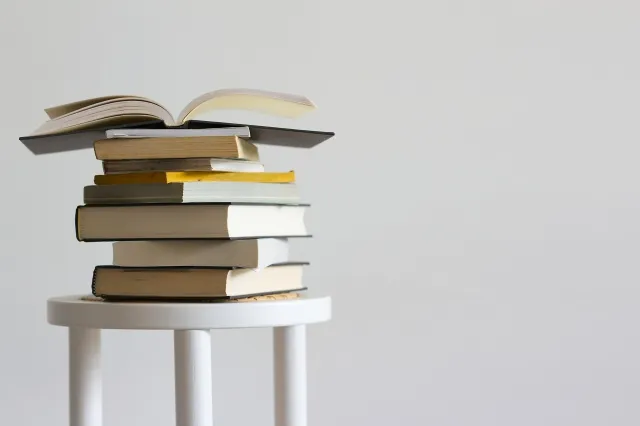
あらゆる試験で一度は触れるであろう「過去問」。
賃貸不動産経営管理士にももちろん過去問はあります。
出題傾向や難易度を知るためにも過去問は重要です。
賃貸不動産経営管理士は国家資格化したばかりで過去問が少ないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、国家資格化する前から試験は行われていたので過去問はけして少ないわけではありません。
しかし、大学受験用の赤本のように書店にずらりと並んでいるわけではないので、どうやって入手すればいいのかわからない方も多いでしょう。
また、入手できたとしても令和元年までは問題数が40問だったのに対して、令和2年以降は50問と問題数も増えているため、どのように過去問を活用していけばいいのかわからない人もいるのではないでしょうか。
ここでは過去問の重要性、そして入手方法と活用法から例題までを解説していきます。
賃貸不動産経営管理士(賃貸管理士) デジタルパンフレットを閲覧する
賃貸不動産経営管理士の過去問は重要?
国家資格化したのは2021年からですが、国家資格化以前の過去問があることは冒頭でお話ししました。だからといって、国家資格化前の過去問は解かなくていいのかというと、そうではありません。他の資格や試験と同様に、賃貸不動産経営管理士も過去問に触れておくことは重要です。
賃貸不動産経営管理士の過去問が重要な理由
賃貸不動産経営管理士の過去問が重要な理由として、「問題に慣れること」があげられます。
知識を習得しただけでは問題は解けません。
実際に出題された問題を解くことで、「知識がどう問われるか」に慣れる必要があります。
それから、過去問を解くことにより本試験の時間配分も考えることができます。
50問を120分(2時間)で解くことになるので、単純計算では1問2分程度で解答していかなければなりません。
しかし、苦手分野や長文の問題はやはり時間がかかってしまうものです。
その対策を立てる意味でも、過去問を解いて慣れておくことは重要といえます。
-
こちらもチェック!
賃貸不動産経営管理士の過去問入手方法は?
さて、過去問の重要性についてはお分かりいただけたと思いますが、「過去問はどこで入手したらいいの?」という方のために、過去問の入手方法をご紹介いたします。
試験実施団体のホームページから過去10年分の問題を入手可能
まずは試験実施団体のホームページです。
賃貸不動産経営管理士協議会のホームページでは過去10年分の過去問題が入手可能です。
なお、同じページで正解番号の一覧も見ることができます。ただし、詳細な解説は記載されていません。
つまり、自分の間違えた問題について「なぜ間違えたのか」が判然せず、もやもやとしてしまうのです。
TACでは解説付き問題冊子が入手できる!
一方で、TACでは解説付き問題冊子を入手することができます。
メールアドレス等必要事項をフォームにご入力いただくことで入手可能です。
『無料』令和7年度(2025年度)賃貸不動産経営管理士試験 解答解説集を閲覧する
令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の問題に加え、TAC講師陣による全問題の解説を掲載したデジタルデータを無料でご請求いただけます。これから資格取得を目指す方や、再度挑戦される方も必見です!以下のフォームにご入力の上、ご請求ください。

個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
また、それぞれの問題に対してA・B・Cとランク付けをしています。
賃貸不動産経営管理士の受験生向け無料採点サービス「データリサーチ」をもとに、正答率70%以上のものをAランク、40%以上70%未満のものをBランク、40%未満のものをCランクとしています。
解説もついているため、正解肢だけでなく正解肢である理由もわかって理解力も深まることでしょう。
賃貸不動産経営管理士の過去問の活用方法
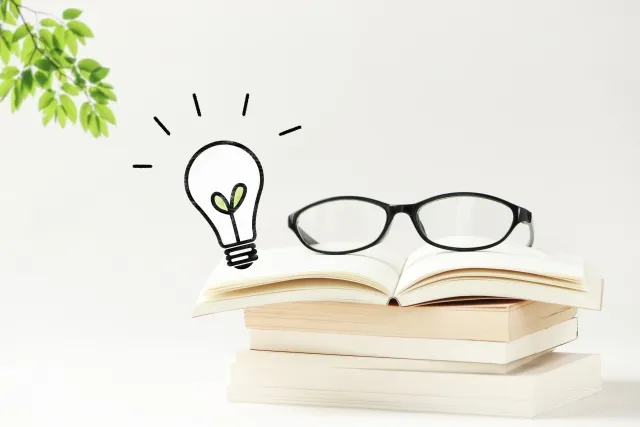
次は過去問を入手後の活用方法についてです。
せっかく入手した過去問も活用しなければ意味がありません。
過去問の活用方法について、TACの講師が解説します。
出題傾向を知る
過去問は今後どんなテーマの問題を出題されるのかを教えてくれる出題者側からのメッセージだと捉えましょう。令和3年の賃貸不動産経営管理士でも出題論点の4割程度が直近6年間の過去問から出題されていました。今後の出題傾向を知る上で、過去問の分析・検討は欠かせません。
また、不動産系の資格は他にもありますが、それぞれ出題される分野が重なっている部分とそうでない部分はあります。
特に「賃貸住宅管理業法」は他の資格試験に出題されることはほとんどなく、メインの科目にもなるのでどのように問われているのかを知ることは大切です。
さらに、賃貸不動産経営管理士は敷金等の金銭の問題や、建物の構造なども問われます。試験範囲が広いため、その中でもどの部分が重点的に問われるのか(=どの部分を重点的に勉強すべきか)は複数年度の過去問を解くことで知ることができます。
知識が定着しているかの確認に使う
試験対策を始めた後は、過去問を項目ごと・肢ごとにバラバラに使ってみましょう。学習した知識で過去問題が解けるかを確認します。
その際、問(四肢択一)ごとに答えを出すのではなく、肢ごとにその内容が合っているのか間違っているのかを判断します。肢が間違っている内容であれば、どこが間違っているのか・どう正せば良いのかが分かるようになるまで繰り返し行いましょう。
過去問を使って時間配分に慣れる
先ほども少し触れましたが、賃貸不動産経営管理士の試験は50問120分です。
時間内に解けるようにするために、過去問を使いましょう。
50問を120分で解くのは簡単なように思えますが、人によっては難しく感じることもあります。
時間配分を誤ってしまうことで、解けた問題を落としてしまうこともあるかもしれません。
そういったことを避けるためにも、本番を想定して過去問を使ってみましょう。
具体的には、項目ごと・肢ごとに過去問を解けるようになったら、総仕上げとして年度ごとに問1から問50までを時間を測って解いてみましょう。解答時間はすでに解いている問題なので1時間半ぐらいに設定するとよいでしょう。
-
こちらもチェック!
賃貸不動産経営管理士の例題
それではここで、令和5年度本試験問題を例にいくつかご紹介します。
賃貸不動産管理に関係する法令の例題
【令和5年 問23】 建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1 建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。
2 経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。
3 賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。
4 造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。
TACの解説
正解2
1 × 賃借物の修繕が必要である場合において、次の場合には、借主は、自らその修繕をすることができる(民法607条の2)。
① 借主が貸主に修繕が必要である旨を通知し、又は貸主がその旨を知ったにもかかわらず、貸主が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
② 急迫の事情があるとき
本肢のケースは②に該当するので、借主は貸主の帰国を待たずに、賃貸住宅の修繕を行うことができる。
2 〇 貸主が行うべき修繕(本肢の経年劣化により故障したトイレの修繕)を借主が行い、借主がその費用(必要費)を負担した場合、借主は貸主に対して費用の償還請求をすることができる(608条1項)。そして、借主が必要費を貸主に請求したにもかかわらず、貸主がその支払を拒む場合、借主は必要費の償還請求権を被担保債権として留置権(物から生じた債務を支払わせるために物の返還を拒むことができる権利)を行使し、賃貸借契約が終了しても、貸主が修繕費用を支払うまで賃貸住宅全体の明渡しを拒絶することができる(295条参照)。
3 × 借主が支出した費用(必要費・有益費)の償還は、貸主が賃借物の返還を受けた時から「1年以内」に請求しなければならない(622条、600条)。したがって、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、借主が貸主に対して必要費償還請求権を行使した場合、貸主はその支払を拒むことができる。
4 × 造作買取請求権排除の特約が付されていない場合、貸主の同意(承諾)を得て建物に付加した造作がある場合には、契約終了時に、借主は貸主に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる(造作買取請求権、借地借家法33条1項)。造作買取請求権は、借主の意思表示が貸主に到達すれば、借主を売主、貸主を買主とする売買契約が成立する形成権(一方的な意思表示により法律関係の効果を生じさせることができる権利)である。したがって、借主の造作買取請求権の行使により貸主の承諾がなくても当然に売買契約は成立するので、貸主は借主と造作にかかる売買契約を締結する必要はない。
賃貸住宅管理業法の例題
【令和5年 問31】賃貸住宅管理業者の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。
2 特定転貸事業者は、200戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を200戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
3 事業者が100室の事務所及び100戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
4 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。
TACの解説
正解1
1 × 事業全体において営利性があると認められる場合、委託された管理業務を無償で引き受けていたとしても、その点のみをもって直ちに営利性がないと判断されるものではないことから、賃貸住宅を200戸以上管理している場合は登録を受けることが適当であると考えられる(賃貸住宅管理業法FAQ2.(3)8)。
2 〇 賃貸住宅管理業(維持保全業務)を行っていない特定転貸事業者(サブリース業者)は、賃貸住宅管理業者に該当しないため、賃貸住宅管理業の登録をする必要がない(FAQ2.(3)10)。したがって、特定転貸事業者は、200戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を200戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
3 〇 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満である場合を除き、国土交通大臣の登録を受けなければならない(賃貸住宅管理業法3条1項、施行規則3条)。そして、事務所は賃貸住宅に該当しないので、本肢の事業者の賃貸住宅の戸数は100戸であるから、賃貸住宅管理業の登録をする義務はない(解釈・運用の考え方2条1項関係1)。
4 〇 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、例えば、登録申請日を含む事業年度の直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合、十分な資力を有する代表者からの「代表者借入金」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合など、上記の「負債の合計額が資産の合計額を超えて」いないことと同等又は同等となることが相応に見込まれる場合には、「財産及び損益の状況が良好である」と認めて差し支えない(6条10号関係)。したがって、登録拒否事由には該当しない。。
建物・設備の知識の例題
【令和5年 問12】 建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
2 1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法である。
3 2013年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられた。
4 共同住宅である賃貸住宅においても、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。
TACの解説
正解4 適切なものを〇、最も不適切なものを×とする。
1 〇 1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する(柱の帯筋間隔を30㎝→10㎝に強化等)等の建築基準法施行令改正があった。
2 〇 1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法(地震時の建物の動的な特性を大幅に取り込んで、中地震に対する1次設計(許容応力度設計)、大地震に対する2次設計(保有水平耐力の確認等)の2段階設計を採用)が、いわゆる新耐震設計法である。
3 〇 2013年に耐震改修法が改正され、一部の建物(要安全確認計画記載建築物)については、地方公共団が定める耐震改修促進計画に記載された期限までに耐震診断を実施し、その結果を所轄行政庁に報告することが義務付けられた(耐震改修法7条)。
4 × 一定規模以上の建築物で、建築基準法の耐震規定に適合しない建築物(特定既存耐震不適格建築物)の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない(努力義務、14条)。賃貸住宅(共同住宅に限る)については、3階以上かつ床面積1,000㎡以上であり、建築基準法の耐震規定に適合しない場合、特定既存耐震不適格建築物となる(14条1号、同施行令6条1項7号・2項3号)。したがって、共同住宅である賃貸住宅において、耐震改修と耐震改修を行うことについて、「努力義務」は課されているが、「義務」とはされていない。
いかがでしたでしょうか?
このように、TACでは詳細な解説を掲載しています。
全問解説が見たい方はまずは「解答解説集PDF」を請求してみてください。
TAC賃貸不動産経営管理士講座の講義が体験できます
体験Web受講では、既にご入会されている受講生と同じWeb学習環境(TAC WEB SCHOOL)にて講義をご視聴いただけます。体験受講をご希望の方は、下記項目をご入力の上、送信ください。体験Web受講の視聴方法ならびにご受講に必要なログインIDとパスワードをご連絡いたします。
お申込いただいた場合、 個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
賃貸不動産経営管理士を知ろう
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅管理に関する深い知識をもった専門家で、賃貸借契約後のトラブル対応や設備の維持・点検を行います。2021年からは国家資格としても認められており、注目度が高まっている資格です。賃貸不動産経営管理士資格の概要や仕事内容をご紹介します。詳しくはこちら »
賃貸不動産経営管理士試験は年1回、11月中旬に実施されます。受験資格や試験内容、5問免除など試験について詳しく見ていきます。詳しくはこちら »
賃貸不動産経営管理士の合格点・合格率は?難易度はどれぐらい?
賃貸不動産経営管理士は2021年度に国家資格になり、不動産業界で注目を集めている資格です。近年の賃貸住宅ニーズの増加もあり、受験者数が急増しています。難易度はどれぐらいなのか、合格点や合格率、他の不動産関連の資格との比較もまじえて解説します。 詳しくはこちら »
賃貸不動産経営管理士合格を目指す場合、試験当日まで計画的に勉強を進めることが合格への近道です。ここでは、合格に必要な勉強時間と、勉強スケジュールの立て方を解説します。 詳しくはこちら »
賃貸不動産経営管理士は独学でも合格できるのでしょうか。合格のためのテキストなど教材の選択方法についても詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。 詳しくはこちら »
賃貸不動産経営管理士を取得するメリット!実務家の経験談を聞く!
賃貸不動産経営管理士取得のメリットは?どんな人におすすめ?実務家の経験談を交えてご紹介します。 詳しくはこちら »
賃貸不動産経営管理士と宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・業務管理者の違い
賃貸不動産経営管理士は、2021年に国家資格になった比較的新しい不動産系資格です。そこで今回は、賃貸不動産経営管理士と関連資格との違いについて、仕事内容や試験・合格率などを比較しながらご紹介します。また、不動産系資格と混同しやすい「賃貸住宅管理業における業務管理者」もあわせて説明します。 詳しくはこちら »