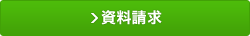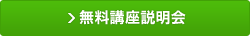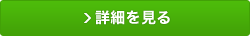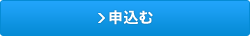令和7年度(第75回)税理士試験も
TACはズバリ的中!
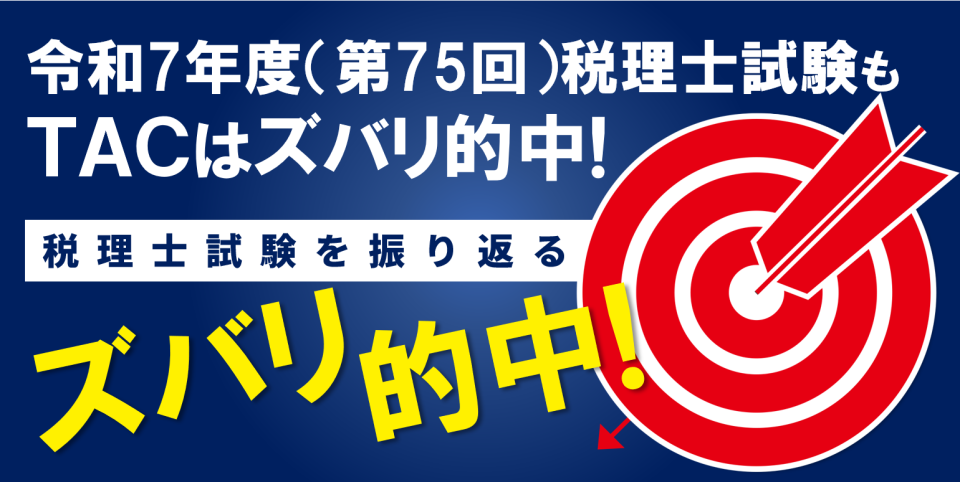
TAC講師陣が徹底分析
税理士試験を振り返る!

【簿記論】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕【資料2】 | 実力完成答練第2回 〔第三問〕7 |
| 全国公開模試〔第一問〕2 | |
| 〔第一問〕【資料3】 | 実力完成答練第6回 〔第三問〕(3) |
| 〔第一問〕【資料5】 | 実力完成答練第6回〔第三問〕4 |
| 〔第二問〕問2【資料1】 | 全国公開模試〔第一問〕3 |
| 〔第三問〕【資料2】3 | 実力完成答練第4回 〔第一問〕 |
| 〔第三問〕【資料3】5(2) | 実力完成答練第5回 〔第三問〕(3) |
| 〔第三問〕【資料2】5(3) | 直前予想答練第3回 〔第一問〕3⃣ |
| 〔第三問〕【資料2】5(6) | 実力完成答練第6回 〔第三問〕6 |
| 〔第三問〕【資料2】8(3) | 実力完成答練第1回 〔第三問〕8 |
| 〔第三問〕【資料2】9 | 実力完成答練第5回 〔第三問〕13 |
【財務諸表論】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問2(2) | 直前予想答練第3回 〔第二問〕2 |
| 〔第一問〕問3(1) | 実力完成答練第1回 〔第二問〕問2 1 |
| 〔第二問〕問1(2) | 直前予想答練第2回〔第二問〕4 |
| 〔第二問〕問2(3) | 上級演習第4回〔第二問〕4 |
| 〔第三問〕1(2) | 上級演習第10回 〔第三問〕1(2) |
| 〔第三問〕4(1) | 実力完成答練第3回 〔第三問〕4(2) |
| 〔第三問〕5(2) | 実力完成答練第1回 〔第三問〕5(2) |
| 〔第三問〕7 | 全国公開模試〔第三問〕9 |
| 〔第三問〕8 | 実力完成答練第4回 〔第三問〕11 |
| 〔第三問〕11 | 実力完成答練第4回〔第三問〕13 |
【法人税法】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問3 | 直前予想答練第1回 〔第一問〕問1 |
| 〔第一問〕問3 | 実力完成答練第6回 〔第一問〕問1 |
| 〔第一問〕問2 | 直前予想答練第1回 〔第一問〕問2 |
| 〔第二問〕【資料2】(5) | 直前予想答練第2回 〔第二問〕問1 |
| 〔第二問〕【資料2】(1)(2)(3) | 実力完成答練第2回 〔第二問〕【資料2】 |
| 〔第二問〕【資料3】 | 実力完成答練第5回 〔第二問〕【資料2】 |
| 〔第二問〕【資料4】 | 実力完成答練第5回 〔第二問〕【資料1】 |
| 〔第二問〕【資料5】(1)(2)(3) | 直前対策補助問題第1回 【資料3】 |
| 〔第二問〕【資料5】(4) | 実力完成答練第3回 〔第二問〕【資料5】(4) |
| 〔第二問〕【資料5】(7) | 実力完成答練第3回 〔第二問〕【資料5】(6) |
| 〔第二問〕【資料5】(8) | 実力完成答練第6回 〔第二問〕【資料3】 |
| 〔第二問〕【資料6】 | 全国公開模試 〔第二問〕問2 |
【所得税法】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問1 | 全国公開模試〔第一問〕問1 |
| 〔第一問〕問2 | 実力完成答練第3回 〔第一問〕問2 |
| 〔第ニ問〕問【資料Ⅱ】1(2) | 直前予想答練第2回 〔第二問〕問2【資料Ⅰ】 |
| 〔第ニ問〕問【資料Ⅱ】3 | 直前対策補助問題第7回〔第二問〕【資料Ⅱ】3 |
| 〔第ニ問〕問【資料Ⅲ】ゴルフ会員権の説明部分 | 直前対策補助問題第1回〔第二問〕【資料Ⅲ】1 |
| 〔第ニ問〕問【資料Ⅳ】1 | 実力完成答練第1回 〔第二問〕問2 |
| 〔第ニ問〕問【資料Ⅷ】(2) | 実力完成答練第1回 〔第二問〕問2 4(1) |
【相続税法】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕(2) | 実力完成答練第6回〔第一問〕問2 |
| 〔第二問〕問1 2 | 実力完成答練第1回 〔第二問〕2 |
| 〔第二問〕問1 3(3) | 実力完成答練第6回〔第二問〕4(7) |
| 直前対策補助問題第5回3(1) | |
| 〔第二問〕問1 6 | 実力完成答練第3回〔第二問〕6(1) |
| 〔第二問〕問1 3(4) | 実力完成答練第3回〔第二問〕3(3) |
| 〔第二問〕問1 3(7) | 直前予想答練第1回 〔第二問〕3(9) |
| 〔第二問〕問1 4 | 直前予想答練第1回〔第二問〕5 |
【消費税法】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問1(1) | 全国公開模試〔第一問〕問1(1)(3) |
| 実力完成答練第1回〔第一問〕問1(1) | |
| 合格情報補助問題〔第一問〕問2(3) | |
| 〔第一問〕問1(2) | 実力完成答練第4回〔第一問〕問1(1) |
| 〔第一問〕問2(2) | 直前予想答練〔第一問〕問2(2)③ |
| 合格情報補助問題〔第一問〕問2(1) | 〔第二問〕(1)【損益計算書に関する付記事項】ハ チ(イ) | 直前対策補助問題第4回〔第二問〕問1【損益計算書に関する付記事項】ホ ワ |
| 〔第二問〕(1)【損益計算書に関する付記事項】ト(ロ) | 実力完成答練第1回〔第二問〕【資料】Ⅴリ(イ) |
| 〔第二問〕(1)【損益計算書に関する付記事項】レ(ロ) | 実力完成答練第3回〔第二問〕問1(2)② |
| 〔第二問〕(2)【製造原価報告書に関する付記事項】イ | 全国公開模試〔第二問〕問1【飲食店業に係る損益計算書に関する付記事項】ニ(イ)(ロ) |
| 〔第二問〕(2)【製造原価報告書に関する付記事項】ホ(ロ) | 直前予想答練〔第二問〕問2 5 ヲ(イ) |
| 〔第二問〕(1)【損益計算書に関する付記事項】ラ(イ)(4)ニ | 実力完成答練第4回〔第二問〕問1<損益計算書及び完成工事原価報告書に関する付記事項>ル(ホ)(5)ロ |
| 〔第二問〕(4)ロ | 直前予想答練〔第二問〕問2 6イ |
| 〔第二問〕(5) | 実力完成答練第1回〔第二問〕【資料】Ⅱ(2) |
| 〔第二問〕(6) | 実力完成答練第2回〔第二問〕問2 3 |
【酒税法】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問1(2) | 全国公開模試〔第一問〕問2 |
| 〔第一問〕問1(5) | 直前予想答練〔第一問〕問1(3) |
| 〔第ニ問〕【資料5】B | 全国公開模試〔第二問〕G |
| 〔第ニ問〕【資料5】D | 実力完成答練第1回〔第二問〕G |
| 〔第ニ問〕【資料5】F | 実力完成答練第1回〔第二問〕I |
| 〔第ニ問〕【資料5】G | 実力完成答練第4回〔第二問〕C |
| 〔第ニ問〕【資料】10 | 実力完成答練第4回〔第二問〕14 |
| 〔第ニ問〕【資料】11 | 全国公開模試〔第二問〕10 |
| 〔第ニ問〕【資料】12 | 全国公開模試〔第二問〕11 |
【固定資産税】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 | 〔第二問〕問1 | 実力完成答練第2回〔第二問〕問1 | 〔第二問〕問2 | 全国公開模試 〔第二問〕問2 |
|---|
【事業税】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問1(2) | 実力完成答練第1回〔第一問〕問2 |
| 〔第二問〕問1【資料】3 | 実力完成答練第4回〔第二問〕【資料】3 |
| 〔第二問〕問1【資料】4X県利息 | 実力完成答練第4回〔第二問〕【資料】7C県利息 |
| 〔第二問〕問1【資料】6 | 全国公開模試〔第二問〕問1【資料】6 |
| 〔第二問〕問1【資料】9 | 実力完成答練第1回〔第三問〕【資料】8 |
| 〔第二問〕問2【資料】4 | 直前対策補助問題第2回〔第三問〕【資料】2、5 |
| 〔第二問〕問2【資料】5 | 直前対策補助問題第2回〔第三問〕【資料】8 |
| 〔第二問〕問2【資料】5(注5) | 直前対策補助問題第2回〔第二問〕【資料】4(注2) |
【住民税】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問2 | 全国公開模試〔第一問〕問1 |
| 〔第二問〕【資料】(1)⑤ | 実力完成答練 第1回〔第二問〕【資料】(1)⑨ |
| 〔第二問〕【資料】(2)⑤ | 直前対策補助問題第2回【資料Ⅱ】(2)⑤ |
| 直前対策補助問題第3回【資料Ⅰ】(7) | |
| 直前対策補助問題第4回【資料】(1)⑩ | |
| 〔第二問〕【資料】(5)② | 実力完成答練第2回〔第二問〕【資料】(1)⑤ |
| 〔第二問〕【資料】(5)④ | 全国公開模試〔第二問〕(1)③ |
| 実力完成答練第2回〔第二問〕【資料】(1)② |
【国税徴収法】の的中実績
| 本試験問題 | TAC予想問題 |
|---|---|
| 〔第一問〕問1(1) | 実力完成答練第2回〔第一問〕1(1) |
| 〔第一問〕問2(1) | 実力完成答練第1回〔第二問〕事例6 |
| 〔第一問〕問2(2) | 合格情報補助問題〔第一問〕2 |
| 〔第二問〕問1 | 実力完成答練第1回〔第一問〕2問1 |
| 〔第ニ問〕問4 | 実力完成答練第3回〔第一問〕1 |

本試験後の受験プランニング
ひと時の休息を過ごされた後は、来年度の合格に向けて新たな受験プランニングをしっかりと立てましょう。次の科目に進むべきか? どのコースが自分にとって最適なのか? を当ページにて確認できます。早期に今後の方向性を決め、新たな気持ちで次年度に向けて学習をスタートしてください!